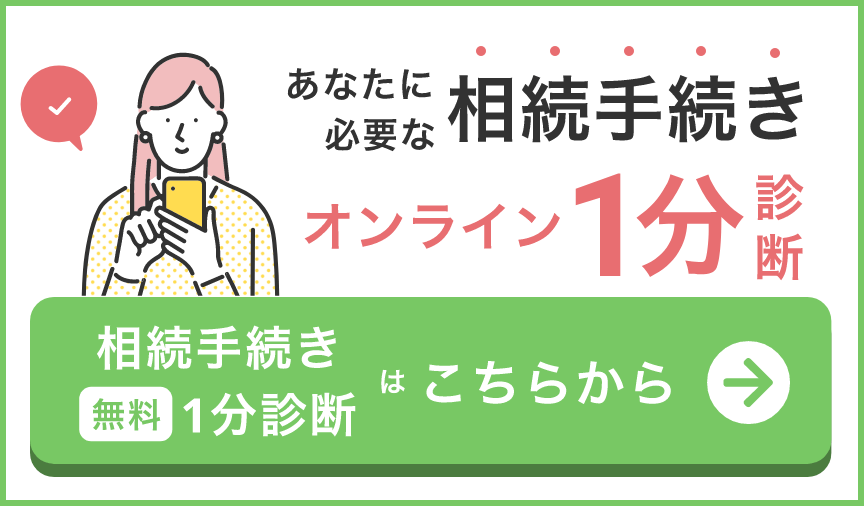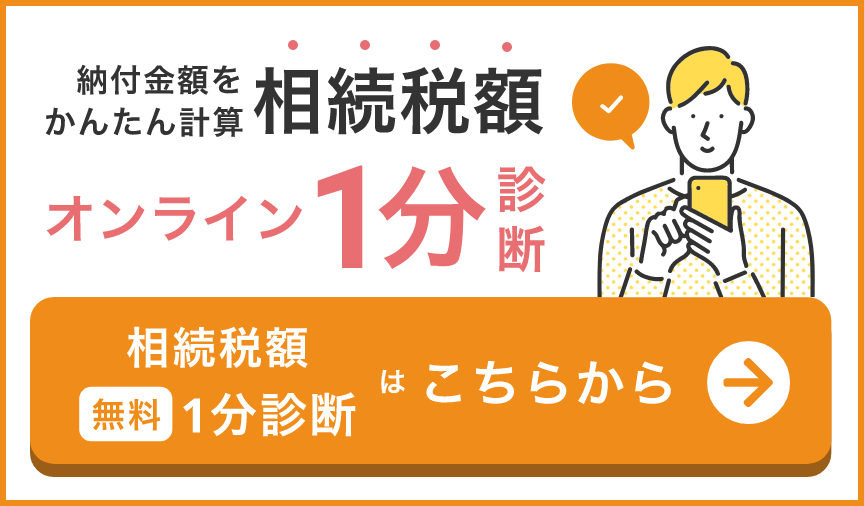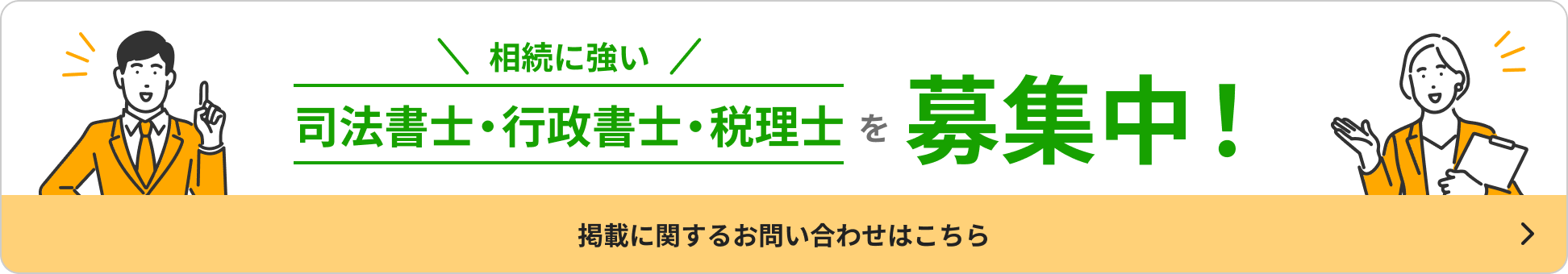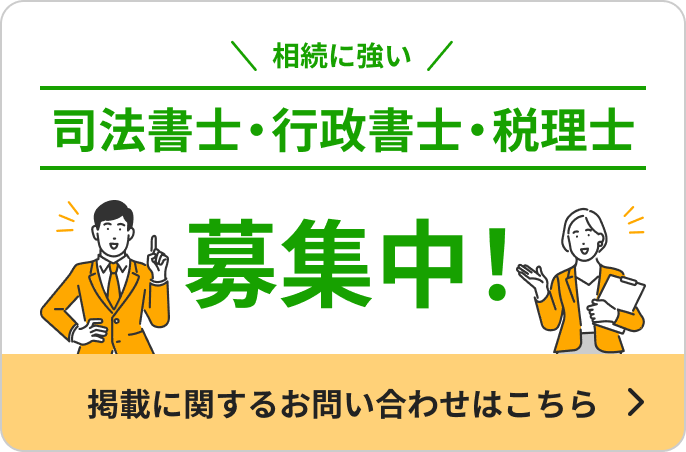遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求との違いや期限・対象を詳しく解説【弁護士監修】

相続は本来、被相続人の意思が尊重されるもの。ただし法定相続人は、遺言にその名が記されていなくても生活保障の意味合いから一定の遺産が配分される権利を認められており、一定の要件を満たす場合には遺留分として遺産の配分を受ける権利があります。
遺留分を請求する際の制度である遺留分減殺請求は、2019年7月の法律改正により遺留分侵害額請求と改称されました。新旧それぞれの法律の特徴を把握しておかないと、適切に遺留分請求ができなくなる可能性があります。
今回の記事では、遺留分減殺請求の概要や遺留分減殺請求の行使方法、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い、請求に関する注意点やよくある疑問などについて解説します。なおこの記事では、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求のどちらにも該当する部分を遺留分減殺(侵害額)請求として表記しています。


この記事の監修者

不動産のある相続問題の解決を得意とし、他士業とも連携して依頼者に最適な解決を目指す。『相続のことがマンガで3時間でわかる本』など執筆も多数。一般社団法人相続総合支援協会理事。
▶ みらい総合法律事務所
目次
遺留分減殺(侵害額)請求とは?
遺留分減殺(侵害額)請求とは、特定の法定相続人が遺言によって相続人に指名されなかった場合、つまり本来受け取れるはずだった遺産を侵害された場合に遺留分として請求すること。これは、権利として認められているものです。
まずは遺留分減殺(侵害額)請求の概要について解説していきましょう。
遺留分の意味をチェック
遺留分とは、被相続人が遺言によって相続相手としなかった特定の法定相続人に対して、相続財産の中で認められる一定の遺産の分配のことです。
遺産相続は、基本的に被相続人の意思を尊重します。したがって、法律で定めた形式に則った遺言書が作成されていた場合、遺言書の内容に従って相続がおこなわれるのです。

たとえば、被相続人と血縁関係にない人が遺言書で相続人に指名されていたとしても、その人の相続は認められます。場合によっては「遺産をすべて慈善団体に寄付する」などと書かれているケースもありますが、これも遺言書の内容どおりに相続がおこなわれるのです。
しかし、民法において法定相続人は最低限の遺産配分を、遺留分として受け取る権利を認められています。法定相続人は第一順位から第三順位まで、被相続人との関係によって順位づけされており、法定相続をおこなう場合には第一順位の相続人から順番に相続権が認められているのです。
遺留分が認められているのは、基本的に法定相続人の中でも第一順位と第二順位にあたる人々です。
遺留分がある相続人とその割合

遺留分が認められている相続人は以下の人々です。
- 被相続人の配偶者(第一順位の相続人)
- 被相続人の子と代襲相続ができる直系卑属(第一順位の相続人)
- 相続人の直系尊属(第二順位の相続人)
法定相続人の定義の中では、第三順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹が該当しますが、この第三順位の相続人には遺留分の権利を認めていません。
したがって、被相続人が兄弟姉妹に財産を相続したくないと考えた場合には、遺言書に兄弟姉妹に相続させない(他の者に相続させる)旨を明記すれば目的は達成できます。
遺留分については改正前の民法第1028条において「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ該当各号に定める割合に相当する額を受ける。」と規定されています(改正後の民法第1042条にも同様の規定があります)。同法律において遺留分の割合は、
- 直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1
- 前号掲げる場合以外の場合、被相続人の財産の2分の1
と規定されています。つまり、遺留分減殺(侵害額)請求権を持つ特定の法定相続人の親族関係及び人数によって、その割合は変化するのです。
▼今すぐ診断してみましょう▼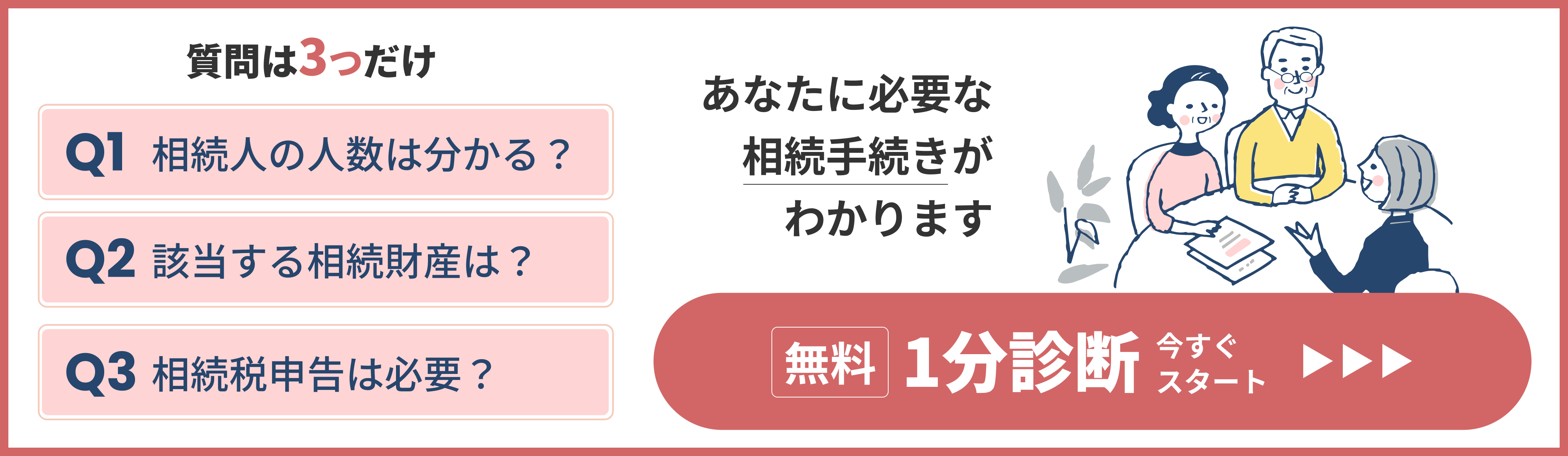
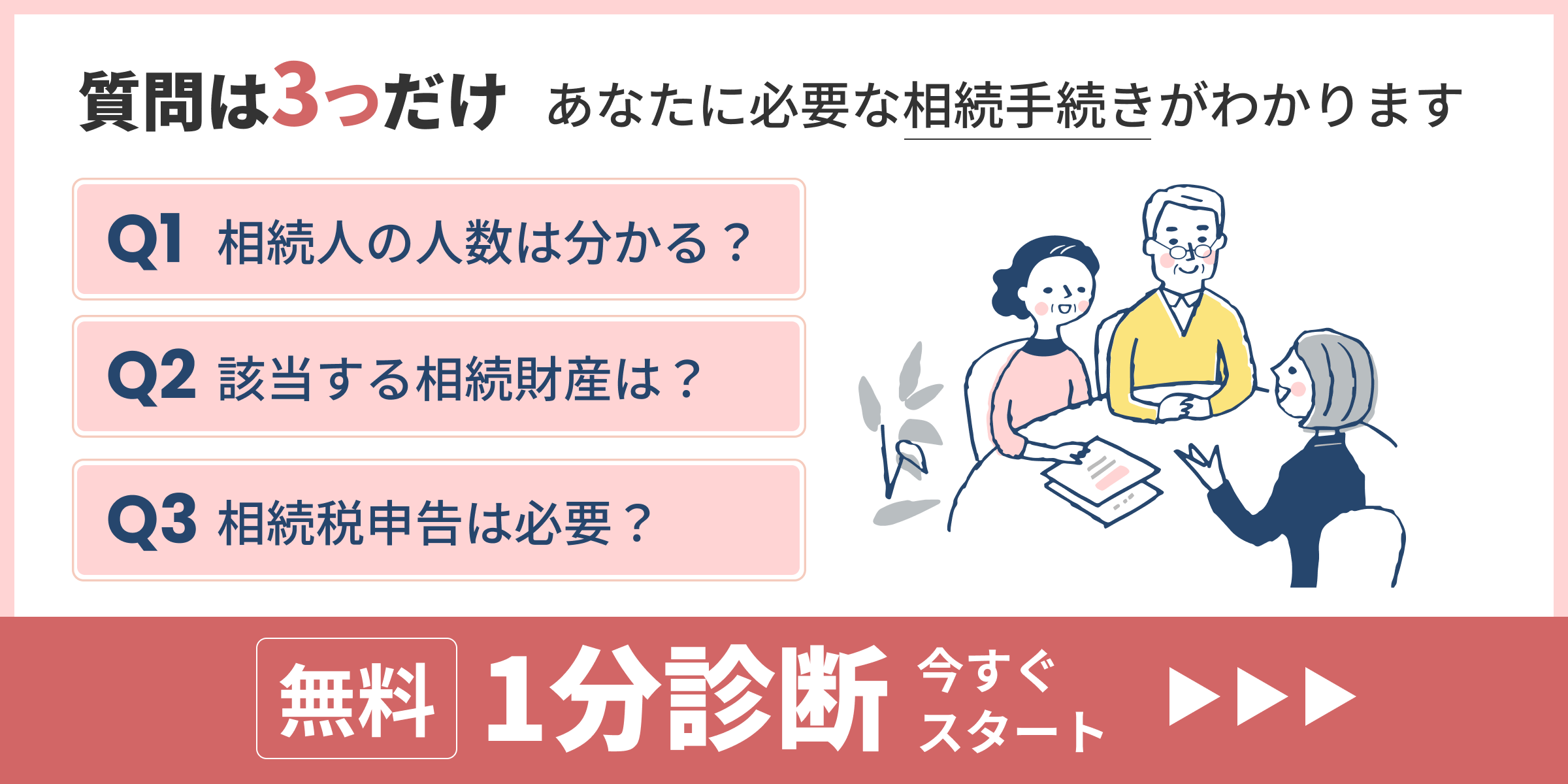
遺留分減殺(侵害額)請求権の行使方法

遺留分減殺(侵害額)請求を行使する方法について解説しましょう。
裁判所を介する必要はない
相続自体は、遺留分が発生しても遺言書の内容に従って遺産分割をおこなうことが可能です。したがって遺留分が認められている特定の相続人が何の申し立てもしなければ、そのまま遺産分割がおこなわれるでしょう。
遺留分減殺(侵害額)請求の権利を行使する場合、法律で決まった手順はありません。したがって裁判所を介する必要はなく、遺留分を侵害して相続財産を受け取っている相続人と直接交渉して請求します。
遺留分減殺(侵害額)請求をおこなう場合には、まず遺言の内容と相続人の数を把握し、相続財産を確認しましょう。遺言書に記載のない相続財産があれば、その財産は遺産分割協議の対象となり、その結果、遺留分を侵害しないかもしれません。
内容証明郵便が一般的
遺留分減殺(侵害額)請求をおこなう場合、手続きの方法は決められていないため、口頭で相手と交渉しても問題はありません。しかし、交渉がスムーズに進まない場合には、内容証明郵便を送って遺留分減殺(侵害額)請求をおこなうのが一般的です。請求したという事実を証拠として残し、請求する権利が時効消滅するのを防ぐためです。
請求のための書面を作成する場合、請求すべき金額などを細かく記入する必要はなく、あくまでも遺留分減殺(侵害額)請求の行使をおこなう点を主張していれば問題ありません。
内容証明郵便を送る際の文書に決まった書式はありませんが、以下に示す事項を記載しておくと良いでしょう。
- 相手方の住所と氏名
- 作成日
- 申立人の住所と氏名
- 被相続人の遺言書によって遺留分が侵害されている事実
- 本書面をもって遺留分減殺(侵害額)請求をする意思
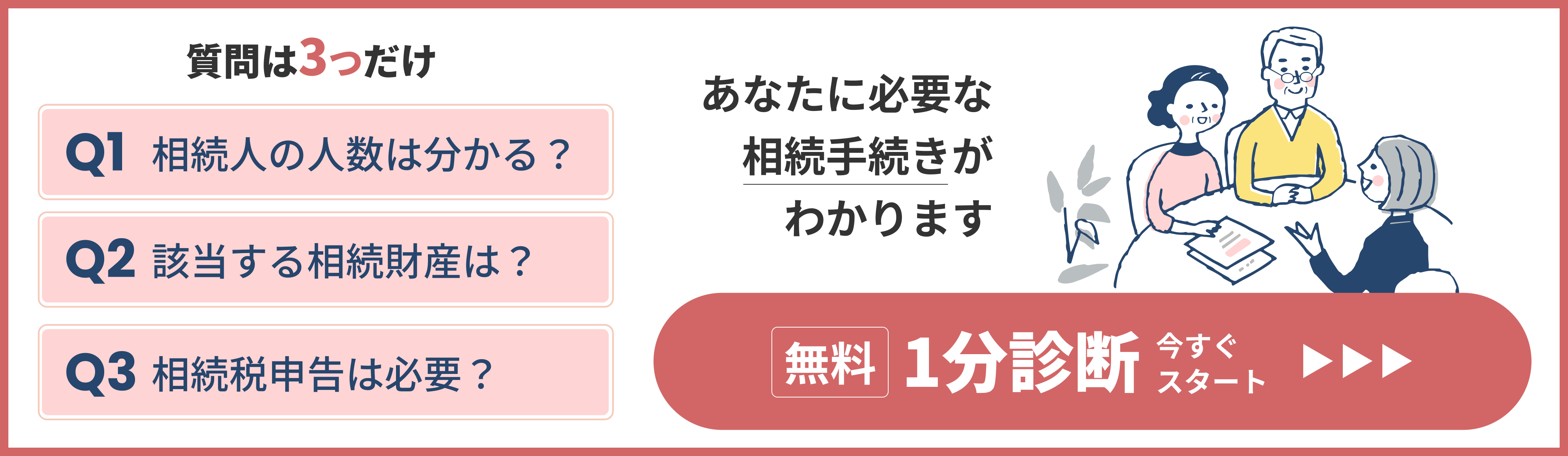
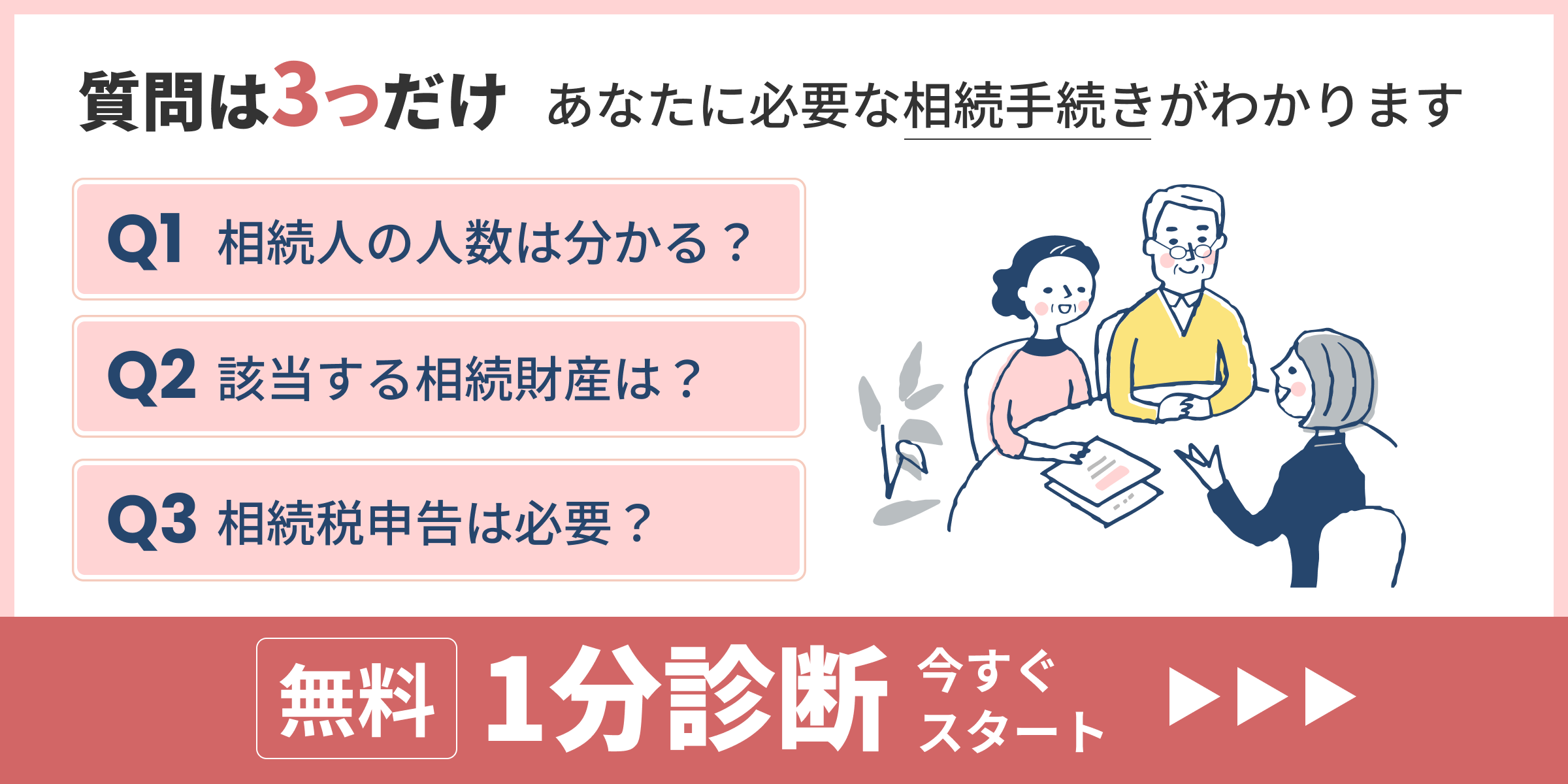
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いとは

本記事では、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求を併記するために「遺留分減殺(侵害額)請求」としていますが、それには意味があります。
これまで遺留分請求は遺留分減殺請求と呼称されていましたが、2019年の法改正によって遺留分侵害額請求へと名称が変更となりました。そこでここからは、それぞれの違いについて解説していきましょう。
遺留分減殺請求は旧制度
遺留分請求については、2019年6月30日まで遺留分減殺請求という名称が用いられていました。これは民法1031条によって規定されており「遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる」と定められていたのです。
遺留分減殺請求では、遺留分を請求すると現金だけではなく、不動産も均等に減殺されます。以前は、遺留分の持つ権利は「物権的請求権」と理解されており、侵害された遺産そのものを取り戻すことが権利として認められていました。
しかし、例えば遺留分減殺請求した後に不動産を共同所有することになった場合では、修繕や売却などの費用負担を巡ってトラブルに発展することが多く、感情的に両者が対立することも。
そのため、この方式は最適ではないと考えられ、2019年7月1日の法改正において名称を「遺留分侵害額請求」と改め、この点が改善されました。
遺留分侵害額請求は金銭請求に一本化

遺留分侵害額請求については改正後民法第1046条によって「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(中略)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」と規定されています。
遺留分減殺請求との最も大きな違いは、請求する権利が金銭請求に一本化されたことです。これにより遺留分侵害額請求後に不動産を共同所有するといったことがなくなり、金銭だけの相続を受けることが可能となったのです。
金銭請求以外の改正点
遺留分侵害額請求権における金銭請求以外の改正点は、遺留分を算定する場合の贈与財産について、最大でも10年前までしか遡及できなくなった点です。
被相続人が特定の相続人に対して20年にわたって生前贈与をおこなっていた場合でも、遺留分侵害額請求の対象になるのは直近の10年分までとなります。
また、遺留分侵害額請求権の行使と、金銭債権の履行請求を同時におこなうことができるようになりました。これにより、金銭債権の行使をおこなうと同時に相手方には遅延損害金を支払う義務が発生します。
支払いの猶予が認められるケースも
遺留分侵害額請求を受けた相手方が不動産を含めた相続を受けている場合、金銭を請求されても不動産分の遺留分侵害額に相当する現金を持っていない可能性があります。
そこで、改正された民法第1047条第5項では「裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる」と規定しています。
これは、法改正によって相手方に遅延損害金が発生することになった場合に、相手方の負担が過大にならないように配慮された結果です。
これにより、相手方は現金による弁済が難しい場合には裁判所に請求し、支払い期限を相当期間猶予してもらえることになりました。
この請求が認められれば、猶予期間中に遅延損害金は発生しません。
▼今すぐ診断してみましょう▼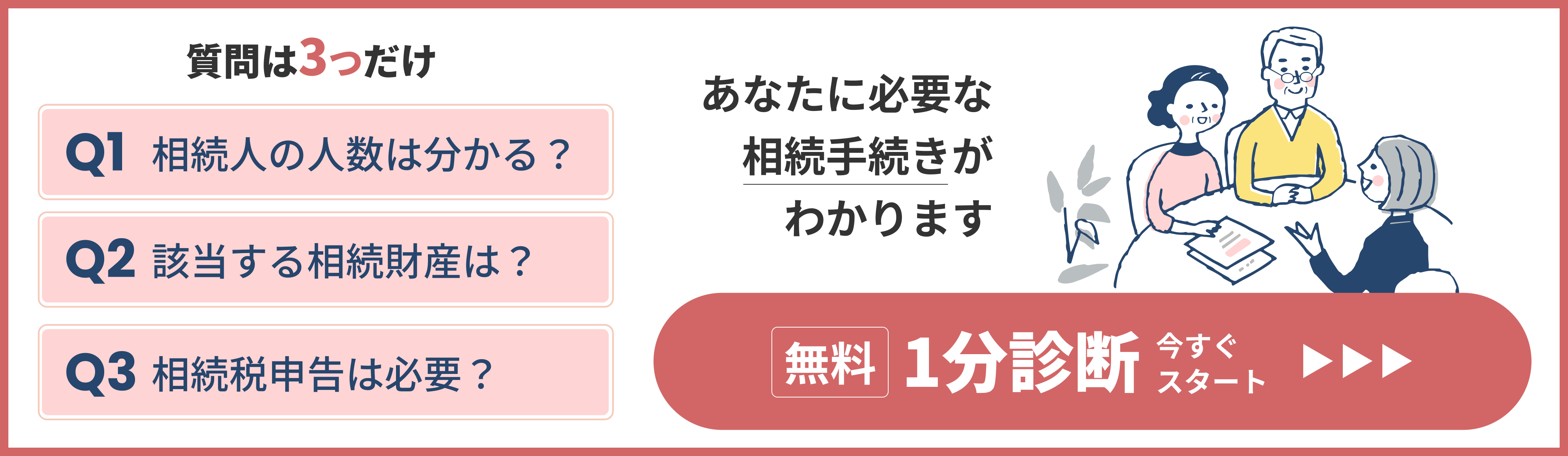
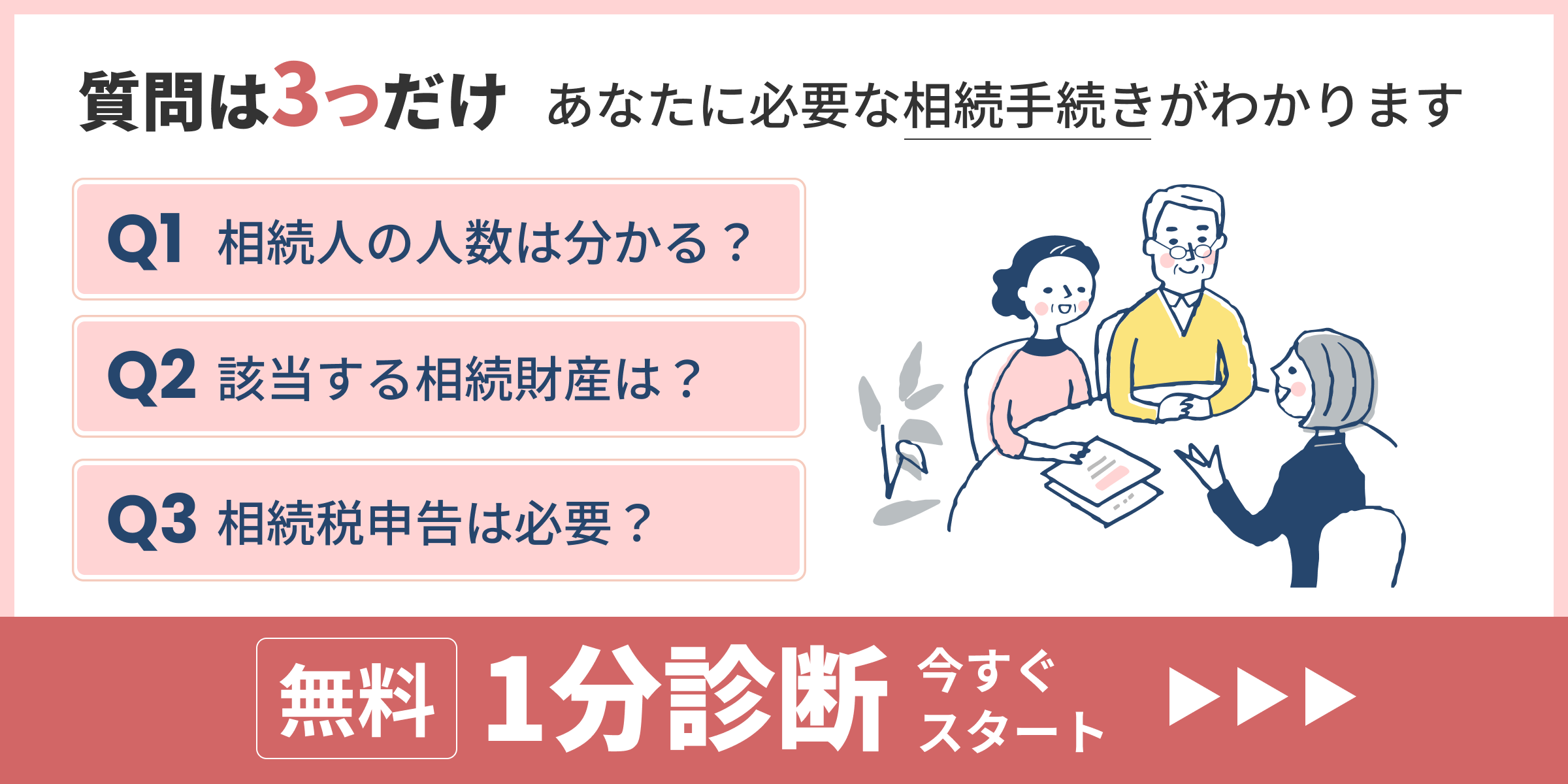
遺留分侵害額請求ができるのはいつから?

遺留分減殺請求、また遺留分侵害額請求は、それぞれどのタイミングで行使できるのでしょうか。ここでは、2つの遺留分請求が可能なタイミングについて解説していきます。
2019年7月1日以降の相続が対象
遺留分侵害額請求の対象は、改正された相続法が施行された2019年7月1日以降の相続(被相続人が亡くなった日が2019年7月1日以降)です。したがって、これから発生する遺留分請求のほとんどは遺留分侵害額請求に則っておこなわれます。
2019年7月1日より前は遺留分減殺額請求権の対象
2019年6月30日までに発生した相続については、旧法である遺留分減殺請求権によって請求がおこなわれます。
現時点で発生した相続について遺留分減殺請求権が適用されることはありませんが、過去にさかのぼって遺留分請求をおこなう場合には、遺留分減殺額請求権が適用されます。
遺留分侵害額請求における遺留分侵害として認められるケース
遺留分侵害額請求は状況によって認められる場合があります。ここでは、遺留分侵害額請求における「遺留分侵害」として認められるケースについて解説します。
相続開始1年以内になされた贈与及び贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を与えることをわかった上での贈与
相手方に生前贈与がおこなわれていた場合でも、相続人でない者に対する贈与は、相続開始から1年間まで遡って遺留分算定の基礎となる相続財産の価額に算入することができます。相続開始から1年以内でなくても、被相続人と受贈者が遺留分権利者の遺留分が減ることがわかったうえで贈与をおこなっていた場合には、遺留分請求の対象として加算されます。
遺留分権者に損害を与える意思がなかったとしても、生前贈与によって遺留分権利者の遺留分が減少するという事実を知っているだけで、加害の意思に関係なく基礎財産に加算され、遺留分侵害額請求の対象になります。
譲渡の対価は支払っているが、譲渡された物の価値と釣り合っていない
被相続人が、所有する不動産を一般的な売買価格とかけ離れた廉価で譲渡していた場合「不相当な対価と認められる」「被相続人と受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」という2つの条件を満たすこととなり、不動産本来の流通価格との差分を遺留分算定の基礎となる相続財産の価額に算入できます。
特別受益にあたる贈与
相続のうち、相続人に対する贈与で特別受益に該当する贈与がある場合は、相続開始から10年間遡って遺留分算定の基礎となる相続財産への算入が可能です。改正後民法第1044条3項が規定しているように同1項の規定を読み替えると、「贈与は、相続開始前の10年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額(中略) を算入する。 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前の日より前にしたものについても、同様とする」となります。
2019年7月1日の民法改正では特別受益の適用範囲を拡大しており、法改正前は1年以内の特別受益が遺留分算定の基礎となる相続財産への算入の対象でしたが、改正によって適用範囲が10年に拡大されました。また、被相続人と特別受益を受けた相続人が遺留分権利者に損害を加えると知ったうえで特別受益をおこなった場合には、10年以上前の特別受益でも遺留分算定の基礎となる相続財産への算入が認められています。
遺留分侵害は判断が難しく、弁護士への依頼がおすすめ
遺留分侵害として認められるケースは多いと思われますが、その計算は非常に複雑です。
また「遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした」と認められるかどうかの判断も難しいため、遺留分減殺(侵害額)請求をおこなう場合には弁護士に依頼し、遺留分請求権の可否や請求業務を依頼するほうが、正確な遺留分請求をおこなえます。遺留分請求を検討している場合には、まず弁護士に相談してみると良いでしょう。
遺留分侵害額請求権が消滅するケース
遺留分侵害額請求が認められるケースがある一方で、遺留分侵害額請求権が消滅してしまう可能性もあります。ここでは、遺留分侵害額請求が消滅するケースを解説します。
相続の開始などを知ってから1年間行使しないとき
遺留分侵害額請求権は、民法第1048条において「遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する」と規定されています。通常、被相続人の死亡後、遺言の内容を知ることによって遺留分侵害を知ることが多いでしょうから、遺留分侵害請求を行う場合には遺言の内容を知ってから1年以内に権利を行使しなければならないと考えておけばいいでしょう。もっとも、事案によって異なりますので、早めに弁護士に相談することが重要です。
相続開始から10年を経過したとき
民法第1048条では、上記の相続と遺留分侵害を知ってから1年以内に遺留分を請求しないと時効によって消滅すると規定していますが、同じ条文のなかで「相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする」と規定しています。
つまり、相続と遺留分侵害を知らずに相続開始から10年が経過すると遺留分を請求する権利がなくなるのです。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼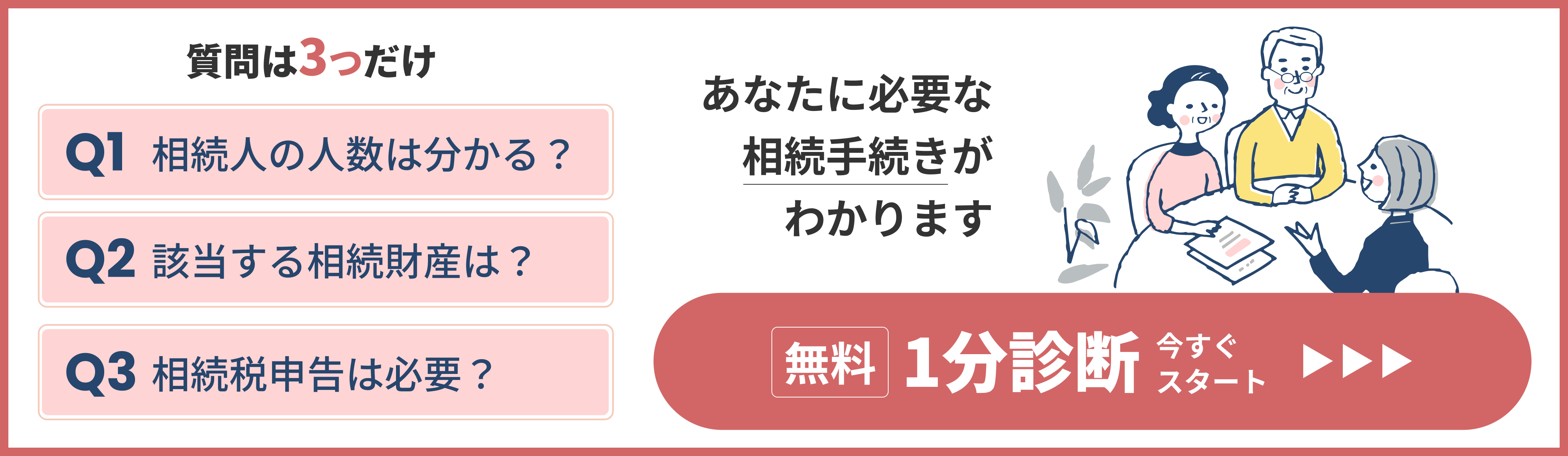
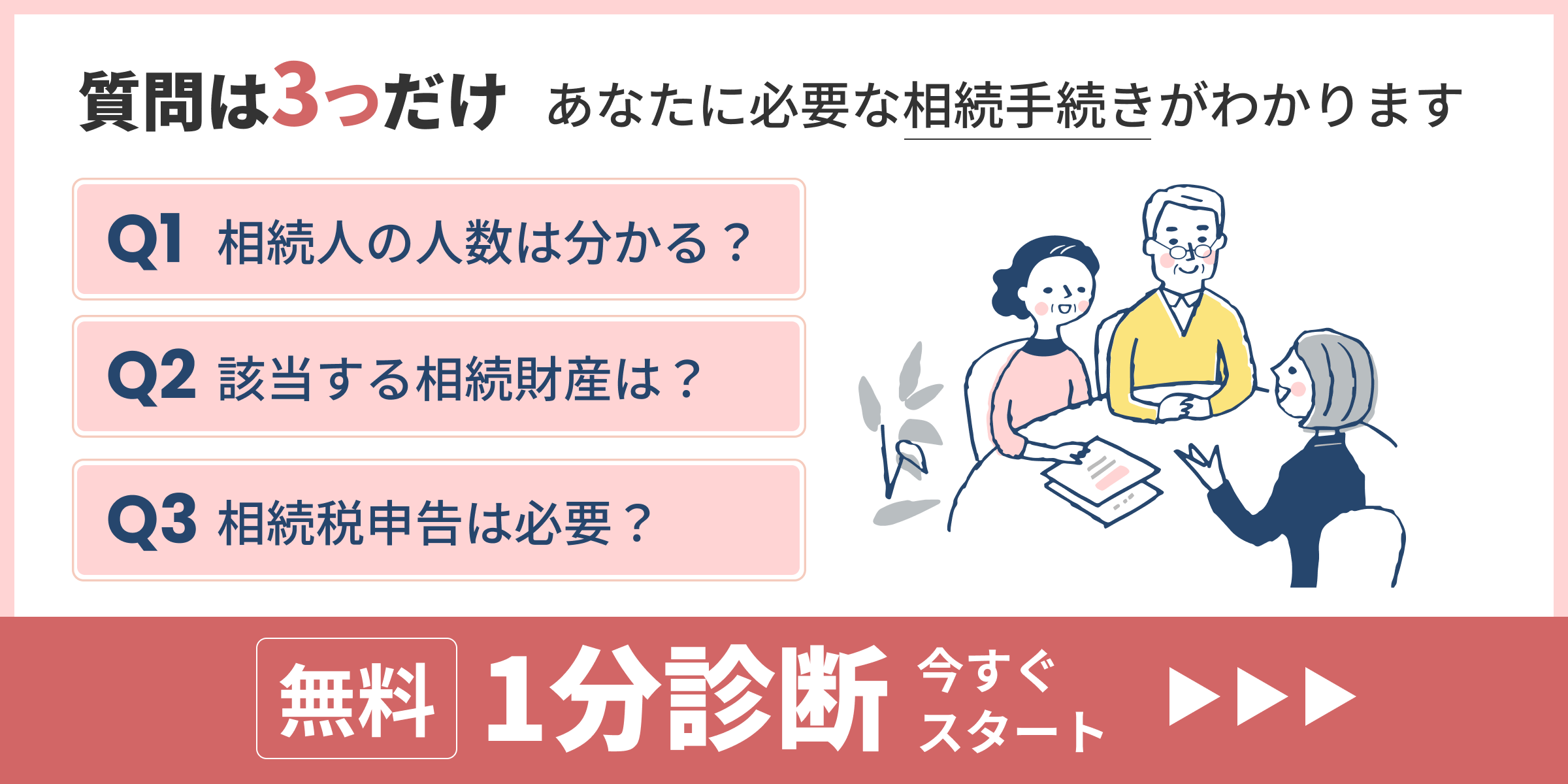
遺留分減殺請求のよくある疑問
最後に、遺留分減殺請求についてよくある疑問とその答えをまとめます。
Q.請求に応じない場合、最初から訴訟を提起することはできませんか?
遺留分侵害額請求には調停前置主義が採用されており、訴訟の前に調停を実施すべきと考えられています。ただし、調停が成立する見込みがないことが明らかであると家庭裁判所の裁判官が認める場合には、訴訟から始まる場合もあるでしょう。
とはいえ、基本的には調停前置主義が優先されているため、よほどの事情がなければ調停から始まると考えておいたほうが良いです。
Q.遺言無効の訴訟中でも遺留分侵害額請求を行使すべきですか?
行使すべきです。なぜなら遺留分侵害額請求権は、相続と遺留分侵害を知ってから1年以内に行使しないと権利が消滅するからです。
遺言無効の訴訟に1年以上かかり、結果的に遺言が有効だと判断されてしまうと遺留分侵害額請求が行使できなくなってしまいます。ですから、遺言の効力を争っている場合は同時進行で遺留分侵害額請求をおこないましょう。
Q. 「遺留分権利者に損害を与えることを知ったうえで贈与をした」という事実はどう証明する?
遺留分減殺(侵害額)請求に関連する民法には「遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした」という条文があります。この点については明確な基準は設けられていませんが、加害の意志よりも、客観的に遺留分権利者に損害を加えることになる事実関係を知っているかどうかで判断されるものです。
明確に証明が難しいことから個人で立証することは難しく、弁護士や裁判官の力を借りながら証明してくのが一般的な方法といえます。
まとめ
遺留分減殺(侵害額)請求は、遺言書による相続などで相続すべき遺産が配分されなかった場合に、遺留分侵害をしている相続人から遺留分を請求する権利です。
今回は
- 遺留分減殺請求権の行使方法
- 遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いとは
- 遺留分侵害額請求が適用される時期
- 遺留分侵害額請求権が消滅するケース
について紹介しました。
遺留分減殺(侵害額)請求にあたっては、相続財産やどの相続人が遺留分侵害をしているかの把握、遺留分請求金額の算出など、非常に煩雑な手続きが必要です。
また、過去に遡って生前贈与の事実や金額を調査し、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした可能性があればその事実を証明する必要があります。直面している遺留分侵害にどの法律が適用されるかも判断が難しく、つまりは実務・知識の両面で遺留分減殺(侵害額)請求を一人で進めるのは非常に難しいといえるでしょう。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能です。遺留分減殺(侵害額)請求でお困りの方はお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、専門家に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。


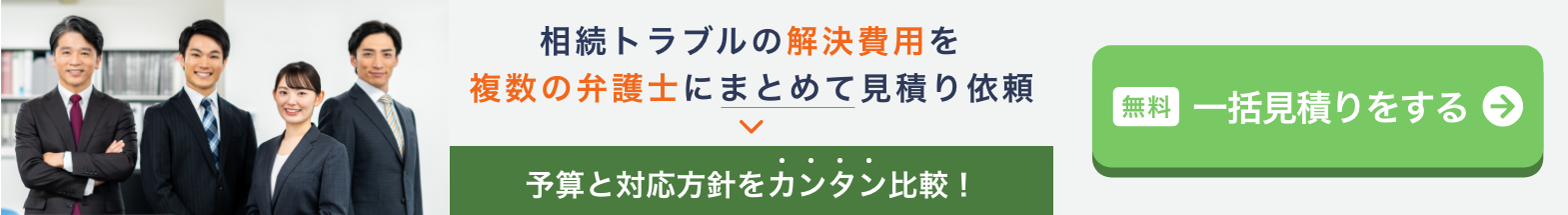
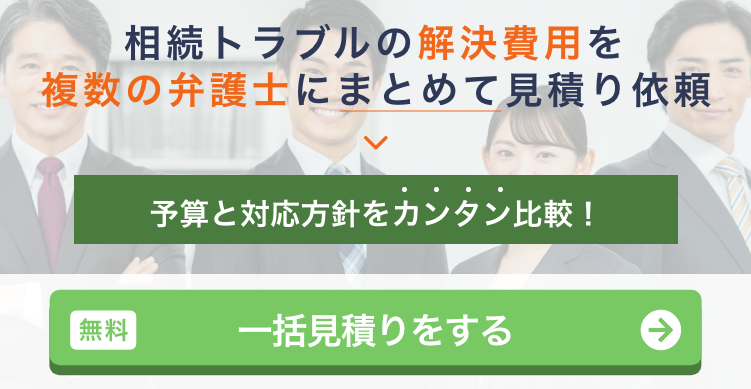

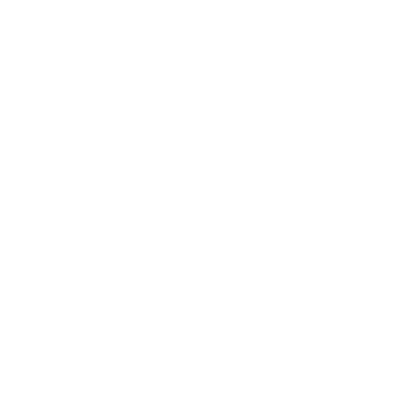
 Webで無料相談はこちら
Webで無料相談はこちら