相続税の基礎知識|相続税の対象になる財産と計算方法、控除額、申告と納税の仕方【税理士監修】
相続に関する法律や制度の改正により、一部のお金持ちだけでなく一般の人にも身近になった相続税。かつての相続税は相続件数の約4%のみが課税対象で、一部の富裕層のみに関係する税金でした。しかし、平成27年の税制改正では基礎控除額が大幅に引き下げられ、課税対象者が約2倍に拡大しました。現在では首都圏を中心とする不動産価格の上昇も相まって、対象者はさらに増加傾向にあり……
相続に関する法律や制度の改正により、一部のお金持ちだけでなく一般の人にも身近になった相続税。かつての相続税は相続件数の約4%のみが課税対象で、一部の富裕層のみに関係する税金でした。しかし、平成27年の税制改正では基礎控除額が大幅に引き下げられ、課税対象者が約2倍に拡大しました。現在では首都圏を中心とする不動産価格の上昇も相まって、対象者はさらに増加傾向にあり……
相続人の中に相続時精算課税適用者がいる場合、相続税の申告はどのように行えばよいのでしょうか? この記事では、申告が必要になるケース、相続税申告書の書き方、添付書類等についてわかりやすく説明します。 この記事を書いた人 ……
故人の相続財産を継承する手続き、遺産相続では、いつまでに行わなければならないと定められたもの、明確な期限はないがなるべく早めに手続きを済ませておいた方が良いものなど、手続きの種類によっても異なります。 この記事では、遺産相続の流れを一覧表にし、各種手続きの内容、期限についてご説明していきます。 遺産相続手続きの一覧 亡くなられた方の財産(遺産)を引き継……
相続税には、様々な特例が用意されています。 特例の適用を受けることによって、相続税をかからなくしたり、税額を低く抑えたり、納税の猶予を受けることができます。 この記事では、相続税の特例を活用して徹底的に節税する方法について説明します。 この記事を書いた人 ……
身内が亡くなったとき、遺族は悲しみに浸る間もなくさまざまな業務に追われます。葬儀などが一通り終わった後に、やらなければならないのが相続に関する手続きです。 誰がどれだけ相続するのか、相続税はいくらになるのかを計算するために、まずは相続財産調査をして故人の遺産がどれだけあるのかをきちんと把握しておくことが重要です。 今回は、相続財産調査について、相続財産の……


身近な人が亡くなって相続人となったものの、他の相続人に遺産を譲りたい場合は、相続放棄をすることが考えられます。 このようなケースにおいて、遺産を取得する相続人から、印鑑証明書を求められることがあります。 相続放棄に印鑑証明書は必要なのでしょうか?必要ないとすれば、なぜ、その人は印鑑証明書を求めるのでしょうか?そして、求められた場合には、印鑑証明書を渡すべ……
亡くなった親が借金等によって債務超過の状態であった場合や、母に父の遺産を譲りたい場合等、兄弟全員でまとめて相続放棄をすることがあります。この記事では、兄弟全員でまとめて相続放棄をする場合の注意点、手続き、必要書類等について説明します。 この記事を書いた人 ……
相続が発生した際に誰が相続人になるかは、民法で定められています。相続放棄をすると、次の相続順位の人に相続権が移ります。 亡くなった人が借金等で債務超過であった場合は、相続放棄をしないと、債務を相続して悲惨な目にあってしまいます。 自分が相続放棄をすることによって、誰に相続権が移るのか、そして、その人も相続放棄をした場合はどうなるのか?親戚関係のどこまで相……
相続の手続きにはさまざまな書類が必要となります。必ず必要なものもあれば、状況によって必要となる書類。さらに、必ず必要ではないけれど、あると便利な書類などもあります。この記事では、相続の流れを簡単にご説明した後に、各種相続に必要な書類やその取得方法について、場面ごとにまとめています。 相続の流れ 相続の主な流れは、一般的に次のような順序で進……
持ち家がない人が宅地を相続すると、相続税の計算上、宅地の評価額を最大で80%減額することができます。 大幅に相続税が安くなる可能性もあるので、特例を受けることができないかどうか、この記事を参考に積極的に検討することをお勧めします。 この記事を書いた人 ……


相続人であるものの、遺産を取得したいと思わないというケースがあります。そのようなケースでは、相続分の放棄がなされることがあります。 似たものに相続放棄と相続分の譲渡があります。 この記事では、それぞれについて説明し、どのような場合にどれを利用すべきかについても説明します。 この記事を書いた人 ……
遺産分割協議を終えた後に「やっぱりやり直したい」「納得できない」と後悔することもあるでしょう。 遺産分割協議は、原則としてやり直しはできません。しかし、協議が無効だったりや相続人の同意が得られた場合など、やり直しが認められるケースもあります。この記事では、遺産分割協議のやり直しができるケース、できないケースについて紹介します。 また遺産分割協議をやり直す……
亡くなった人の残した財産が、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多い場合、相続すると損してしまうので、相続放棄をすることが考えられます。 相続放棄を希望する場合は、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が受理するかどうかを決定します。 場合によって受理されないこともあり、そうすると、亡くなった人の借金を相続人が弁済しなければならなくなってしまい……
遺産分割協議に期限はあるのでしょうか? 期限がないとすれば、目安としていつまでに済ませた方がよいのでしょうか?わかりやすく説明します。 この記事を書いた人 株式会社鎌倉新書 ……
遺産相続の手続きにはいくらぐらいの費用がかかるのでしょうか? 司法書士等の専門家に依頼する場合にかかる費用と、自分で手続きする場合にもかかる費用について、それぞれ説明します。 是非、参考にしてください。 遺産相続の手続き費用 「相続手続き」という言葉は法律用語ではないので、はっきりとした定義はありません。 この記事では、相続人が相続財産を自分のもの……
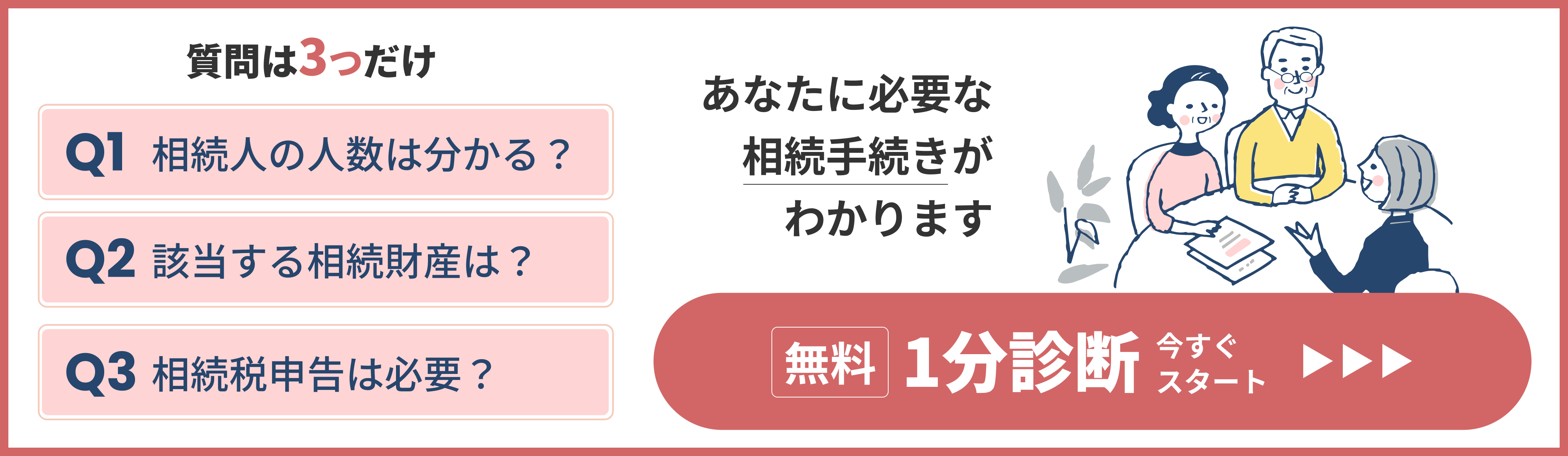
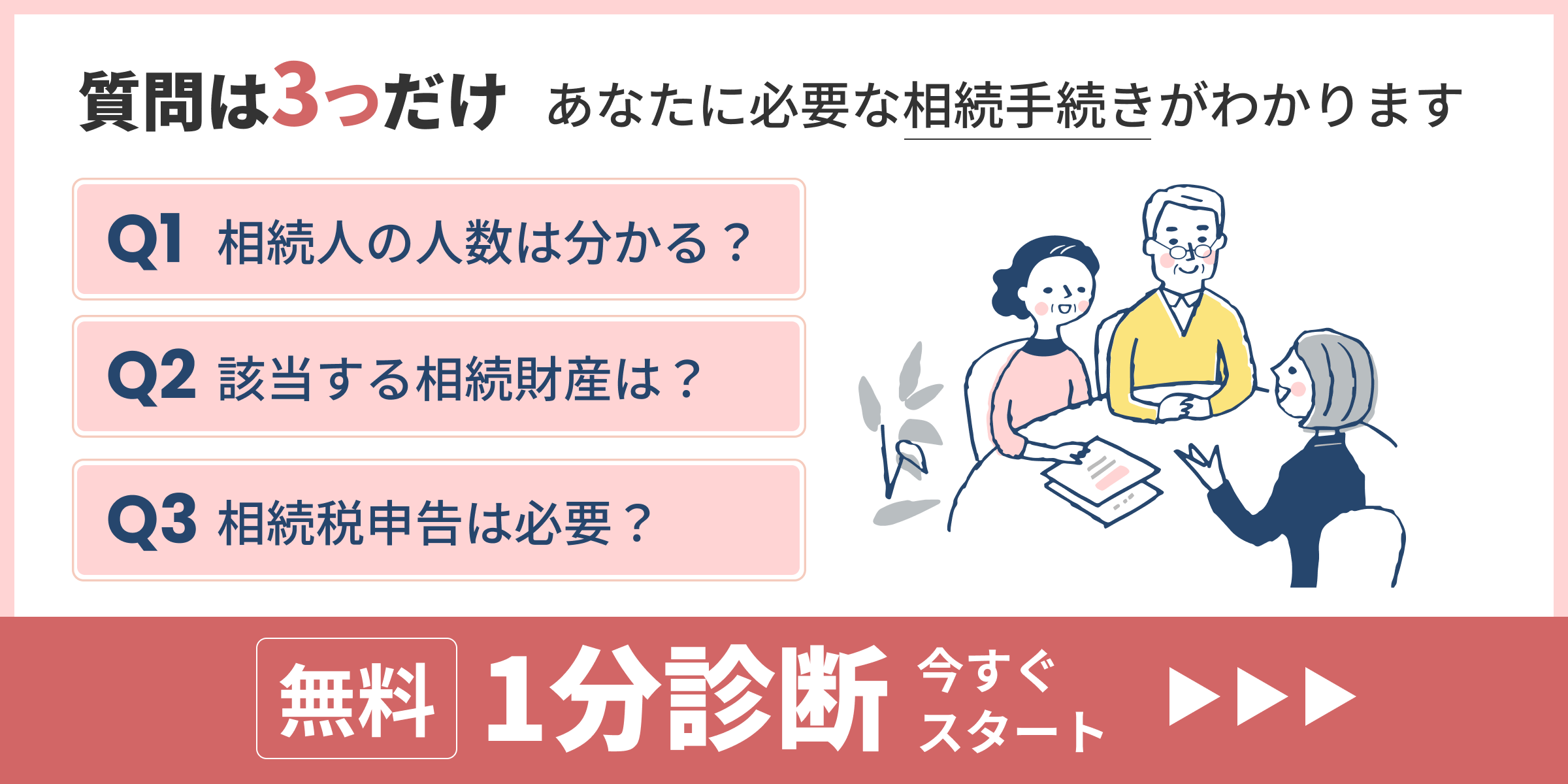
身近な人が死亡したときに、相続手続きでは、死亡した人の戸籍謄本が必要になるケースがとても多いのです。 役所に行って戸籍謄本を請求しようとすると、請求用紙には「戸籍全部事項証明書」と記載されているため「これでいいのかな・・・?」と一瞬迷う方もいるのでは? 戸籍謄本を戸籍全部事項証明書は同じものです。データで戸籍を管理するようになって以降は、戸籍全部事項証明……
相続税の税額を過大に納めてしまった場合は、更正の請求という手続によって、過大であった税額の還付を受けることができます。 この記事を書いた人 株式会社鎌倉新書 ……
家の所有者が死亡後、その家の相続人は、家の名義変更をしなければならないのでしょうか? 名義変更とはどのような手続きを言うのでしょうか。 その期限は決まっているのでしょうか? 名義変更の必要書類や費用についても併せてご紹介します。 是非、参考にしてください。 死亡後の家の名義変更は義務ではない期限もない 所有者が死亡し、相続……
家族が亡くなると、葬儀費用等のお金が必要になります。 家族が亡くなった悲しみの最中、お金の心配しなければならないのは辛いですよね。 この記事は、相続した遺産はいつもらえるか、お金が振り込まれるまでの期間について説明します。 さらに、お金が振り込まれるまでの流れや、相続手続きの完了前にお金が必要な場合の対処法について説明します。 是非、参考にしてくださ……
銀行預金の相続手続について、わかりやすくまとめました。 是非、参考にしてください。 この記事を書いた人 株式会社鎌倉新書 いい相続 ……
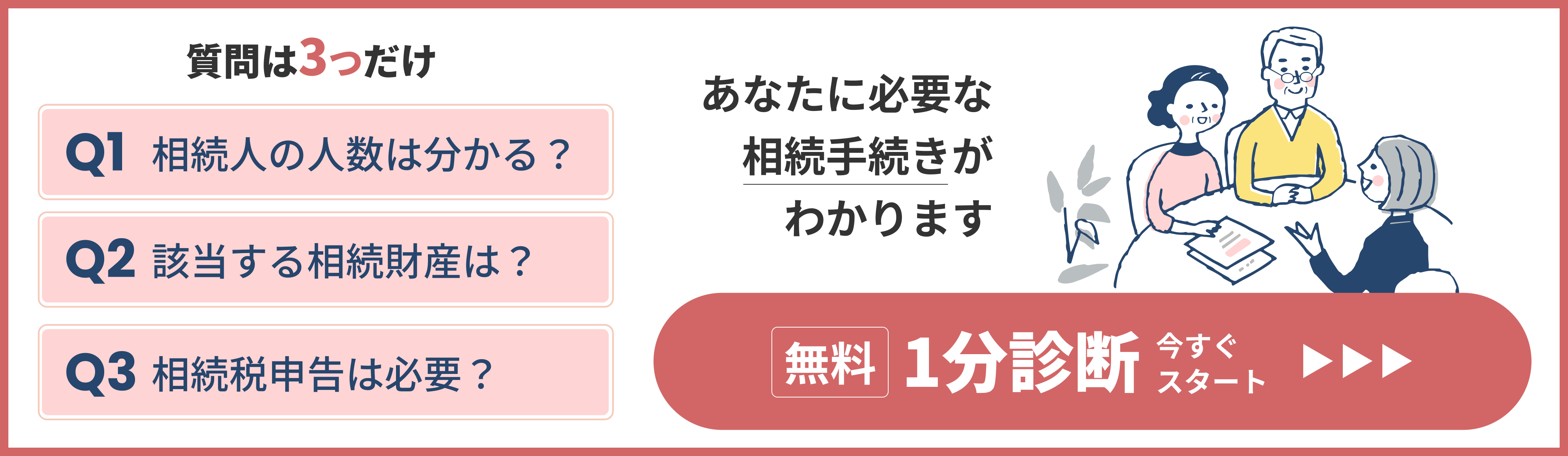
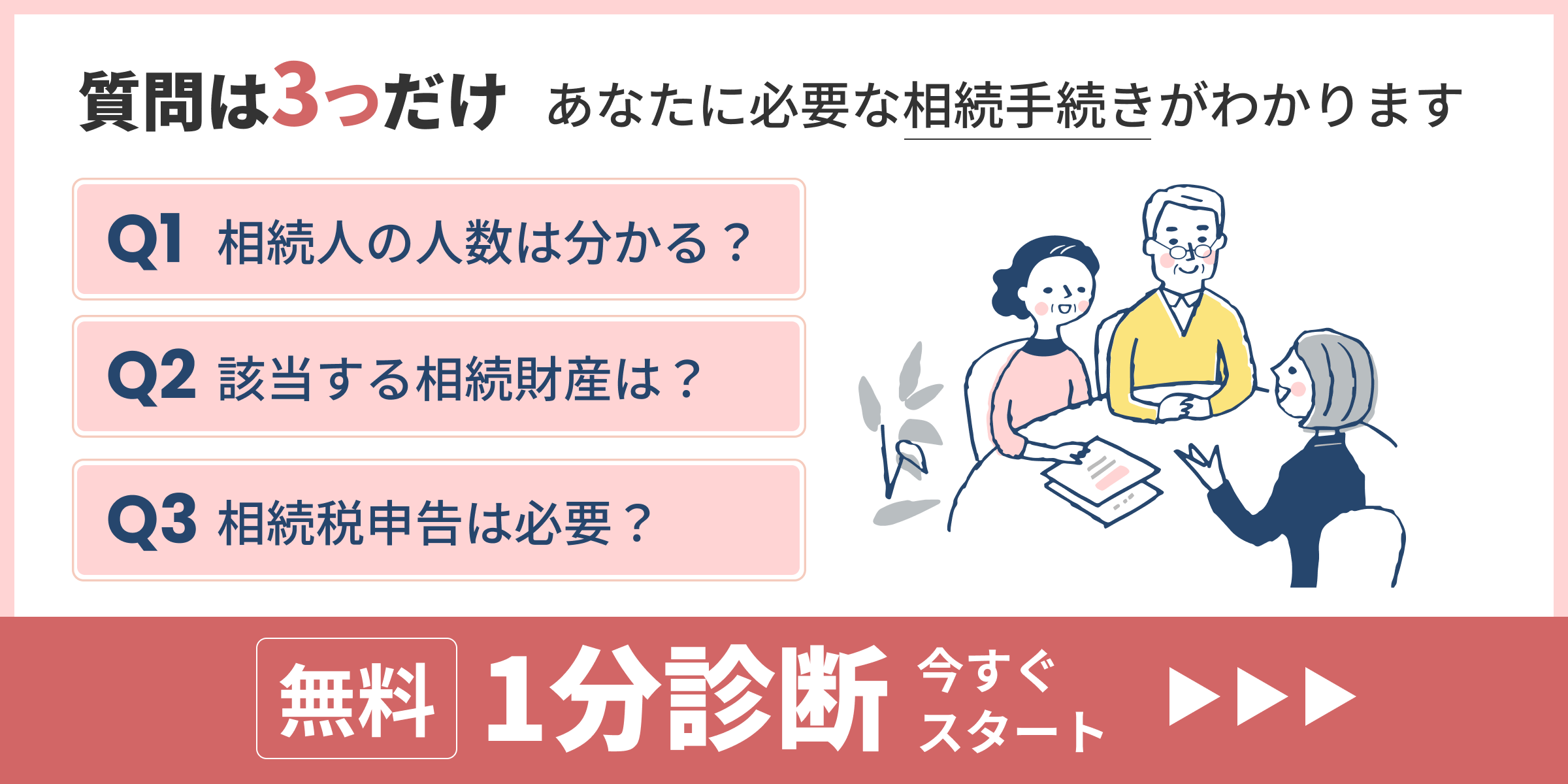

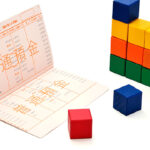








口コミ評価件数No.1に関する注意事項
相続関連ポータルサイトを対象とした口コミ評価件数の結果による(自社調べ/調査時期:2024年12月/調査対象サイト:いい相続、相続費用見積ガイド、相続会議、ベンナビ相続、相続プラス、そうぞくガイド、ミツモア、つぐなび、相続弁護士ドットコム、相続弁護士相談広場、相続弁護士相談Cafe、他/調査方法:調査対象サイトにアクセスし、士業個人及び士業事務所に対して相続に関する内容で掲載されている口コミ評価=レビュー点数のある口コミの件数を合算。※同一ユーザーの口コミが重複掲載されている場合は除外。※同一事業者が複数サイトを運営している場合は合算して事業者単位で集計)
Copyright(C) Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved. 無断転載・剽窃禁止
無料相談 相続のお悩みを解決 相続のお悩みを解決!まずはご相談ください
mail_outline Webで相談する keyboard_arrow_right