【相続登記の義務化が決定】所有者不明土地・空き家問題、相続登記の現状と登記しないことのデメリット【行政書士執筆】
不動産の相続登記を義務化するために政府は2020年の秋の臨時国会に法案を提出する予定です。相続登記が義務化された場合に相続手続きにどのような影響が出るのでしょうか。 この記事では現在検討されている情報をもとに相続登記の義務化について、相続登記の現状や相続登記が進まない理由、そして相続登記をおこなわないことのデメリットなどについて解説していきます。 相続登……
不動産の相続登記を義務化するために政府は2020年の秋の臨時国会に法案を提出する予定です。相続登記が義務化された場合に相続手続きにどのような影響が出るのでしょうか。 この記事では現在検討されている情報をもとに相続登記の義務化について、相続登記の現状や相続登記が進まない理由、そして相続登記をおこなわないことのデメリットなどについて解説していきます。 相続登……
不動産は遺産の中でも大きな割合を占めることが多いため、相続税対策での利用価値も高くなります。一方で、評価が難しかったり分割しにくいという側面もあります。 不動産の相続に詳しい人でなければ、有効な相続対策をとるのも難しいでしょう。まずは知識を身につけてから、専門家に相談することをおすすめします。 この記事では、不動産の相続税評価額の算出方法や申告方法、相続……
家や土地など、亡くなった方名義の不動産がある場合には名義変更(相続登記)をおこなう必要があります。ですが、相続登記は一生に何度も経験するものではなく、「いくらくらい費用がかかるのだろう?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 そこで、 家や土地の名義変更(相続登記)は何をするのか、どんな費用がかかるのか 相続登記にはどんな書類を準備するのか……
「孫は目に入れても痛くない」とは、昔からよく言われる言葉です。ご自身の子育てを終え、精神的にも経済的にも余裕のある中で見守るお孫さんの成長は思わず目を細めてしまいますよね。 少子高齢化が進んだことで、孫と祖父母との関係は、昔に比べより深いものになっているでしょうし、また、共働き世帯が増えていく中で、孫の面倒を見る機会も増え、子育てならぬ孫育てで忙しい方も。……
遺品整理とは、故人の遺した遺品を整理し、遺族で分配したり処分をしたりすることです。 遺品整理の進め方については、決められたルールや明確な期日があるわけではありません。 しかし、遺族にとっては葬儀の後、さまざまな手続きなどがあるだけでなく、大切な方を失った負担も大きくのしかかります。そのため、遺品整理がなかなか進まないといったケースも多数あるようです。 ……
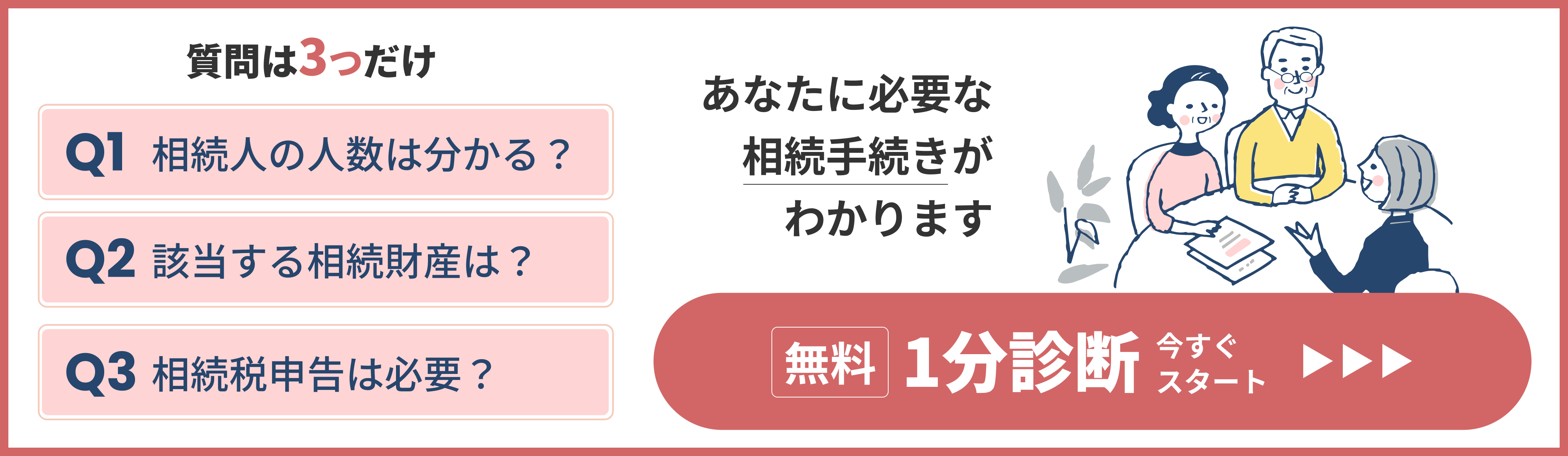
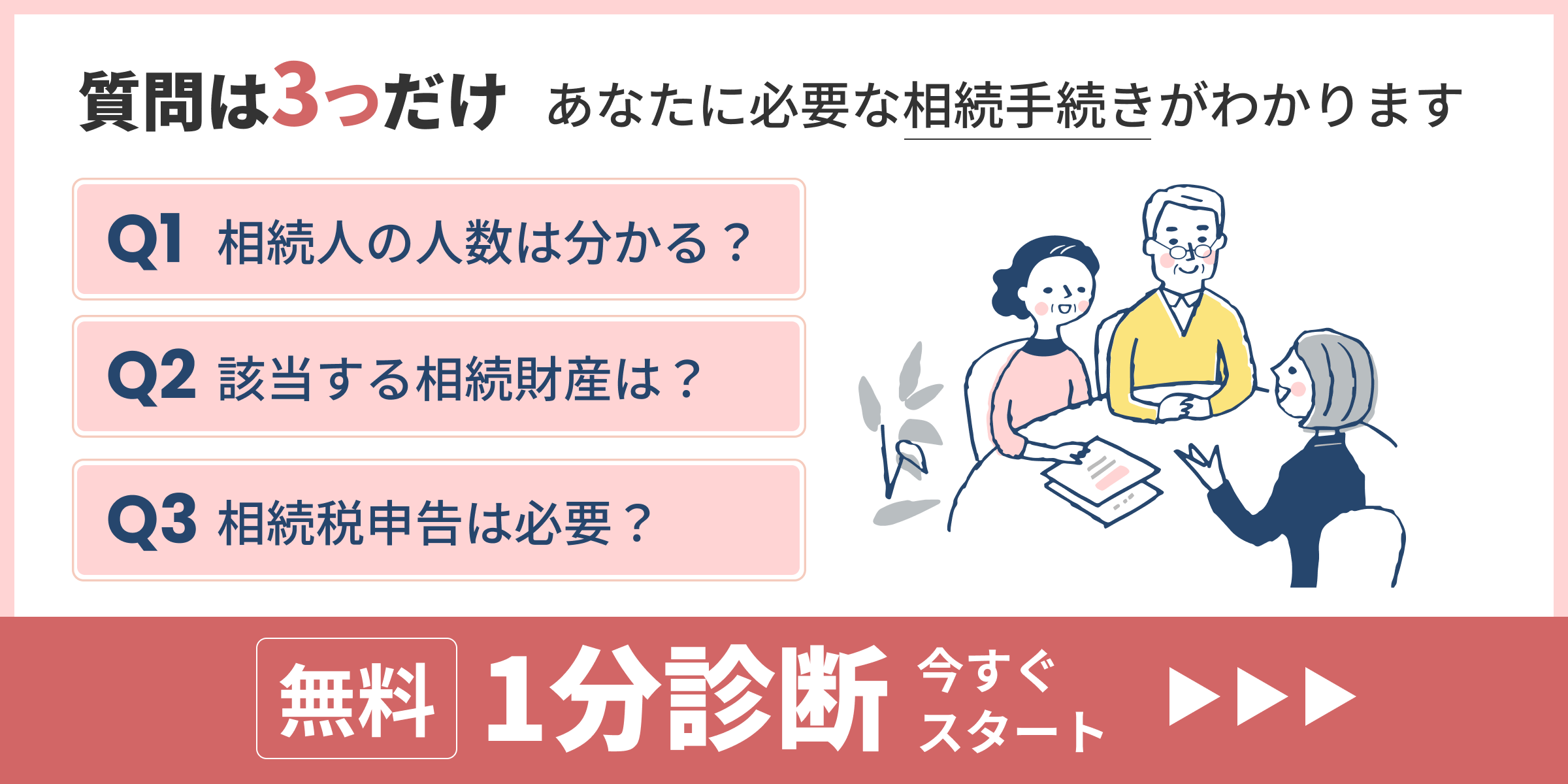
預金は最も身近な金融資産のひとつ。遺産相続の対象となる財産は様々ありますが、中でもほとんどの方がお持ちなのが銀行などの預金ではないでしょうか。 口座名義人が亡くなった場合、相続人は金融機関で、故人の預金口座に残された預金を払戻ししたり、相続人の口座に移すなど、相続の手続きをおこなう必要があります。 この記事では、預金を相続する手続きの流れや、相続の際に必……
相続において親族間にトラブルが起こることは珍しくありません。中でも兄弟姉妹については、親の死後、遺産相続のために関係が悪化したり、また兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者や子が相続人となる場合と比べて一部取り扱いが異なるものもあったり、兄弟姉妹だからこそ起こりやすいトラブルもあります。 この記事では、兄弟姉妹にかかわる相続について、法定相続順位と法定相続分の……
遺産相続には、状況によって遺産分割協議書の作成や相続税申告などのさまざまな準備や法的な手続きが必要になります。 そのすべてを自分自身の手で行うのは難しく、どうしても専門家に相談するケースも出てくるでしょう。税理士、司法書士、行政書士、弁護士、銀行などの各専門家の得意分野を把握しながら、時期や状況に応じて依頼をすることが非常に重要です。 この記事では、相続……
相続税の申告・納税期限は定められており、期限を過ぎると追徴課税など相続人にとってさまざまな不利益が起こりえます。手続きは煩雑なため、事前によく調べて対策や準備をおこなっておかなければなりません。 この記事では、相続税と申告・納税の期限をテーマに、相続税申告に必要な知識や、上手に活用することで相続税対策にも効果が期待できる特例などをご紹介。さらに、相続税の申……
相続税は、どのように場合にかかって、どのような場合にかからないのでしょうか? また、相続税がかからないようにする方法はあるのでしょうか?わかりやすく丁寧に説明します。是非、参考にしてください。 この記事を書いた人 ……


相続がいつ起こるかは誰も正確には予想できません。相続が発生したときにバタバタしないように、あらかじめ相続について学んでおくことはとても大切なことです。インターネットや本などで相続についていろいろ調べると「相続人」という言葉をよく目にします。相続人は、相続の基本用語の1つです。相続人の解釈を間違えてしまうと、相続に関連した制度の理解に誤解が生じてしまいます。 ……
亡くなられた方(被相続人)の財産(遺産)を引き継ぐ手続きを「遺産相続」と言います。 だれが遺産を受け継ぐのか、その配分はどのようになっているのか、どんな手続きがあるのか、事前に知っておいた方がいいことが多くあります。万一期限を過ぎた場合には大きな損失へつながるおそれも・・・。 相続が発生した際に速やかに行動するために、まずは遺産相続の大まかな流れや仕組み……
亡くなった人に借金がある場合等は、相続放棄をすることで借金を相続してしまうことを免れることができます。 その際、「相続放棄ができない場合はあるのか?」ということが気になることでしょう。 相続放棄ができずに多額の借金を背負うことは絶対に避けたいものです。 そこで、この記事では、相続放棄ができない場合をケースごとに理由を添えてわかりやすく説明します。 ……
相続の基本的なルールは民法で規定されています。この民法の相続に関連する部分の法律は「相続法」と呼ばれています。 2019年には「相続法」の約40年ぶりの法改正によって、自筆証書遺言の作り方が容易になりました。この記事では、自筆証書遺言の書き方や、2019年の法改正で変わったポイントについての説明、自筆証書遺言を作成する際によくあるトラブルとその対処法などに……
相続した財産の中に不動産が含まれているときには、不動産の名義変更(相続登記)をする必要があります。相続登記には以前は期限がなかったため、手続きをしないまま放置しているようなケースもありますが、デメリットが少なくありません。 この記事では、相続登記をしなかったときのデメリット、相続登記に必要な書類、相続登記の仕方に加え、相続した不動産を売却したいときの注意点……
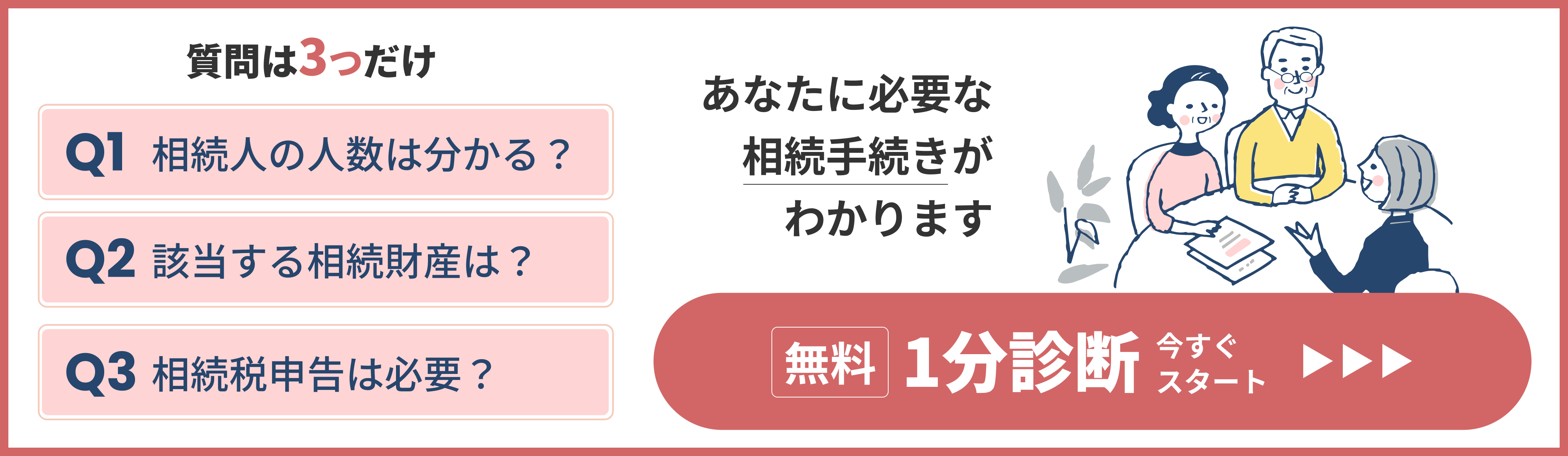
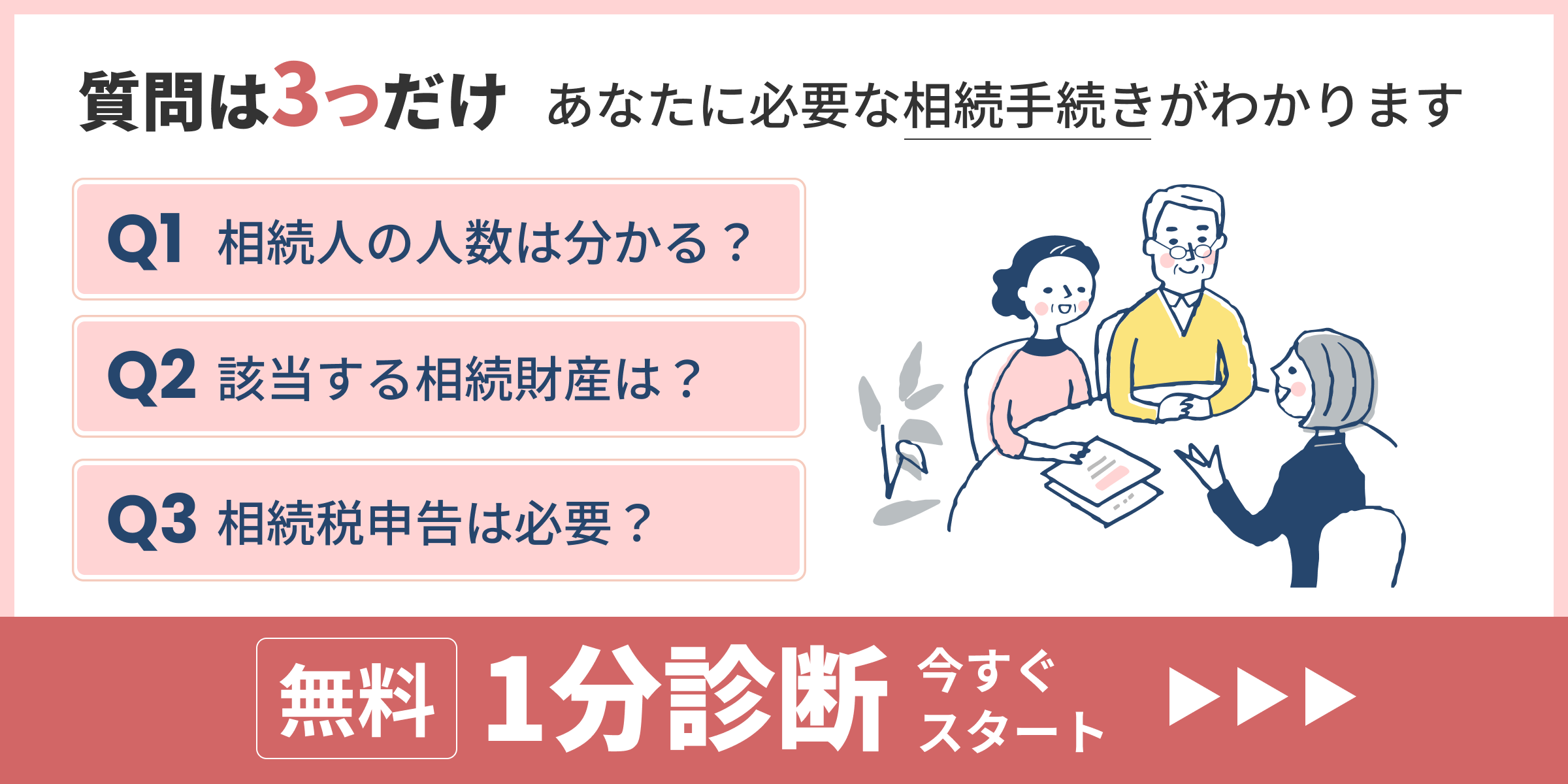
この記事はこんな方におすすめ:相続手続きを少しでも簡単にしたい方、戸籍謄本など取得する数量を減らしたい方 法務局や金融機関に提出すると、戸籍謄本などの原本を還付してもらえる 相続関係説明図で、戸籍関連の書類を取得する手間の軽減につながる 相続関係説明図は、相続人が多い場合や数次相続の際に便利 無料相談受付中!相続のお悩みの際は、ご希望……
相続が発生した際に気になる相続税。2015年に施行された相続税法の改正により、相続税が課税される割合は8%程度と、それ以前の倍近くに増えています。 この記事では以前よりも身近な問題となってきた相続税申告について、相続税申告までの流れ、相続税申告の期限、相続税申告書の書き方、相続税申告に必要な書類などをご説明します。 長文なので、お急ぎの方は目次から必要な……
相続税申告を税理士に依頼するに当たって、報酬額が気になることでしょう。 この記事では、報酬の相場や料金表の見方についてご説明します。税理士選びの参考になれば幸いです。 この記事を書いた人 ……
納付した相続税について更正の請求をする場合、いつまでにしなければならないのでしょうか? 税理士に依頼した方がよいのでしょうか?依頼する場合、報酬はいくらくらいかかるのでしょうか? 自分で請求する場合は、どのように手続すればよいのでしょうか?請求書や添付書類には、どのように記載すればよいのでしょうか? 以下では、このような相続税の更正の請求についてご説明……
人が亡くなるとその人の財産を相続人で分けます。これを遺産分割といいます。 遺産分割をするためには具体的には何をしたらいいのでしょうか。 この記事では、遺産分割の意味や、遺産分割をおこなうための事前準備や、流れ、遺産分割協議のやり方から注意点まで、わかりやすく順番に解説していきます。是非参考にしてください。 遺産分割とは 遺産分割とは被相続人が残し……
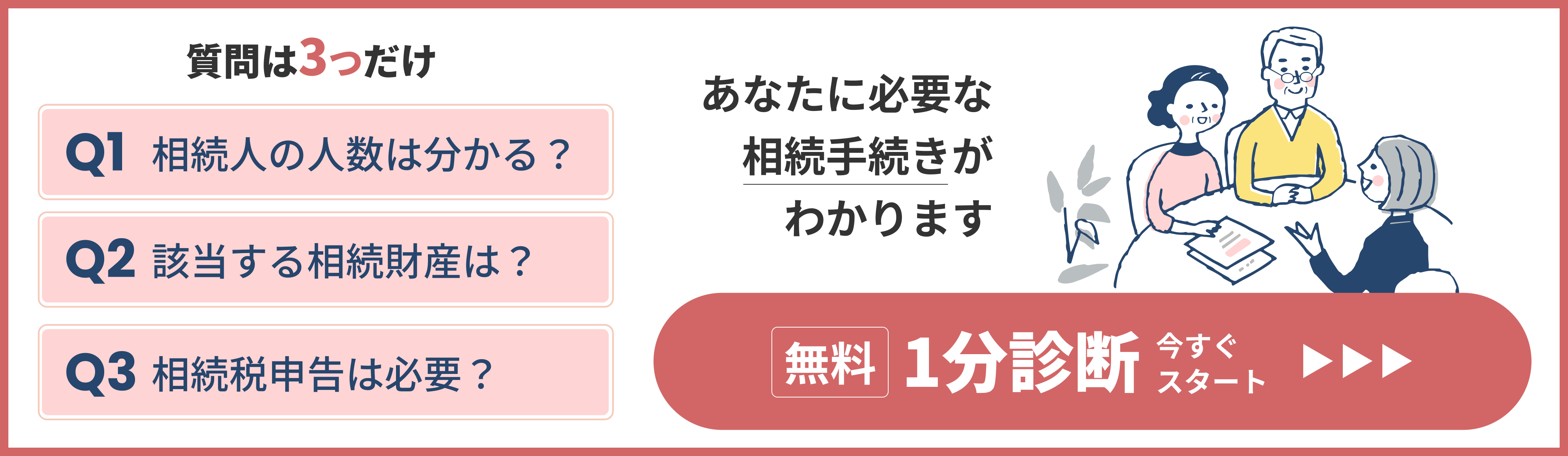
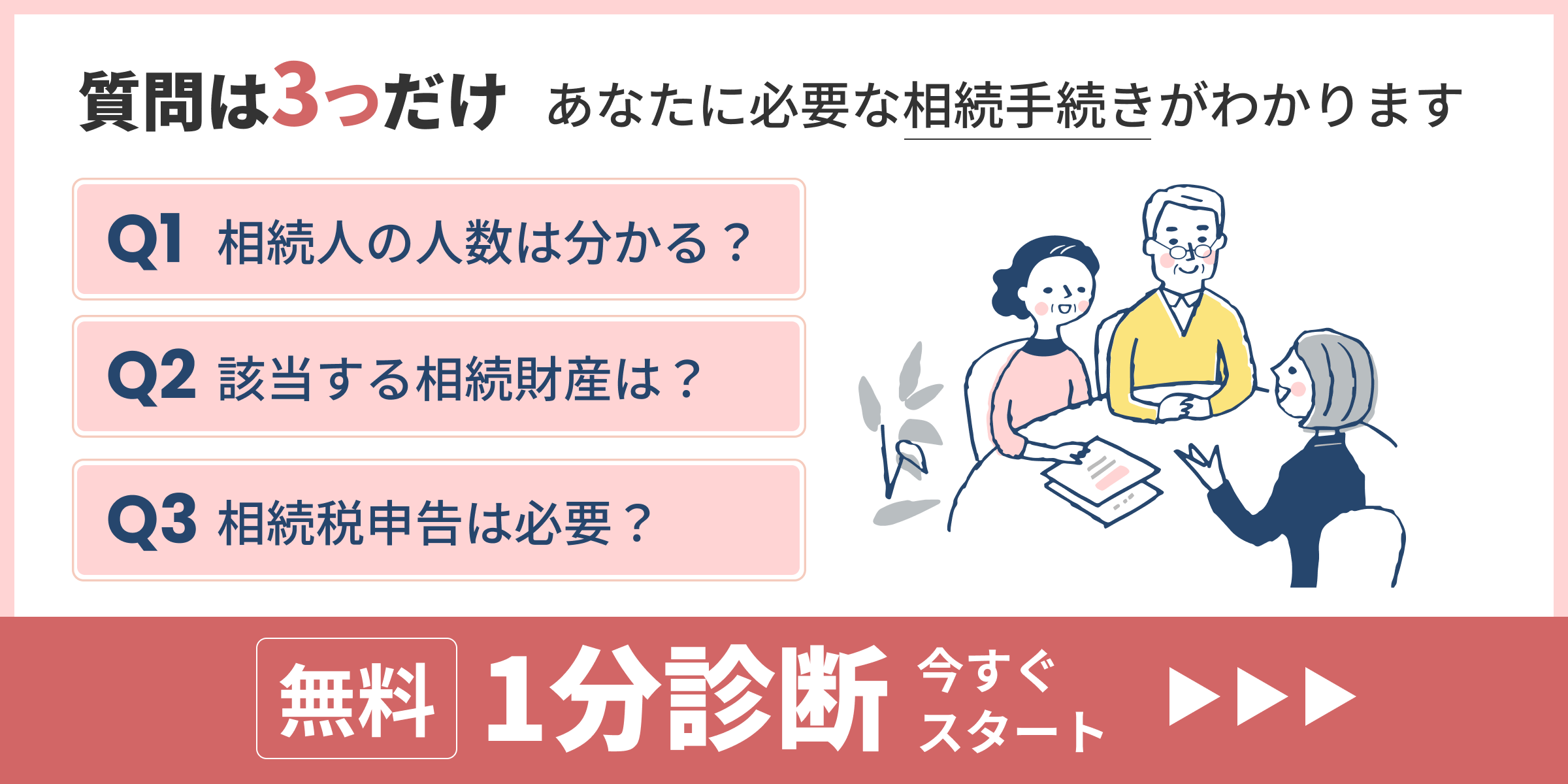

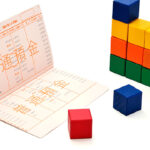








口コミ評価件数No.1に関する注意事項
相続関連ポータルサイトを対象とした口コミ評価件数の結果による(自社調べ/調査時期:2024年12月/調査対象サイト:いい相続、相続費用見積ガイド、相続会議、ベンナビ相続、相続プラス、そうぞくガイド、ミツモア、つぐなび、相続弁護士ドットコム、相続弁護士相談広場、相続弁護士相談Cafe、他/調査方法:調査対象サイトにアクセスし、士業個人及び士業事務所に対して相続に関する内容で掲載されている口コミ評価=レビュー点数のある口コミの件数を合算。※同一ユーザーの口コミが重複掲載されている場合は除外。※同一事業者が複数サイトを運営している場合は合算して事業者単位で集計)
Copyright(C) Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved. 無断転載・剽窃禁止
無料相談 相続のお悩みを解決 相続のお悩みを解決!まずはご相談ください
mail_outline Webで相談する keyboard_arrow_right