土地や株式、預貯金など相続税評価額を自分で計算する方法をわかりやすく解説【税理士監修】
相続税申告が必要か判断したり相続税の額を計算するには、相続財産1つ1つの評価額を算出し、足し合わせる必要があります。 税理士に相続税の申告を依頼する場合でも、まずは大体の金額だけでも知っておきたいのではないでしょうか。土地家屋や預貯金、株式など、相続するケースの多い財産の評価の出し方を確認しておきましょう。 この記事では、路線価図や評価倍率表を用いた土地……
相続税申告が必要か判断したり相続税の額を計算するには、相続財産1つ1つの評価額を算出し、足し合わせる必要があります。 税理士に相続税の申告を依頼する場合でも、まずは大体の金額だけでも知っておきたいのではないでしょうか。土地家屋や預貯金、株式など、相続するケースの多い財産の評価の出し方を確認しておきましょう。 この記事では、路線価図や評価倍率表を用いた土地……
先月母が亡くなり遺産分割をしようと思っています。相続人は高齢の父と長男の私と弟です。遺産は母名義の土地と、預貯金などです。法定相続分どおり分けようと思っていますが、何か注意点はありますか。 親が高齢で、まとまった資産がある場合、誰が何を譲り受けるかということと相続税はセットで考え、加えて、残されたもう一方の親の二次相続も視野に入れた遺産分割を検討すると……
質問者:H.A このケースでは、たとえ墓が存在するとしても庭の所有者は実家である土地建物を相続した弟さんということになります。 祭祀承継者って何? 民法897条では「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」としています。宗教的な物については、民法では他の相続財産と切り離し……
質問者:T.H マンションは一戸建てと比較して、土地部分を他の部屋の所有者と共有で持っているため、評価が安くなることが多いといえます。 マンションの権利関係と評価 マンションは、一戸建てとは権利関係の構造が若干異なります。 一戸建てでは建物と土地は別々の登記簿として構成されており、それぞれ別々の権利の動きをすることもあります。(たとえば土地所有……
質問者:S.M 相続税とは、申告期限内に全額を「金銭で」納付することが原則です。しかし現実的にはほとんど現金や預貯金の相続財産がなく、不動産など現金化しづらい財産ばかりのこともあります。そのような場合はどうすればよいのでしょうか。 相続税の延納 相続税は基本的に「被相続人が亡くなった翌日から10カ月以内」に現金で全額を納付しなければならないので……
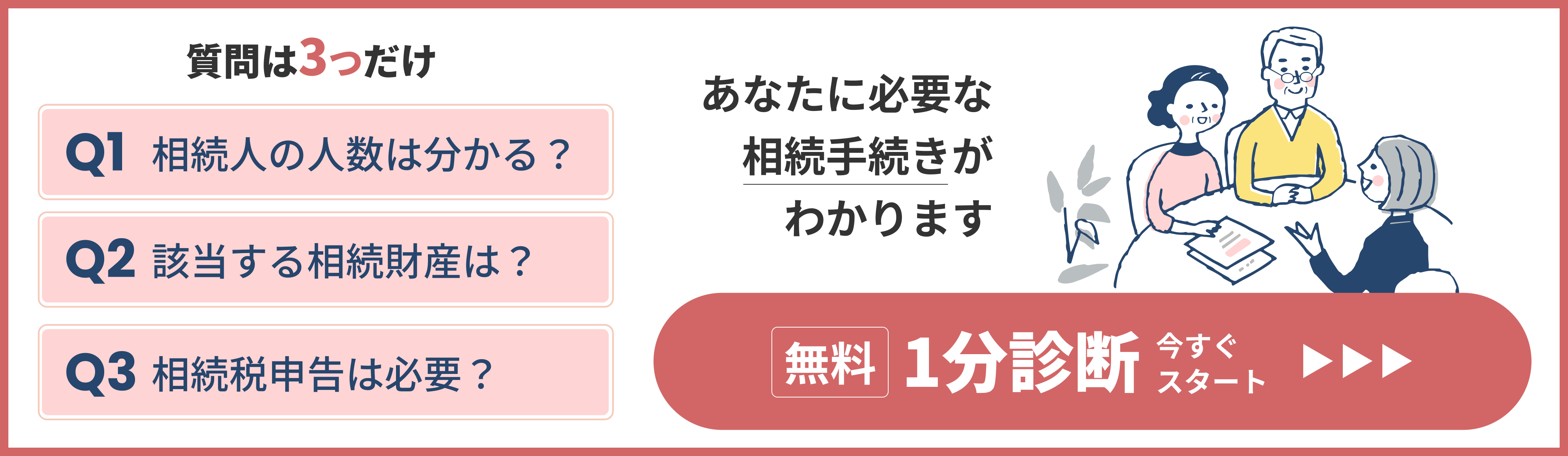
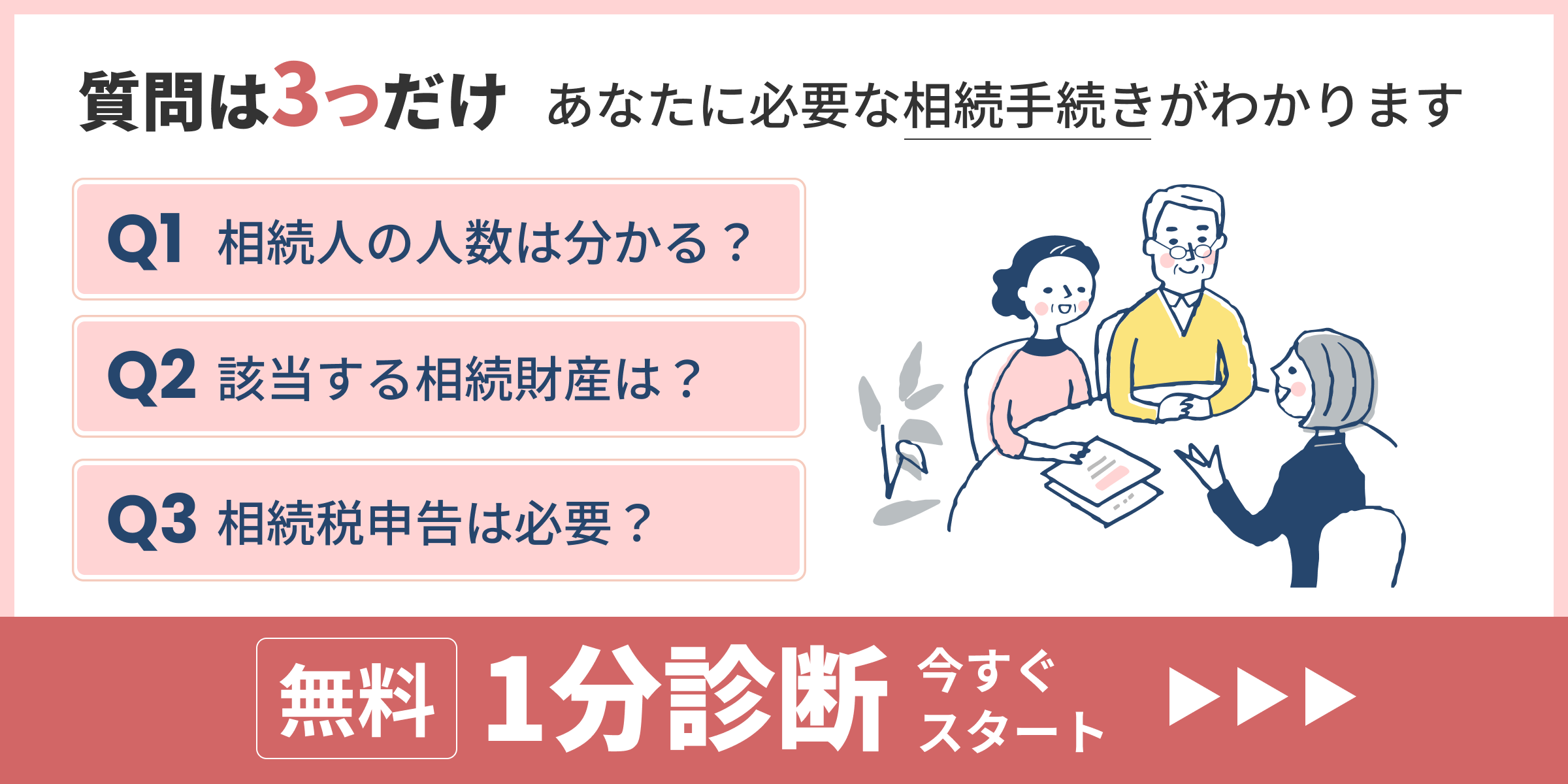
質問者:T.I 被相続人はマンション購入時に「団体信用生命保険」に加入していたケースと思われますので、この場合は保険でローン残額が返済される形となり、マンションが奥様に相続されてマンション自体が相続財産となります。 民間の銀行では団体信用生命保険加入が必須 団体信用生命保険とは、住宅ローンの債務者が死亡または高度障害に陥った際に保険……
質問者:M.S 個人名義で賃貸物件を所有している人は、その事業を法人化することによって所得税や相続税の節税につながることがあります。その手順を確認してみましょう。 まず、法人を設立する 法人の設立は、旧商法のもとでは資本金1,000万円を確保しなくてはなりませんでしたが、現在は最低資本金制度そのものがなくなっているため、100万円……
質問者:K.N 相続した土地に法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)が誰も住む予定がないため、売却して金銭で分けるというのは近年、よくあることです。 不動産を譲渡して利益が出れば「譲渡所得税」がかかりますが、そこから控除できる費用にはどのようなものがあるのでしょうか。 相続登記を経なければ売却はできない 親などから相続した土地をどうするのか……
質問者:J.W 相続における不動産の価格は、何を目的とするかで計算方法が異なりますが、相続税の計算に使われるのは「路線価」と「固定資産税評価額」になります。 いわゆる市場価格(売却した際の代金)が使われるわけではありません。 土地の相続税を計算するための基準 土地の相続税を計算する際は、その土地がどのような地域にあるのかによって価格を算出する方……
質問者:I.C 自筆証書遺言は法的要件が多く、それが1つでも欠けると無効になってしまうため注意しなくてはなりません。 自筆証書遺言の要件 自筆証書遺言とは、自宅などで遺言者が自分の準備した筆記用具で作成する遺言書です。公正証書遺言のように費用がかからず、一見、とても手軽に見えますがそこには大きな落とし穴があります。 自筆証書遺言を確実に有効な遺……
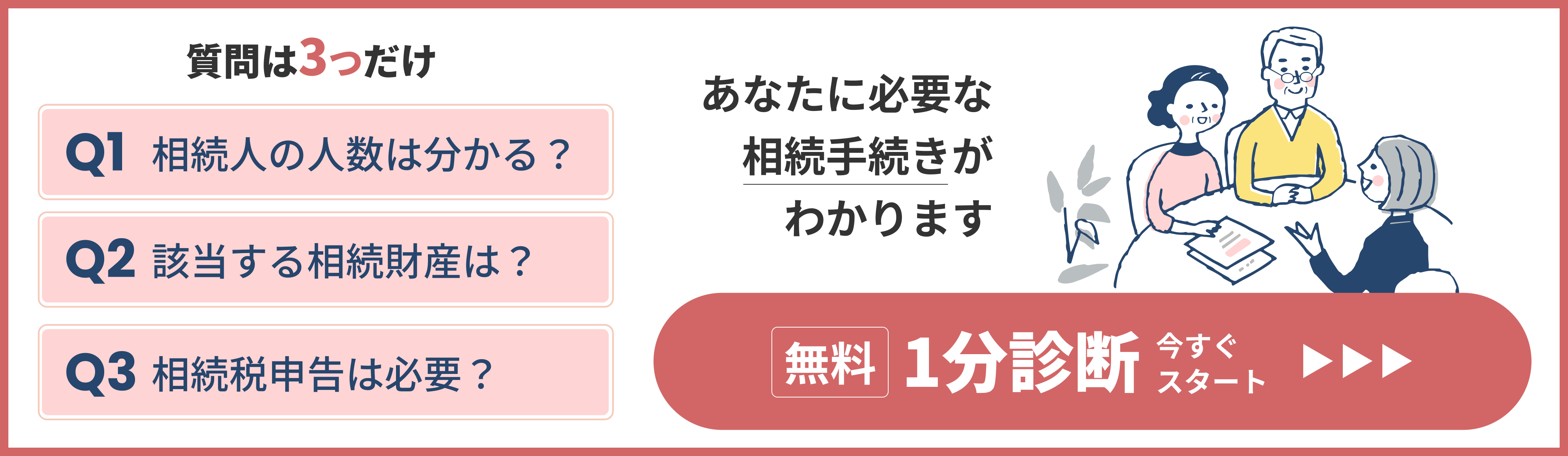
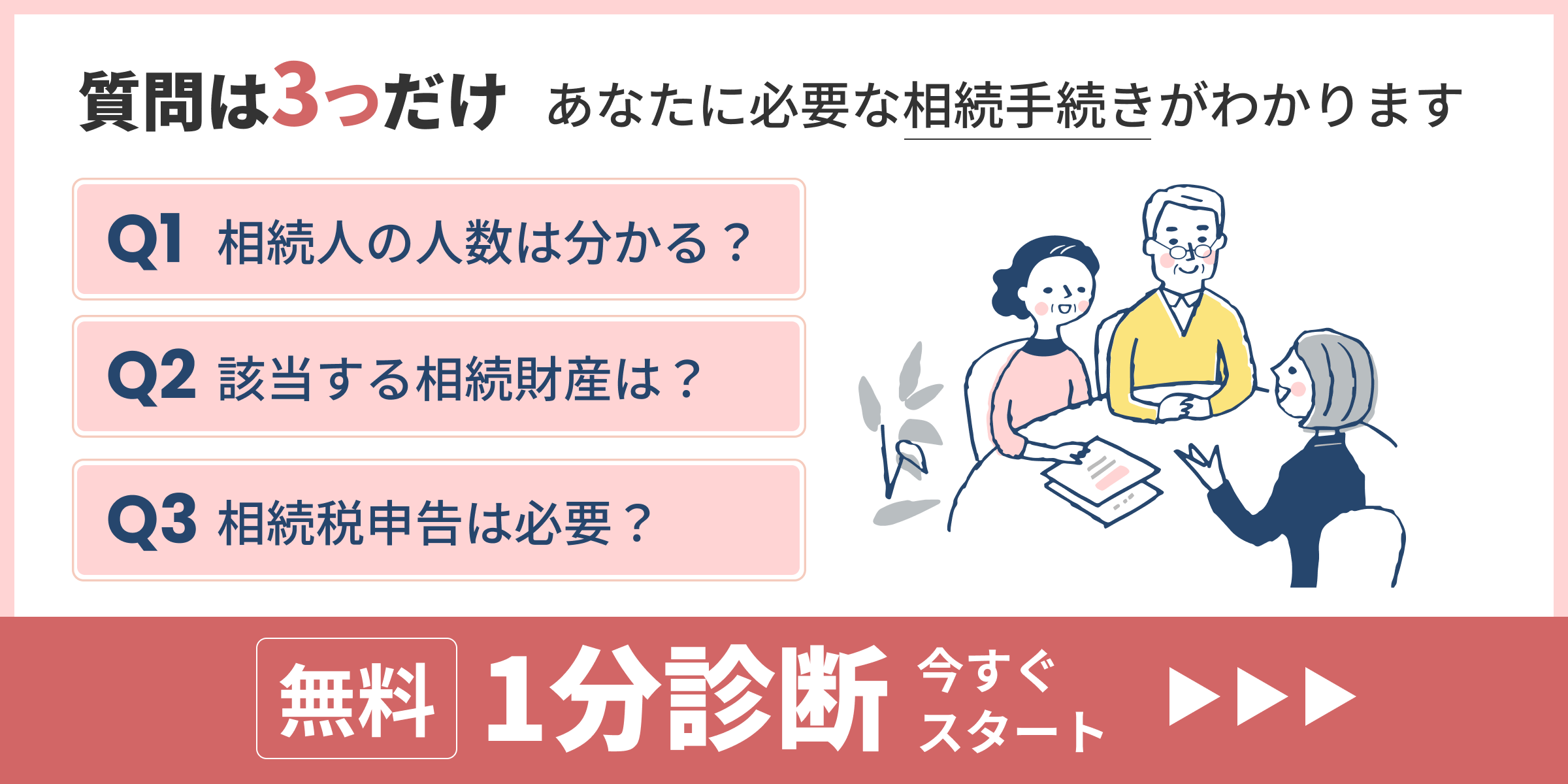
質問者:Y.O 相続税においては、大幅に税額を減らすことのできる特例があります。そのうちの一つが「小規模宅地等の評価減の特例」という制度です。 小規模宅地等の評価減の特例とはどんなもの? 小規模宅地等の評価減の特例とは、「被相続人(亡くなった人)の自宅や被相続人が事業のために使用していた宅地」は、もし相続税のためにこれを売ることになれば相続税の……
昨年母が亡くなり、預金と母が住んでいたマンションを相続して、相続税を払いました。そのマンションを売ったら、また違う税金がかかると聞き、なんだか二重に払わされる気がしてしまいます。 相続により取得したマンションを売却して利益が出た場合も、相続税の納税有無に関わらず、譲渡所得金額に対して所得税(+復興特別所得税※)・住民税がかかります。ただ……
昨年母が亡くなり、私は母が住んでいたマンションだけを相続し、相続税を100万円くらい払いました。 そのマンションを売った場合、売ったことで手に入るお金に税金はどのくらいかかるのでしょうか? マンションは5年ほど前に母が購入したもので、いくらだったのかは聞いていません。 相続により取得したマンションを売却した場合、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引……
質問者:T.N 相続した家が空き家となりそのまま放置されることを防ぐ対策として「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が設けられています。 空き家問題は深刻になっている 少子化、そして都会へのさらなる人口集中も進んでいます。 そのような中で、誰も住む人がおらず放置される「空き家」の問題は年々深刻化し、全国で……
印鑑証明書とは、その印鑑が、届け出られている印鑑であることを証明するものですが、法人の場合は登記所が、個人の場合は市区町村長が証明します。 個人が届け出た印鑑は一般には実印(じついん)とも呼ばれ、相続だけでなく、日常生活でも家の購入のような重要な契約などで使用します。 この記事では、主に個人が使用する印鑑の印鑑証明書について、印鑑証明書が必要な相続の手続……
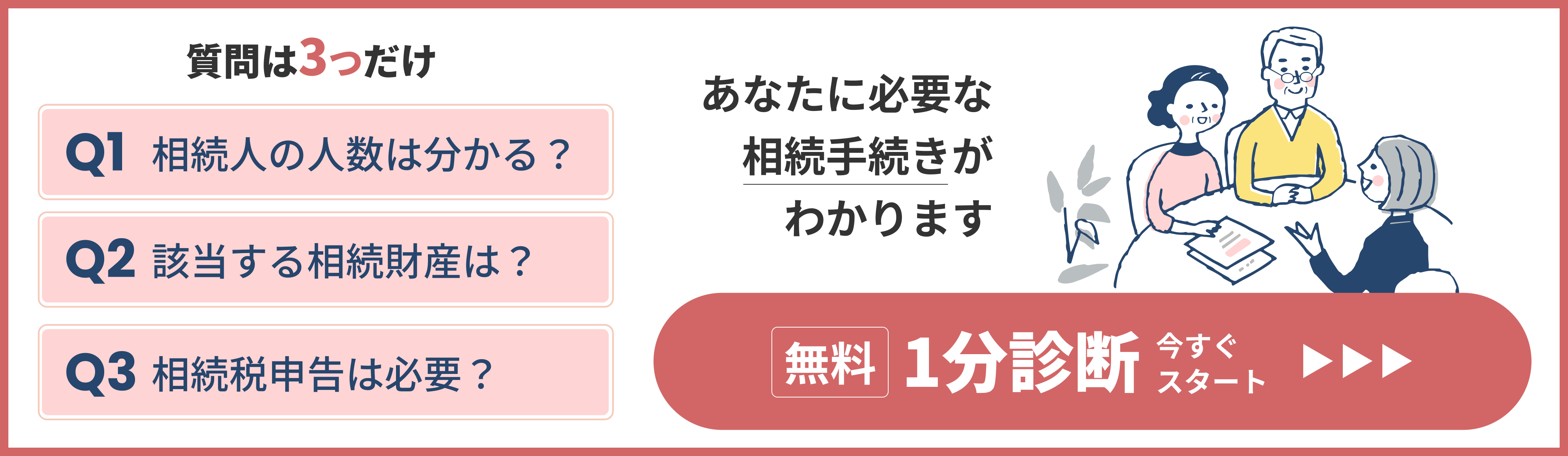
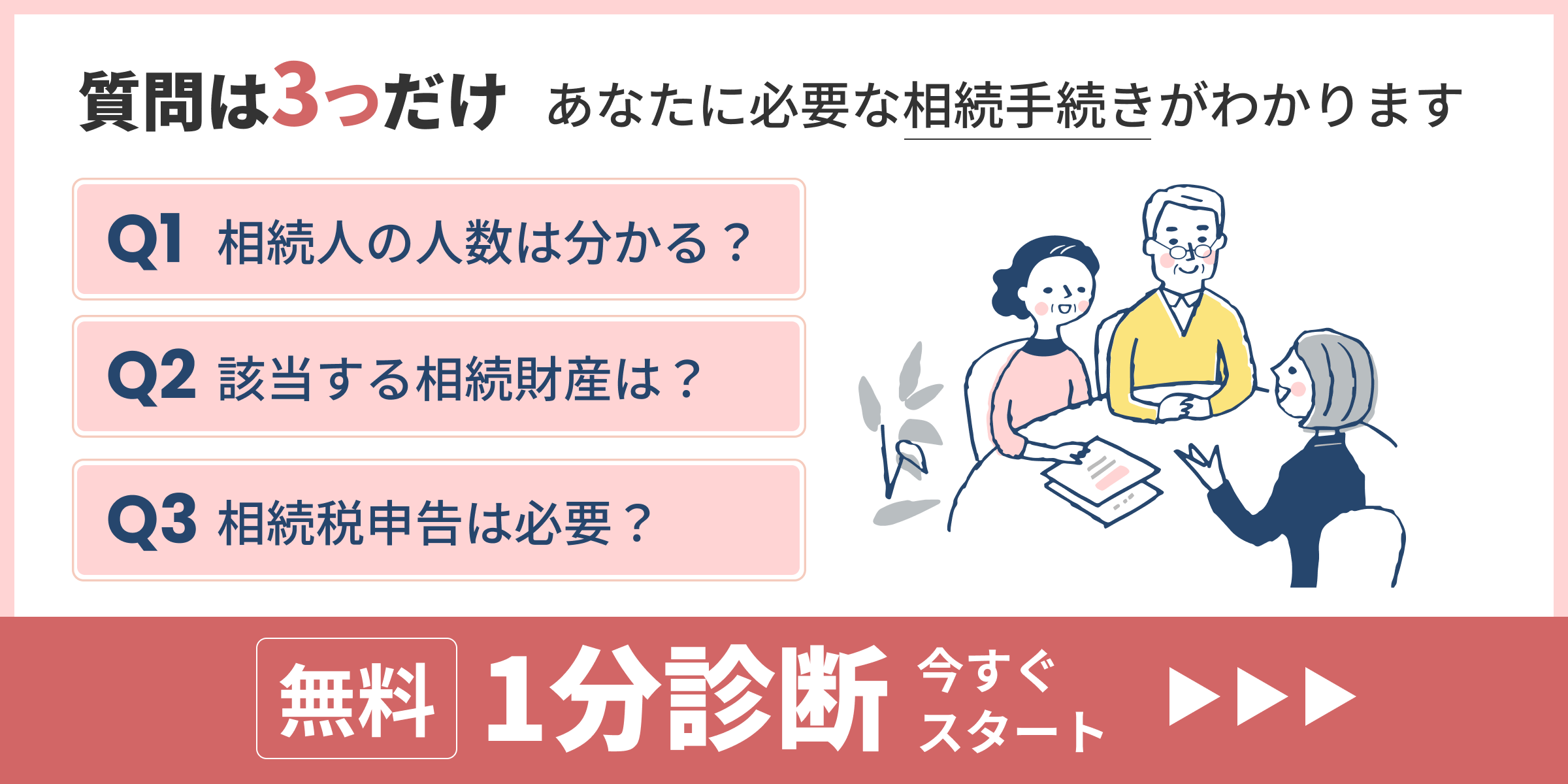
賃貸アパートを相続するうえで以下のような疑問が生じる方は多いでしょう。 「賃貸アパートの相続手続きはどんなことをするの?」 「賃貸アパートはどのように遺産分割すればよいの?」 「賃貸アパートを相続するときにどんなことに注意すればいい?」 この記事ではこのような疑問も踏まえ、相続手続きの流れに沿って説明をしていきます。 賃貸アパートを相続したときの流……
遺産相続において、相続開始の時点で相続人がいない、またはいるかどうかがわからない状態を「相続人不存在」といいます。 相続人不存在となるのは、被相続人の遺産を相続する相続人がいない場合や、また相続人はいるものの、被相続人のマイナスの財産が多く、全員が相続放棄をした場合などが考えられます。 いずれの場合も、「相続人不存在」になると、残された財産は「国庫に帰属……
被相続人の財産に土地・家屋があると、その価値を正確に知ることは難しいため、財産の全容がわかりにくくなります。また、相続放棄をした後も管理を続けなければなりません。そのため、そのほかの財産と異なり、相続したくないからといって、必ずしも相続放棄が最良の選択ではないケースもあります。 この記事では、土地・家屋を財産としてどのように評価すべきか、相続したくないとき……
相続手続きを進めるうちに、実は建物が未登記だったと判明することがあります。 この記事では未登記建物が相続に含まれる場合に、どのような相続手続きをとればいいのか、また未登記のままにしておくとどのような問題点があるのかを解説します。 この記事はこんな方におすすめ: 「未登記建物を相続した人」「相続財産に未登記建物が含まれている人」 この記事のポイ……
親が住んでいた分譲マンションを相続した場合、住む以外に、マンションを貸して家賃収入を得る、思い切って売却する、という選択肢もあります。 どうやって判断したらいいのでしょうか。 この記事では、マンションの相続に際してやるべきことや、マンション相続後の3つの選択肢とそれぞれのメリット・デメリットなどのポイントを詳しく解説します。 この記事はこんな方にお……
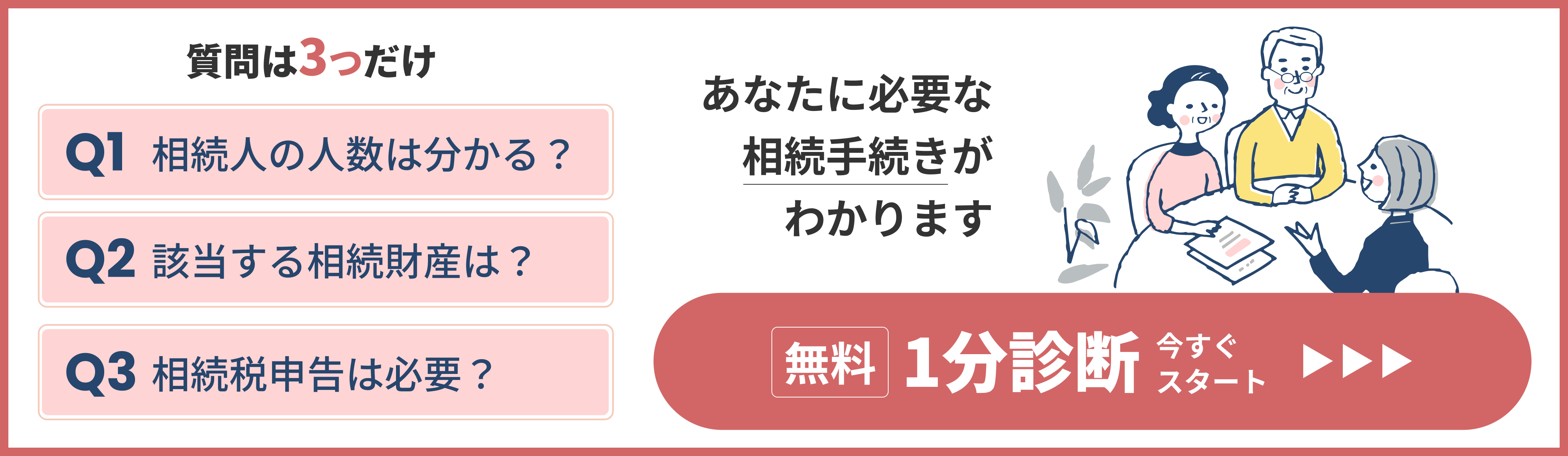
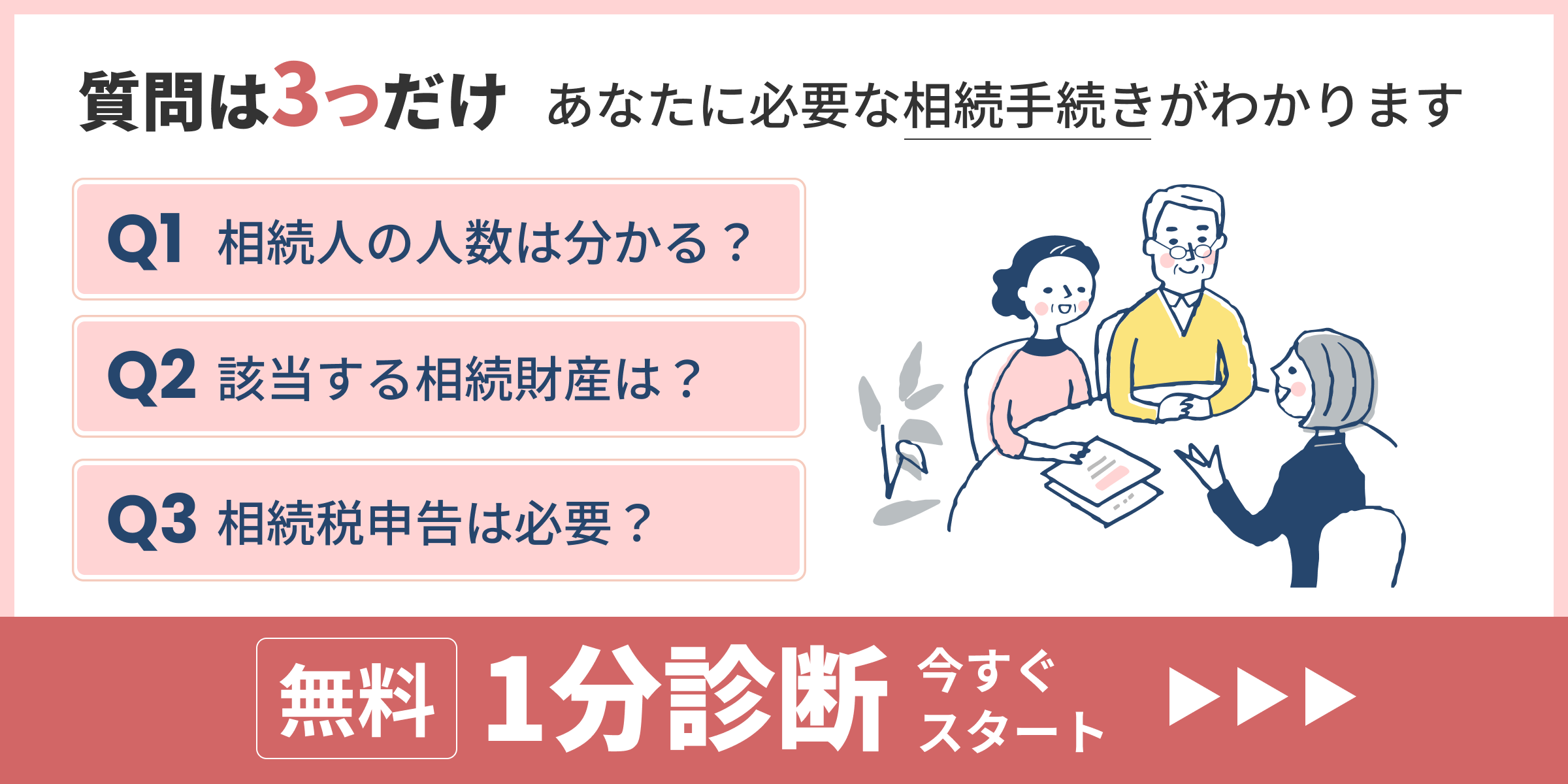

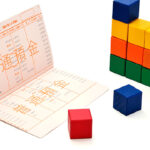








口コミ評価件数No.1に関する注意事項
相続関連ポータルサイトを対象とした口コミ評価件数の結果による(自社調べ/調査時期:2024年12月/調査対象サイト:いい相続、相続費用見積ガイド、相続会議、ベンナビ相続、相続プラス、そうぞくガイド、ミツモア、つぐなび、相続弁護士ドットコム、相続弁護士相談広場、相続弁護士相談Cafe、他/調査方法:調査対象サイトにアクセスし、士業個人及び士業事務所に対して相続に関する内容で掲載されている口コミ評価=レビュー点数のある口コミの件数を合算。※同一ユーザーの口コミが重複掲載されている場合は除外。※同一事業者が複数サイトを運営している場合は合算して事業者単位で集計)
Copyright(C) Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved. 無断転載・剽窃禁止
無料相談 相続のお悩みを解決 相続のお悩みを解決!まずはご相談ください
mail_outline Webで相談する keyboard_arrow_right