父が毎年、私の誕生日に110万円をくれます。税金はかかる?かからない?
父は私の誕生日に、毎年110万円贈与として通帳にお金を振り込んでくれます。この金額なら贈与税はかからないですよね? 毎年1月1日~12月31日までの贈与が110万円までは、暦年贈与の基礎控除であるので贈与税はかかりません。 暦年贈与とは 暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日(こよみ)の1年間に受贈者(もらった人)一人につき110万円を超……
父は私の誕生日に、毎年110万円贈与として通帳にお金を振り込んでくれます。この金額なら贈与税はかからないですよね? 毎年1月1日~12月31日までの贈与が110万円までは、暦年贈与の基礎控除であるので贈与税はかかりません。 暦年贈与とは 暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日(こよみ)の1年間に受贈者(もらった人)一人につき110万円を超……
質問者:T.N 住宅取得資金を子供などに援助したい人はぜひ検討したいのが「住宅取得等資金の贈与の特例」です。 住宅取得等資金の贈与の特例のポイント この非課税制度は、「子供や孫が自宅の新築や購入、増改築、あるいはその敷地を取得する際に対価に充てる資金として親や祖父母から贈与されたものを一定の金額まで非課税にする」というものです。 ・住宅取……
質問者:T.M 相談者のご主人が行っていた振り込みは、生活費として必要な金額以上の部分は贈与とみなされます。年間110万円を超えるようであれば贈与税が課税されますので、奥様が当然に自分自身の財産として扱うことはできません。 親族等の口座に自分のお金を振り込むことは贈与? 夫が妻名義の口座にお金を振り込んで妻がやりくりするというスタイルは比較的よ……
質問者:Y.O 基本的に、順当にいけば夫の方が先に亡くなるようなケースでは生前贈与で妻に財産を移しておくことは相続税の節税になりますが、妻自身が保有する財産とのバランスなども考えなければなりません。 夫婦間贈与の定番である「おしどり贈与」 相談者の場合は奥様がまだかなり若いため、結婚からそれほど経過していないことも考えられますが、もし婚姻期間2……
質問者:K.H 通常であれば離婚に際しての財産分与に贈与税はかかりませんが、通常の財産分与の範囲を超えている程度であれば贈与税の対象となります。 財産分与の性質 離婚に際しての財産分与というのは、基本的には贈与にはあたりません。よって、基本的には贈与税の心配をする必要はないのですが、財産分与の程度を超えてしまった場合には気をつけなければなりませ……
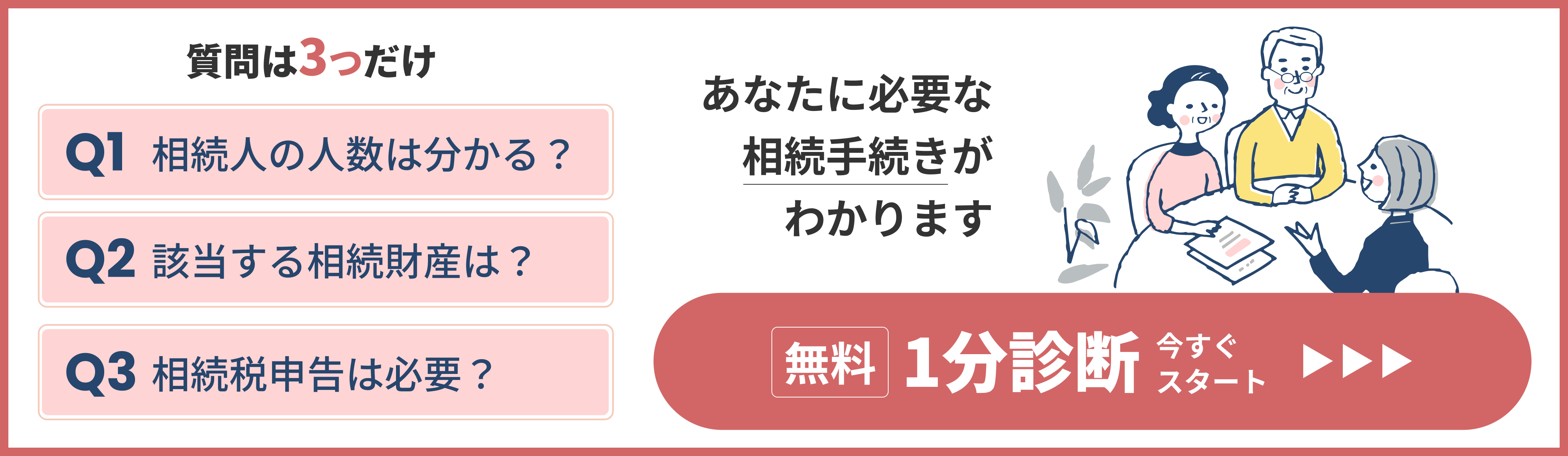
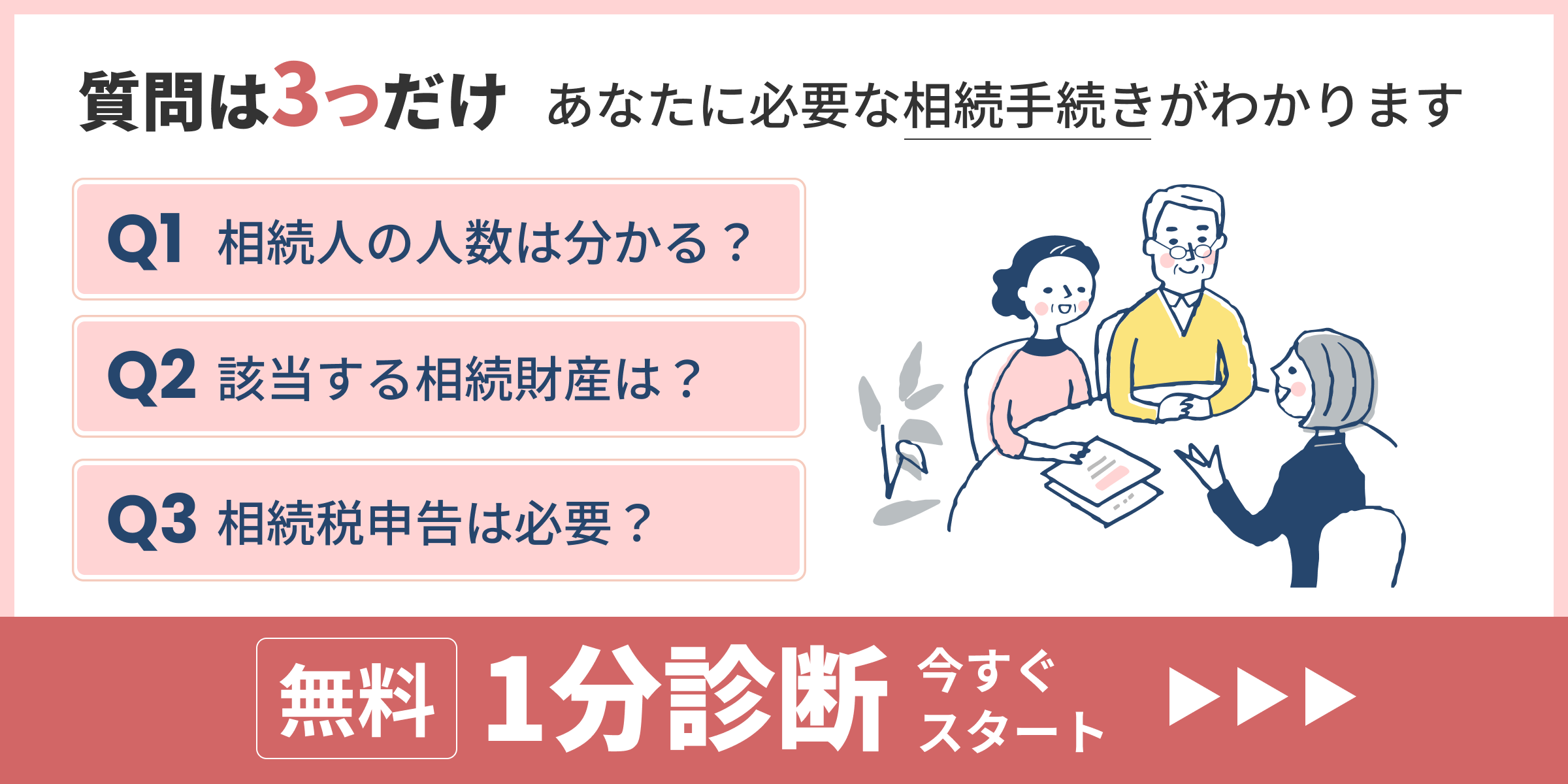
質問者:H.I 贈与税は、たしかに相続税に比べれば計算方法が複雑ということもなく一見楽に見えるのですが、申告に至るまでの各種判断の過程等を考えるとやはり税理士に依頼しておいた方が望ましいといえます。 贈与税は国税最高レベルの税率 贈与とは、ある人がその年の1月1日から12月31日までにもらった金銭その他財産価値があるものが基礎控除額(110万円……
年間110万円までなら非課税で贈与できると聞きましたが、現金はともかく不動産などは毎年それをやっていたらキリがありません。うまい方法ありませんか? 質問者様のようなケースでは、状況によっては「相続時精算課税」を利用すると節税効果が上がることがあります。 暦年課税(暦年贈与)と相続時精算課税 基本的に、贈与を受ける人1人あたり年間110万円までは……
質問者:J.T 祖父母が孫の教育費を贈与する場合については、「教育資金の一括贈与に係る非課税制度」というものがありますが、それを使わなくても非課税にすることができます。 基本的に、教育資金には贈与税がかかる? 贈与税というのは、もらう人1人あたりが年間110万円を超える贈与を受けると申告、納税の義務が発生するものです。 ただ、扶養義務者が子供に……
子供への贈与を考えていますが、贈与税というのはどれくらいかかるものでしょうか?計算方法を教えてください。 贈与については国税の中でも最高レベルの税率が設定されているため、知識不足により膨大な税金を課せられないように注意したいものです。 贈与税の基本 最も基本的なことで押さえなくてはならないのは「基礎控除」です。 贈与税の基礎控除は、もらう人一人……
親が亡くなる前に親の現金で私の借金を清算してもらいました。これは贈与にあたるのでしょうか? 本来、子供自身が返済するべき借金を親に支払ってもらったケースは贈与に該当します。特にこのケースは親が亡くなる前ということで死亡前7年以内の贈与であれば、取り扱いに少々注意が必要です。 原則的な考え方 子供が返済するべき借金を親が返済すると、親から子供への……
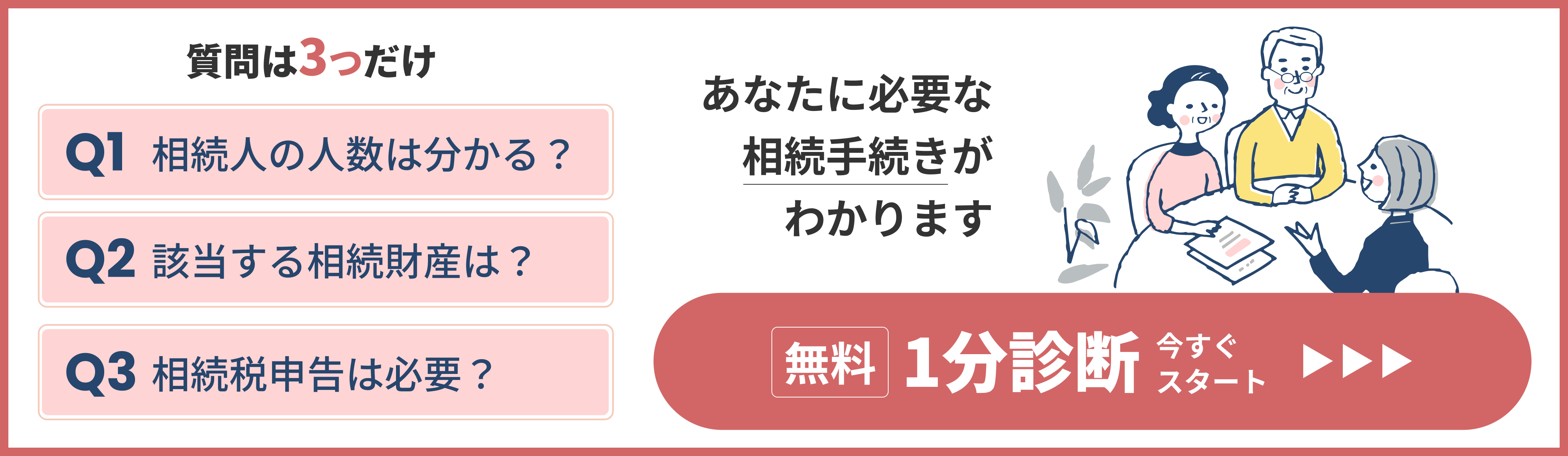
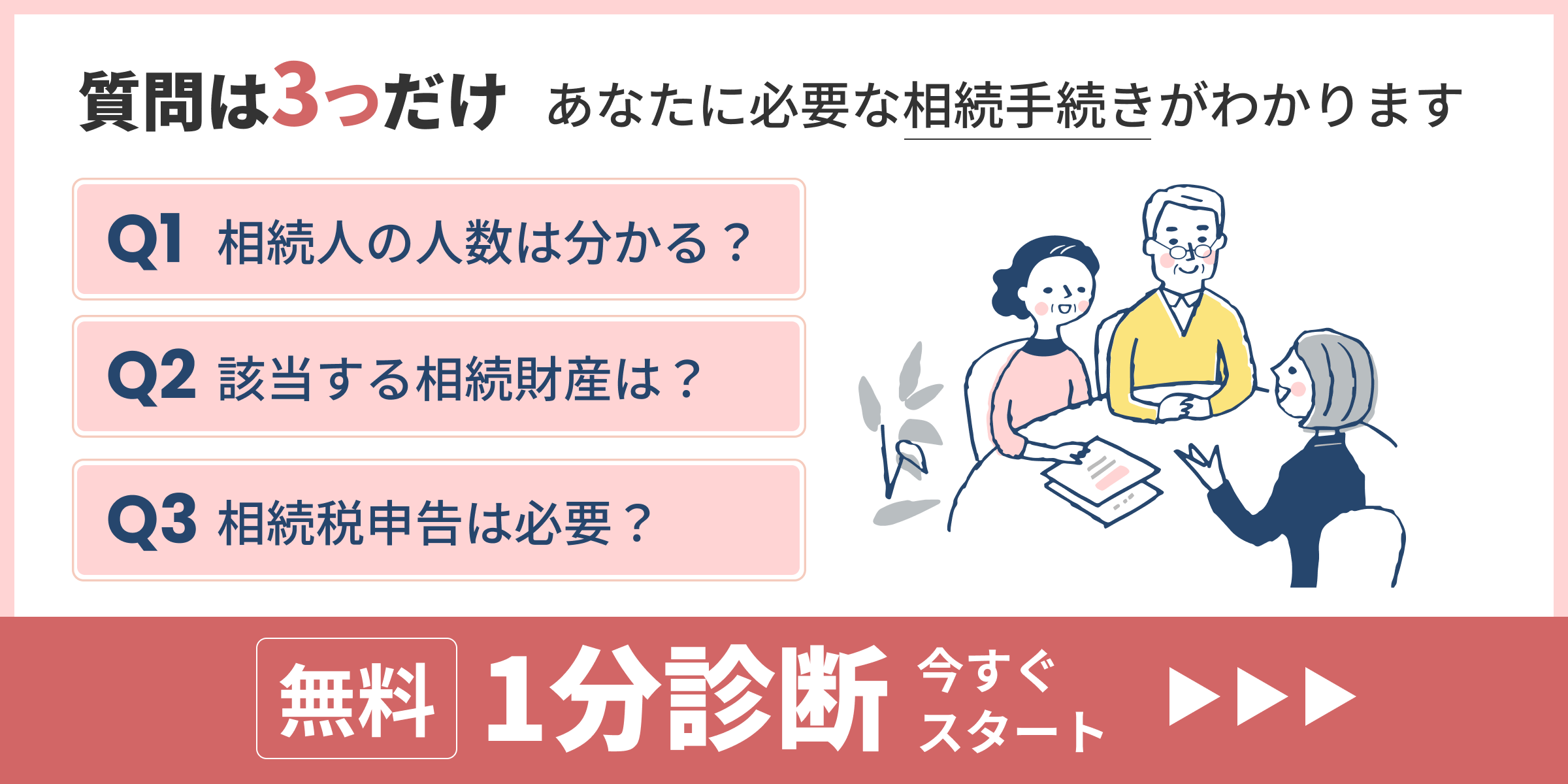
質問者:S.N 生前贈与の場合、各種の特例を使って減税、免税にすることができる場合もありますが、そうではないのであれば非常に高額の贈与税を支払うことになりますので一般的には借用として「相続」扱いにした方がトータルで安くなる可能性が高いでしょう。 相続税の基礎控除の範囲に収まっているかどうか 相続税を回避するために生前贈与でどんどん子孫に財産を移……
質問者:I.C 「生前贈与」という言葉は、相続人やそれ以外の人に対する贈与全体を包含する表現になりますが、「遺贈」や「相続」と対比する場合に使われることが多くなるでしょう。 「生前贈与」とは? 生前贈与とは、文字通り贈与者が生きている間に自分の財産を誰かに渡すことを指した言葉です。遺贈(死亡に伴って誰かに財産を渡す)や相続(死亡に伴って必然的に……
父が存命なうちに私の分の相続財産をもらっておいても問題ないですか? お父様が亡くなっていないので前もって遺産分割をするということはできません(生前の遺産分割は法的に効力がありません)が生前贈与という形では可能です。「相続時精算課税」であれば遺産の前倒しという意味合いで生前贈与が可能です。ただし、生前贈与にあたっては、「税務的な問題」や「他の相続人と……
成年後見人に弁護士がなることも多いと聞きましたが、本職がありながら片手間にできるようなものなのでしょうか? 成年後見人は、もっぱら被後見人(後見を受ける側の者)の法的な保護を目的としているため、法律知識のある弁護士や司法書士が就任することも多くなります。 ただ、業務の煩雑さはその被後見人の抱える事情によってまったく異なるため、月に1~2回程度何らか……
去年念願のマイホームを購入したのですが、どうしても予算オーバーしてしまい200万円ほど親から頭金を出してもらいました。これは生前贈与にあたりますか?お金をもらったことは兄には内緒です。 マンションの頭金であればある程度まとまった金額と思われるので、「特別受益」として相続財産に加味する形で遺産分割協議をした方がよいと考えられます。後の相続トラブルに発展す……
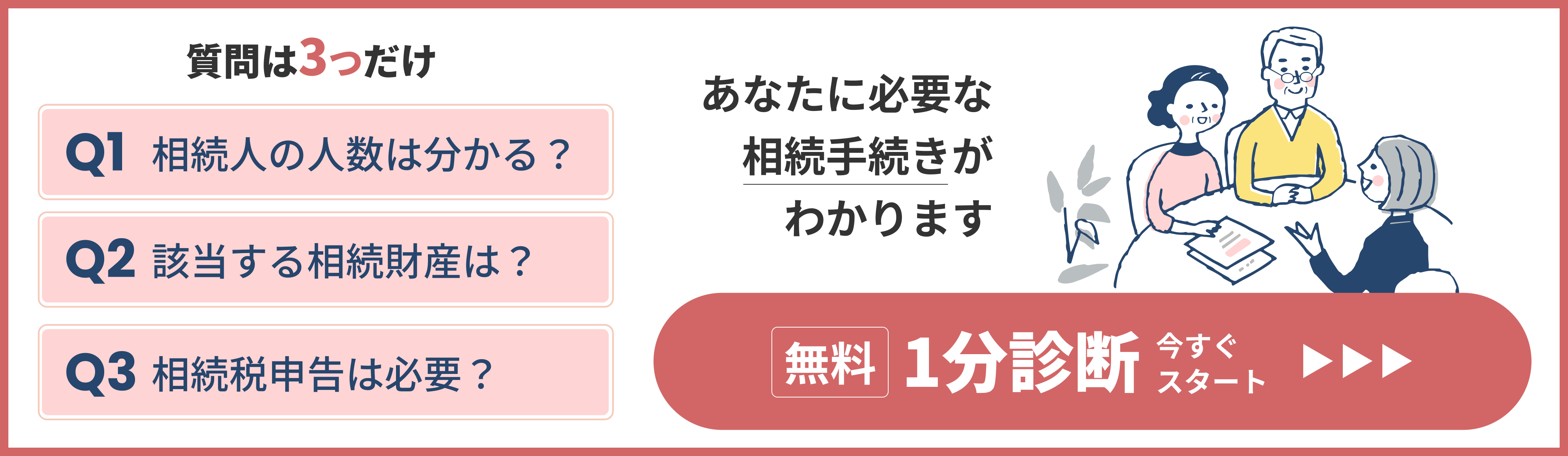
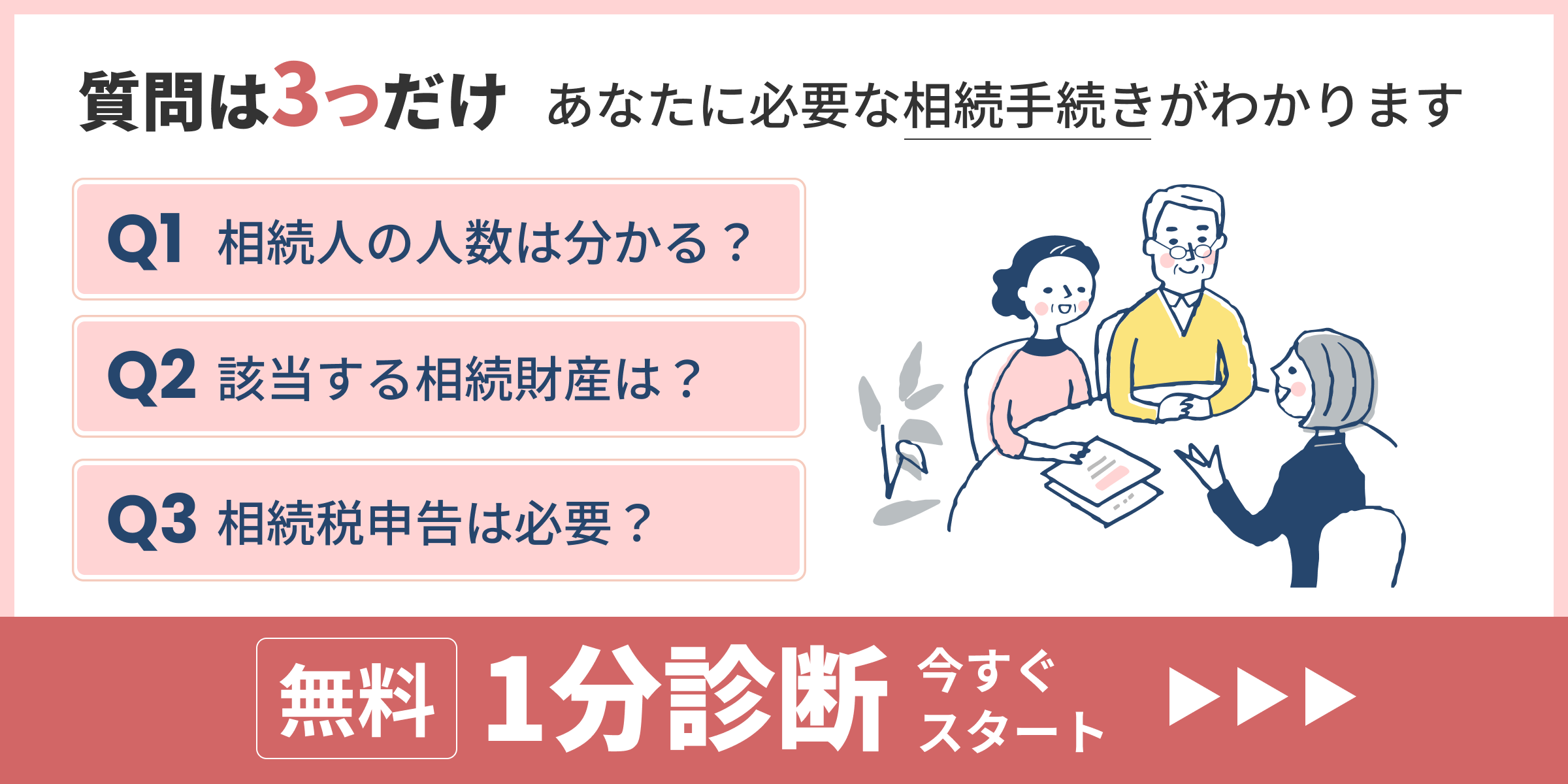
大学生になって地方から上京したのですが、親からの月に10万の仕送りは生前贈与になりますか? 親が子に対する仕送りは贈与税がかからないのが基本とされています。 贈与税を考えるにあたって、「通常の贈与」と「自分が扶養している相手への仕送り」は分けて考えることができます。 どのような点を基準に区別し、どこから贈与税がかかるのかを以下に解説していきます……
私は大学入学時に地方から上京したので、毎月15万ほど仕送りをもらっていました。これはもしかして贈与税がかかりますか? 親子間のような扶養義務が発生する者の間では「通常、必要となる生活費や学費」については贈与税が課せられません。 扶養すべき者に対する贈与は無税 基本的に、贈与税は年間110万円を超える贈与を受けた受贈者が申告・納税の義務を負って……
結婚するにあたって、親から500万円ほどお金を出してもらいました。これは贈与税はかかりますか? 結婚祝いやご祝儀については原則非課税とされています。結婚費用の多額の援助については、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」を利用することで300万円まで非課税となります。 贈与税のかからない財産 親……
先日父から生前贈与をされたんですが、何か証明するものがあったほうが良いですよね?預金通帳があれば良いでしょうか。 生前贈与の存在を税務署に対して証明するには贈与契約書が最も大切な書類となります。契約内容を履行したことを補足的に説明する意味では、預金通帳も必要な資料といえるでしょう。 生前贈与はその契約を明確にする必要がある 当事者たちは生前……
海外在住の、生活が苦しいと言う息子に仕送りをしたいと思っています。これは贈与税はかかりますか? 日本の税法で言うところの贈与税がどの範囲までかかるかというのは、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の住所、財産の所在地の組み合わせによって決まります。しかし外国の税法が関係してくることもあるため若干、複雑です。 そもそも「住所」とは? 税……
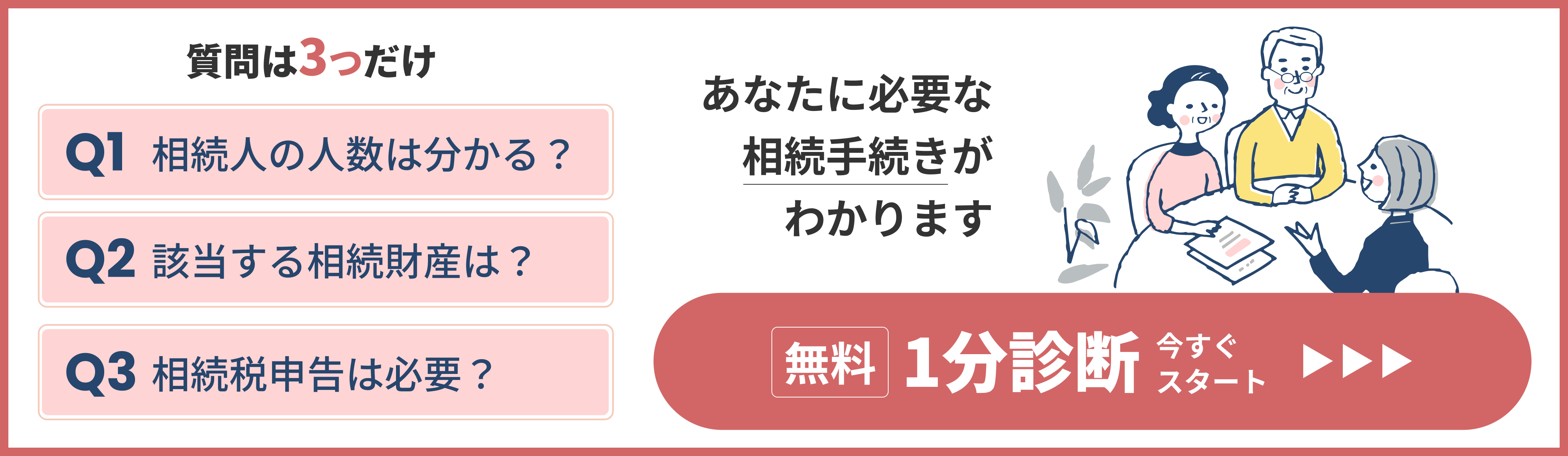
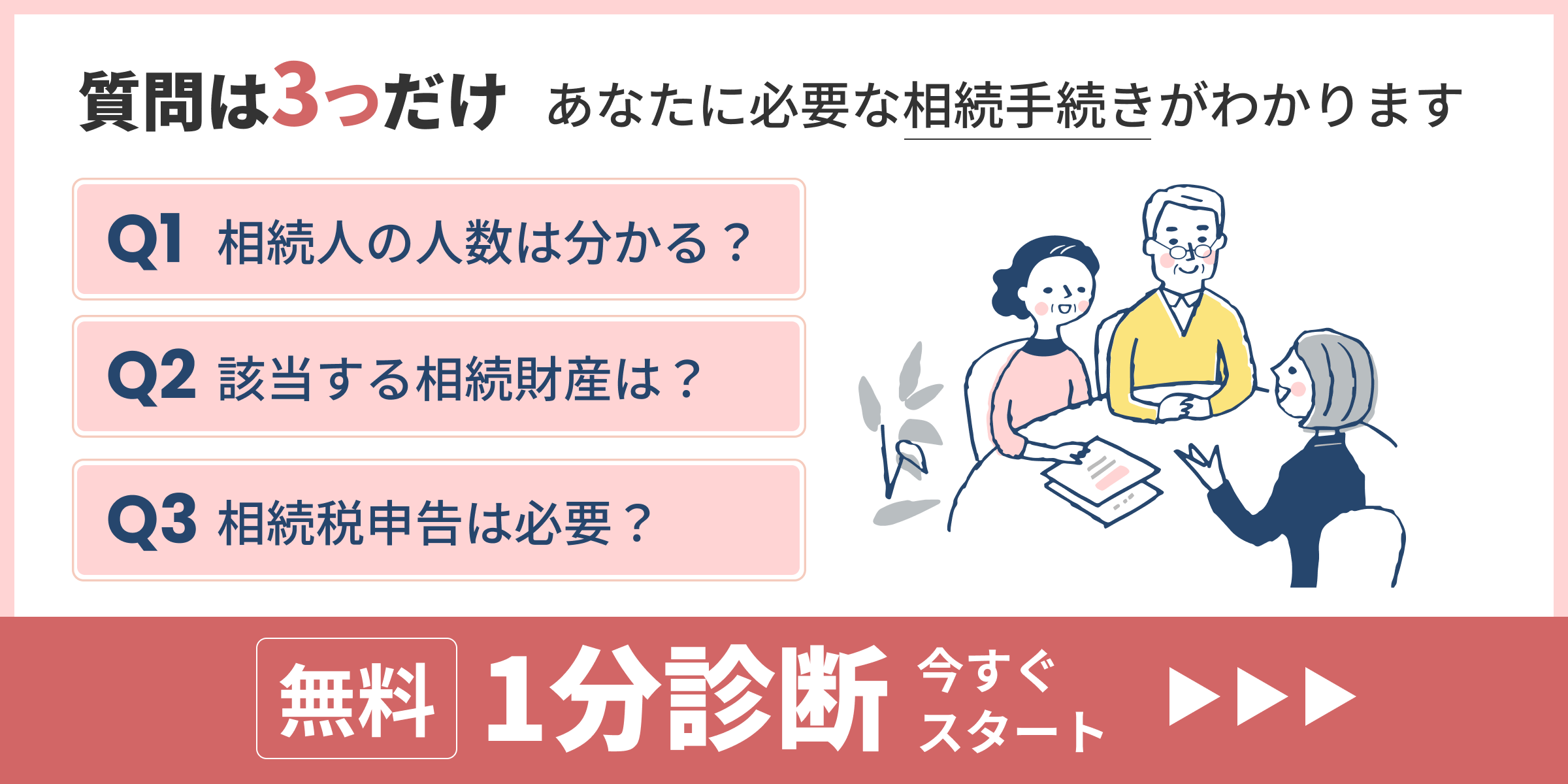










口コミ評価件数No.1に関する注意事項
相続関連ポータルサイトを対象とした口コミ評価件数の結果による(自社調べ/調査時期:2024年12月/調査対象サイト:いい相続、相続費用見積ガイド、相続会議、ベンナビ相続、相続プラス、そうぞくガイド、ミツモア、つぐなび、相続弁護士ドットコム、相続弁護士相談広場、相続弁護士相談Cafe、他/調査方法:調査対象サイトにアクセスし、士業個人及び士業事務所に対して相続に関する内容で掲載されている口コミ評価=レビュー点数のある口コミの件数を合算。※同一ユーザーの口コミが重複掲載されている場合は除外。※同一事業者が複数サイトを運営している場合は合算して事業者単位で集計)
Copyright(C) Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved. 無断転載・剽窃禁止
無料相談 相続のお悩みを解決 相続のお悩みを解決!まずはご相談ください
今すぐ電話で無料相談
平日
9:00〜19:00
土日祝
9:00〜18:00