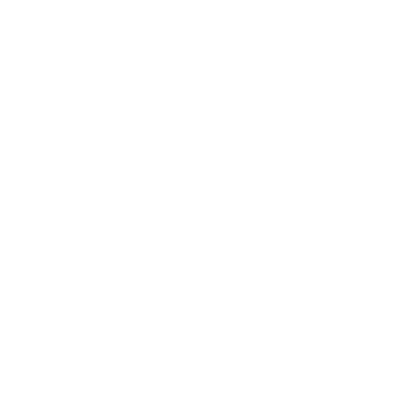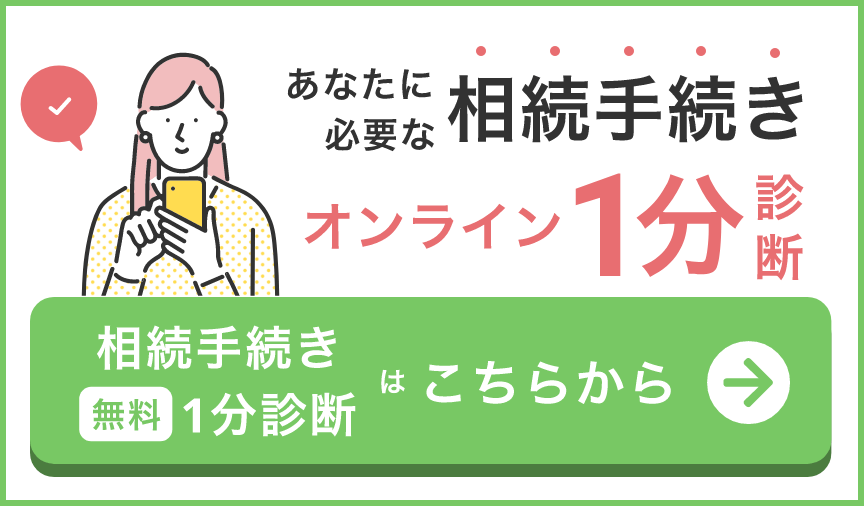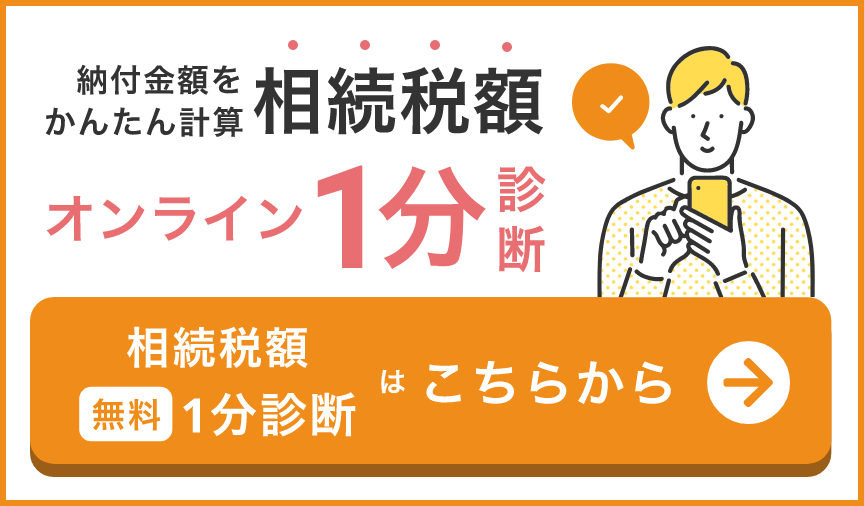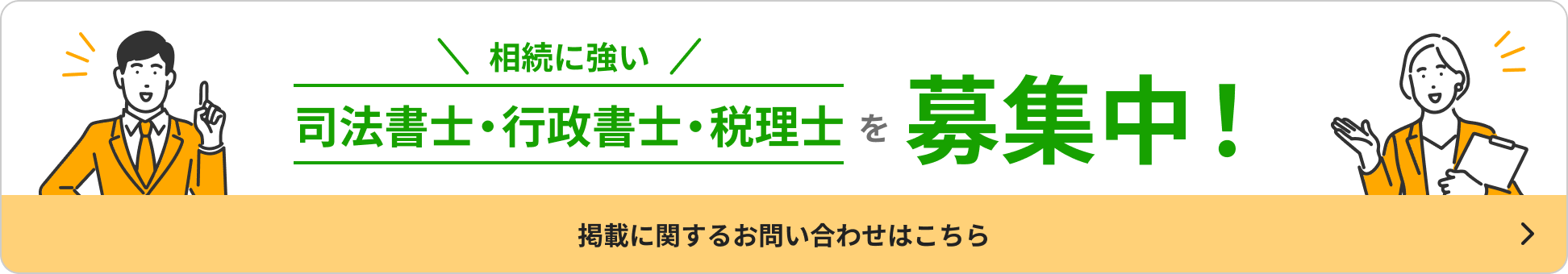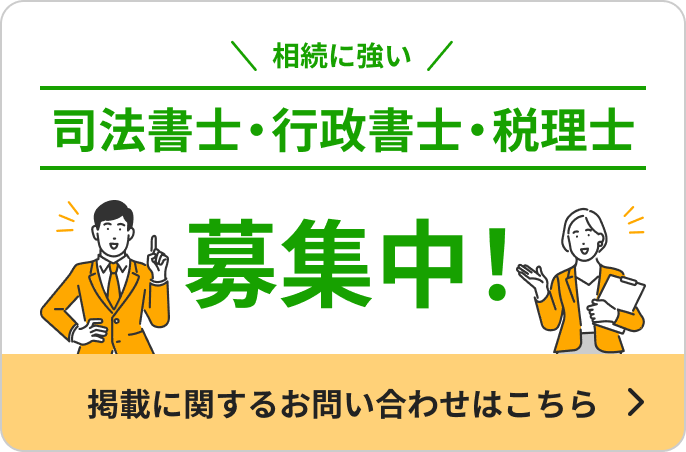遺言書が必要になる場面、個別の事情があるとき【行政書士執筆】

民法では、相続人が開始した場合の相続分を定めていますので、原則、これに従って遺産を分けることになります。この民法で定められている相続分を法定相続分といいます。例えば、「子及び配偶者(妻)が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」というように定められています。被相続人(父親)の遺産が1,000万円だったとします。この場合には、子及び配偶者(妻)が500万円ずつ相続することになります。しかし、この規定は必ず守らなければいけないものではありません。そもそも、相続といっても、財産の状況や家庭環境など様々で一律に相続をこなすことはできません。
そこで、今回は、個別具体的な事情に照らして遺言の必要性を見ていこうと思います。


遺言書とは
皆さん「遺言書」という言葉を知っていますか。聞いたことはあっても、「遺言書」がどういったものか正確に答えられる方は少ないと思います。
「遺言書」とは、一般的には残された遺族の方に向けたメッセージとしての意味合いで使われているかもしれません。しかし、この意味合いで使うのは「遺書」とう言葉になります。
では、「遺言」と「遺書」の違いはなんでしょうか。この2つの違いは、法的効力があるかないかです。「遺書」は、遺族の方に向けたメッセージで法的効力はありません。一方、遺言書は、法的効力をもつ公式な書類です。
遺言は、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者(亡くなった方)の意思表示です。遺言がないことによって相続財産について争いが生じることがとても多いです。遺言は、そういった争いを未然に防ぐためにも大事です。しかし、遺言だったらなんでも良いというわけではありません。そこでこの遺言が示されている遺言書がどのような場面で必要になるかを理解することが大事になります。
遺言執行者
遺言執行者とは
遺言執行者とは、各相続人の代表として遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことをいいます。
具体的には、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
相続が開始すると、遺言執行者は、選任されたことについて承諾するか断るかの回答をしなければなりません。遺言で、この遺言執行者の指定をすることができます。
遺言で遺言執行者を選任するメリットとしては、相続人が複数いる場合には、作成する書類の収集や署名押印手続きなど何かと煩雑になっていますが、遺言執行者を指定していれば、執行者が相続人代表者として手続きを進められるので、手続きが円滑に進められます。遺言での遺言執行者の選任手続きを見ていきましょう。
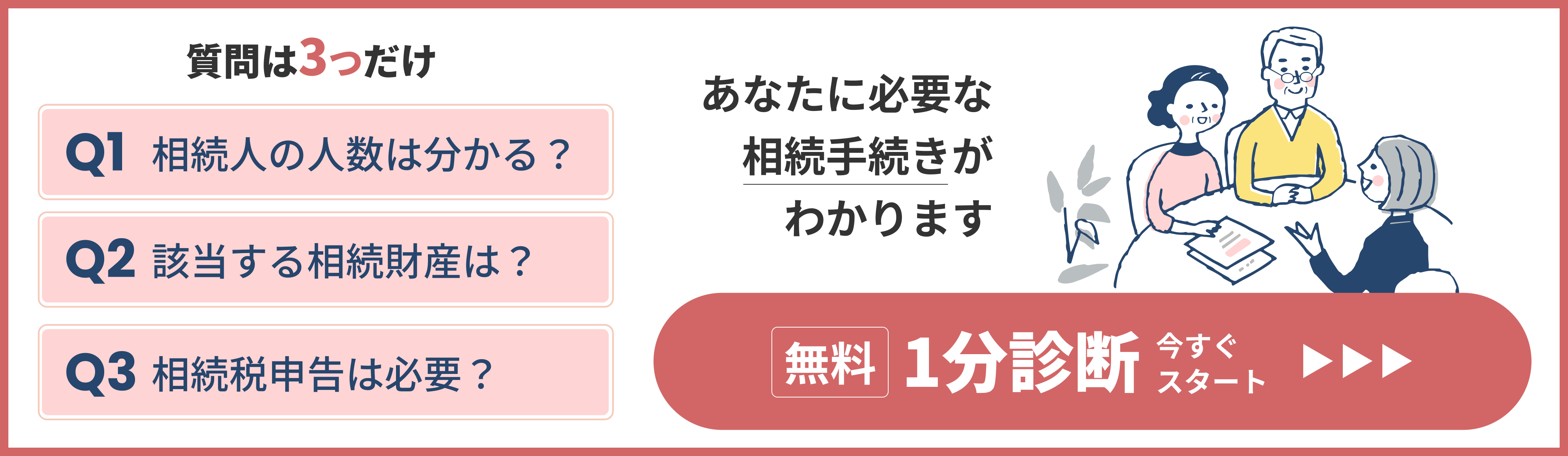
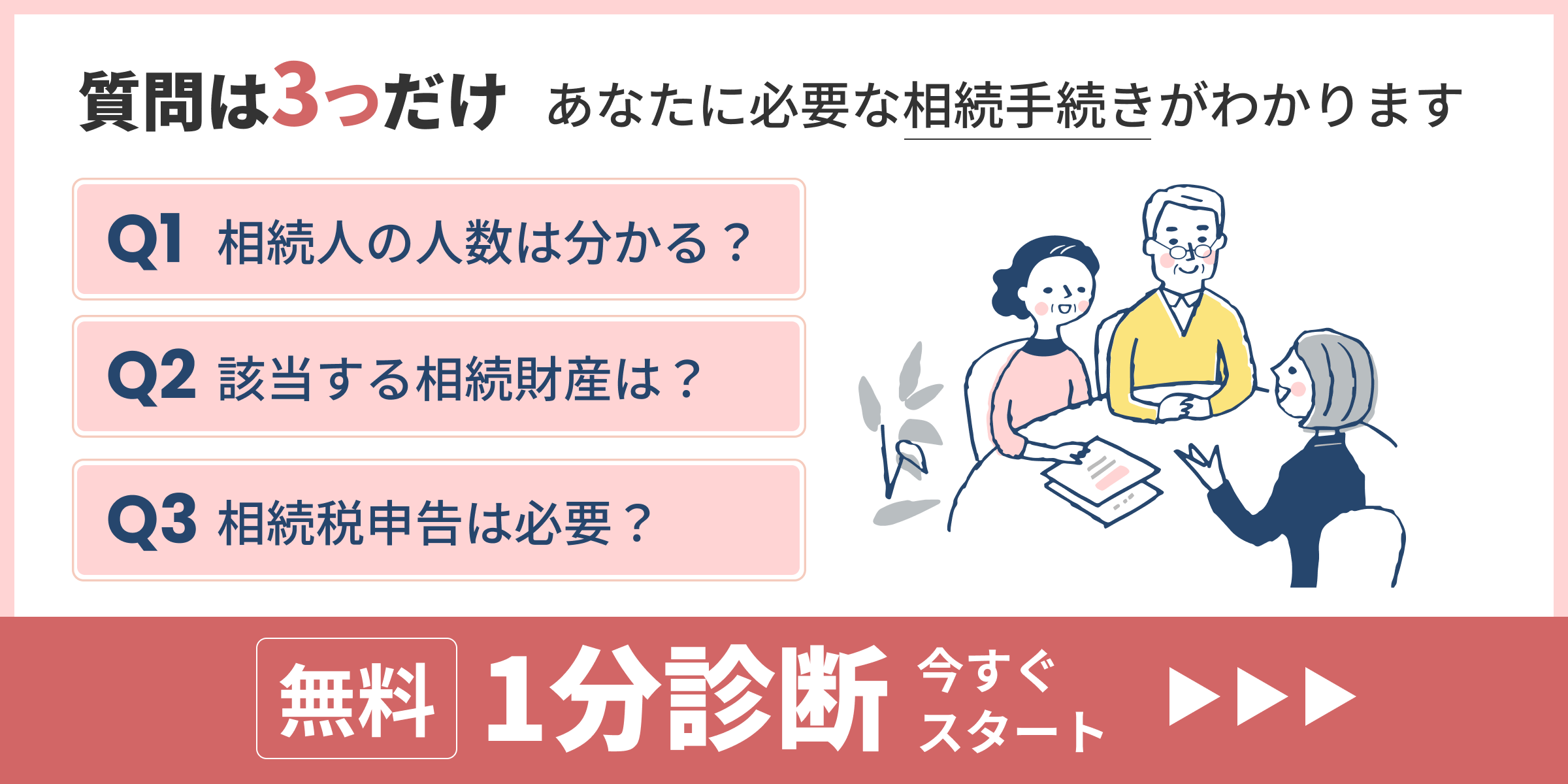
遺言執行者を指定するとき
では、遺言の内容を執行する遺言執行人を選任しましょう。
遺言執行者の選任の方法は、①遺言書で指定する、➁第三者に遺言執行者を指定してもらうような遺言書を作成する、③遺言者死亡後に家庭裁判所にて遺言執行者を選任してもらうという3つがあります。
この3つ以外の方法でいつ誰でも選任できるわけではありません。未成年者及び破産者は遺言執行者になることができません。つまり、未成年者と破産者以外なら遺言執行者になることができます。
しかし、遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人ですから適当に決めてしまっては後々争いになる可能性が高いです。そこで、できれば専門家に依頼した方がよいでしょう。
遺言執行者に選任されたものが遺言執行者になることを承諾したら就任承諾した旨を相続人全員に通知します。
なお、遺言に、①非嫡出子、➁相続人の廃除とその取消しが指定されている場合には、必ず遺言執行者を選ばなければいけません。
複数の遺言執行者を選任するとき
前述した通り、遺言執行者は未成年と破産者以外なら、原則として誰でもなることができます。
しかし、例えば、法律問題が発生する場合には弁護士などの法律の専門家に遺言執行者を指定するべきですし、税金問題が発生する場合には、税理士に遺言執行者を指定すべきです。
また、絶対に他人に知られたくない事情がある場合には友人などを遺言執行者に指定するのも1つの手です。このように、目的に沿って複数の遺言者を指定したい場合には、複数の遺言執行者を指定することができます。遺言者の意思を確実に実行させるために、複数の遺言執行者を選任し役割を分担させるとよいでしょう。
遺言執行者の報酬を決める
遺言執行者の報酬は、遺言者が遺言書で具体的な金額を記載しておけば、その金額になります。
仮に、遺言書に書いてなければ相続人と遺言執行者との話し合いで決めます。万が一、それでも決まらない場合には、家庭裁判所に決めてもらうことになります。報酬の額は、対象財産の額、執行に要する時間などを考慮して決めます。
なお、遺言執行者には、忠実に任務を行う義務があるので、相続人から請求があれば、いつでも遺言執行の状況について報告しなければいけません。
故意または重大な過失によって遺言執行の処理を間違った場合には、損害賠償の責任を負うことになります。遺言執行者が損害賠償責任を負う場合には、報酬と相殺して残額を支払えばよいことになります。
遺産分割の方法の指定を第三者に委託するとき
遺言によって、あらかじめ遺産分割の方法を指定しておいたとしても、相続開始の時点で財産をめぐる状況が大きく変化している可能性もあります。
そうした場合に、遺言どおりの遺産分割を行うとかえって相続人同士の争いに発展してしまうことがあります。そこで、自分の死後、財産の状況に応じて分割方法を決めてもらうように、第三者に分割方法の指定を委託することもできます。
相続財産に利害関係のない第三者に決めてもらえば、公平な分割として、相続人も納得することになります。相続人は委託された人が示す分割方法を承諾する義務を負います。
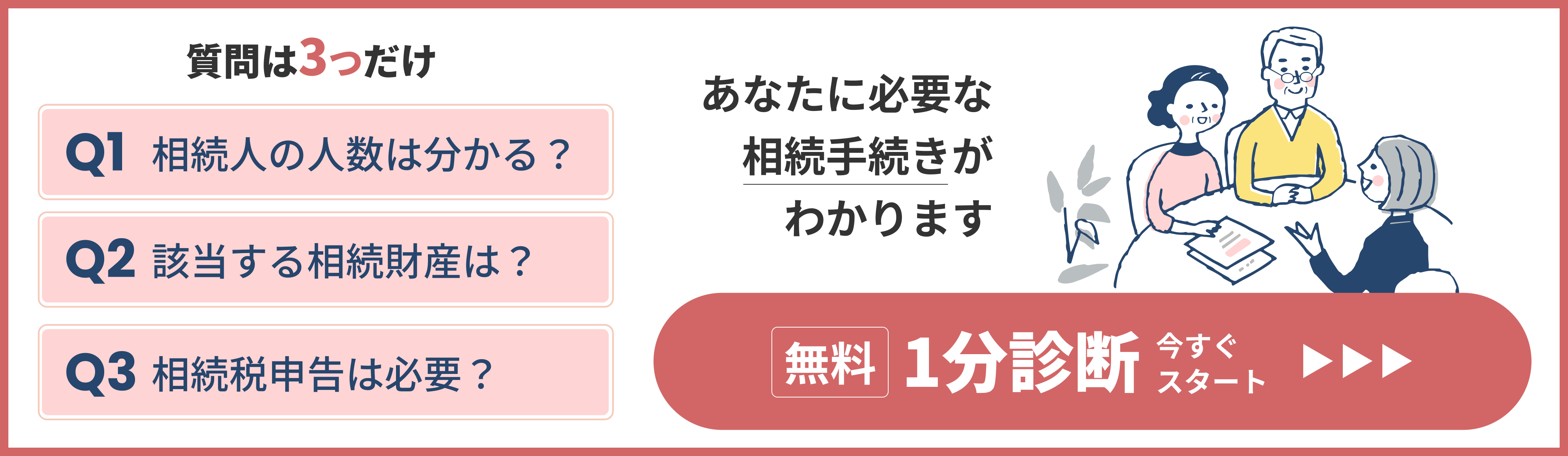
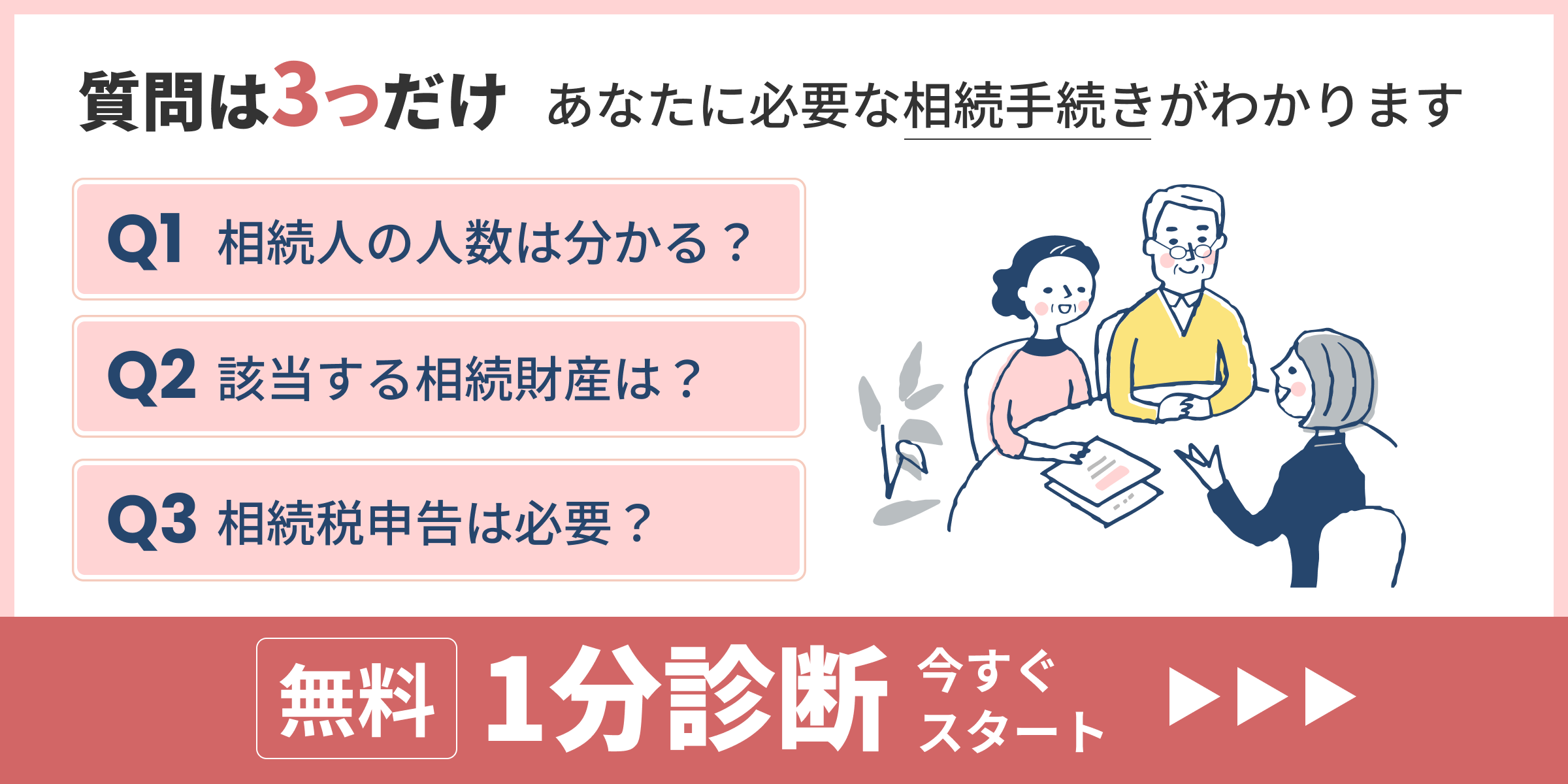
個別の事情があるとき
①夫婦に子がいない場合
夫婦に子がいない場合は、その父母が相続人となります。
父母が死亡している場合には、兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹が死亡している場合には、その兄弟姉妹の子である甥と姪が相続人となります。
この時に、遺言者としては、子がいいないので全財産を配偶者である妻に相続させたい場合には、遺言書を遺します。財産の全てを配偶者に相続させる旨を記載します。もっとも、父母には、遺留分がありますので、気をつけなければいけません。遺留分とは、一定範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。
例えば、遺言の内容によって、今回のように配偶者だけに全ての財産を相続させようとする場合があります。そのような場合に他の法定相続人が遺留分を請求することができるように遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)が認められています。したがって、父母が遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を行使したら、配偶者は遺留分を返さなければいけないので全財産を相続することはできません。
➁相続人が誰もいないとき
配偶者がすでに死亡し、子・親・兄弟姉妹といった法定相続人がいないという場合には、被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故があった者である特別縁故者に財産を分け与えることができます。
特別縁故者として認められる具体例としては、内縁の妻などが該当します。それでも、財産が残った場合には、国庫に帰属します。つまり、国のものになってしまうのです。国にとられてしまうのがどうしても嫌だという方は、遺贈という形で特定の方に譲り渡すのも1つの手段です。
③相続財産の中に寄与分があるとき
被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与、つまり貢献をした相続人は、本来の相続人とは別に、その寄与分を相続財産の中から取得できます。
寄与分を受け取ることができるのは、相続人に限られます。寄与分を反映させる場合には、遺産の総額から寄与分を差し引いた額を相続財産として確定し、その相続財産を受け取ることができます。
寄与分は相続人間の協議で決めるため、遺言による寄与分の指定がそのまま効力を生じるわけではありませんが、遺言者がその相続人の貢献について遺言書に記載することで、遺言者の思いを伝えることができます。
④特別受益があるとき
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたりと被相続人から特別に利益を受けていることを言います。
特別受益を受けた相続人がいるにもかかわらず、法定相続分通りに相続をしてしまうと不公平になってしまいます。そこで、相続人が被相続人から特別に財産をもらっていた場合には、その分を考慮して相続分を算定します。
相続時に遺言で与えられる遺贈も特別受益にあたります。しかし、遺言者が遺言で特別受益を差し引かないとしていた場合には、遺留分の規定に反しない限り、特別受益を差し引くことができません。
特別受益分が遺留分を侵害している場合には、侵害された相続人は特別受益を受けた人に対して遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をすることができます。
⑤相続財産の中に借金があるとき
家をローンで購入した場合に、プラスの財産としての家に加えてローン返済分のマイナスの財産も相続財産になります。ローンなどの債務負担がある家を相続させる場合には、家を相続する相続人に、その家のローンの債務も一緒に相続するように遺産分割の方法を指定するとよいでしょう。
しかし、気をつけなければいけないのは、特定の相続人に債務を承継させる旨の遺言を残しても、それは相続人間でのみ有効になるにすぎません。債権者に対してはその指定相続分を主張することはできず、法定相続人は各相続分に応じてその債務を負担しなければいけません。
⑥子の未成年後見人を指定するとき
未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり、未成年者の監護養育,財産管理、契約等の法律行為などを行います。
未成年の子供に親がいないとき、親権者に代わって未成年後見人が子の身上監護や財産管理を行います。
未成年後見人は、最後に親権を行う者の遺言で指定することができます。
未成年後見人は複数選任することもできます。未成年後見人は親権者と同様の権限と責任をもっていますので、誰を指定するかは、しっかり決めるべきです。
⑦遺産分割を禁止するとき
相続人は、原則として、相続開始後はいつでも遺産を分割することができます。しかし、被相続人は、遺言によって、5年を超えない限度で遺産の一部また全部の分割の禁止をすることができます。
仮に、5年を超えても分割を望まないのなら、被相続人の意思を尊重してもらえるような遺言書の書き方を考える必要があります。なお、この遺言に法的効力はありませんので、遺族の方の判断になります。
⑧遺産で一般社団法人を設立するとき
「一般社団法人」とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を根拠に設立される非営利法人のことです。株式会社が営利を目的とするのに対して、一般社団法人は、非営利法人です。遺言で一般社団法人を設立することができます。設立するには遺言者が、遺言書に定款に記載すべき事項を定める必要があります。
その後、遺言執行者が、定款を作成し、一般社団法人を設立します。そのため、遺言執行者には、どのような法人を設立したいかなど被相続人の意思がしっかり伝わるように事前に話し合うなどして詳細を明確にしておいた方がよいでしょう。
まとめ
今回は、個別具体的事情に当てはめて遺言の必要性をみてきました。しかし、あくまで、いくつかの代表的な例を挙げたにすぎません。ここで挙げた以外にも遺言が必要な場面は被相続人によって全く違います。また、ここで挙げた事例も被相続人によっては変わる可能性ももちろんあります。したがって、相続に関する多くの知識と経験を持っている行政書士などの専門家に相談し、サポートしてもらう方がよいでしょう。そうすることによって、争いのある「争続」になることなく、被相続人の意思を尊重し、相続人全員が納得いく相続とすることができるでしょう。


▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きや遺言書の作成を依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。