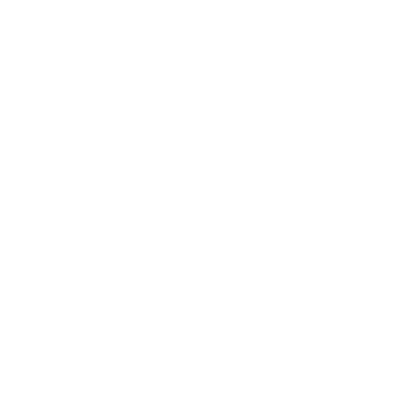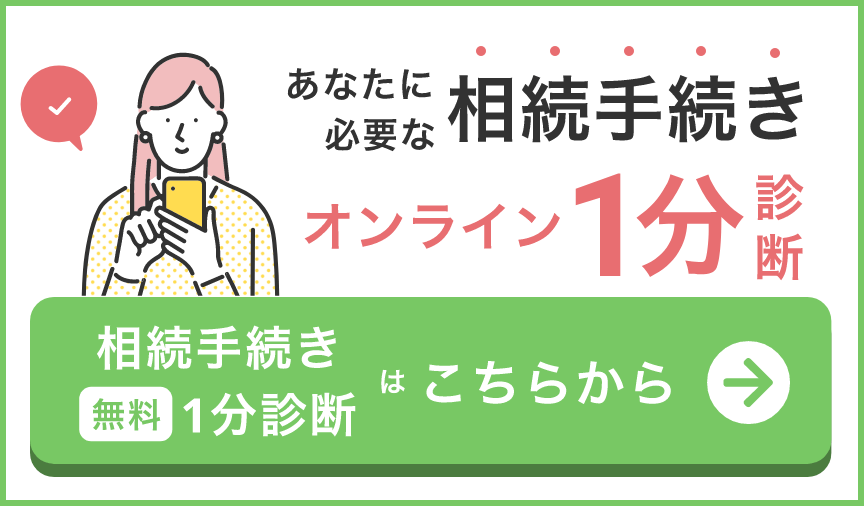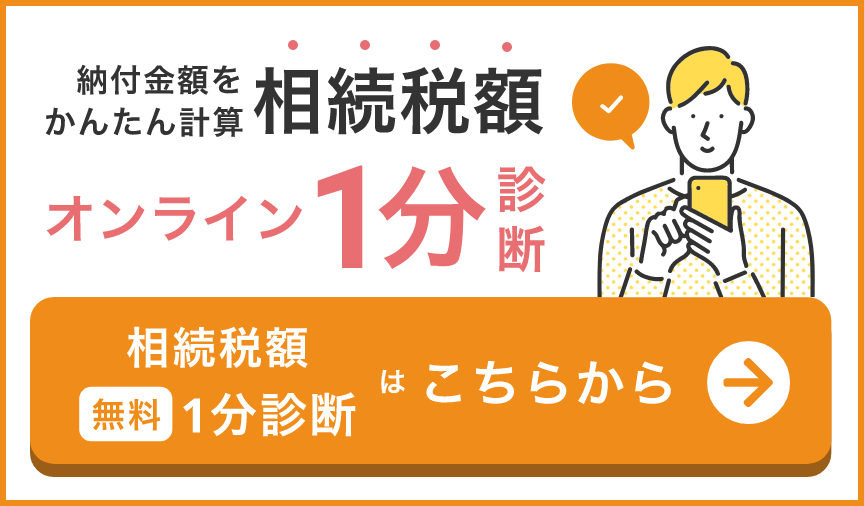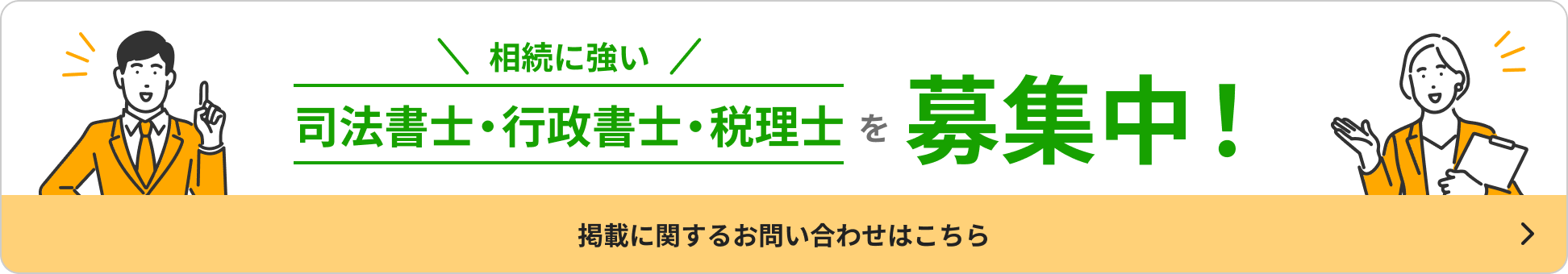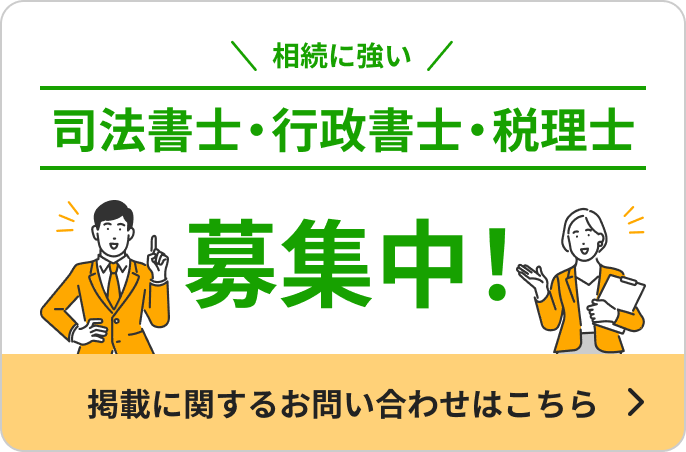遺言書が無効になるパターンとは?争族事例で見る、納得できない遺言書の対処法【弁護士・司法書士監修】

遺産相続では、「遺言(遺言者の意思)は、法で定められた相続分(法定相続分)より優先される」という大原則があります。しかし、遺言の内容が、特定の相続人だけが得をするものだったり、ほとんどの財産を第三者へ遺贈していたり、認知した隠し子に財産を渡していたりするものだったりすると、極めて高い確率で「争族」とも言える相続トラブルが発生します。
このような場合、遺言の無効を確認するための裁判に発展する可能性があり、解決までに長い時間と労力を費やさねばなりません。そうした事態を避けるためにも、遺言者は相続にまつわる最低限の基礎知識を身につけておくべきです。
今回は、遺言書が巻き起こしたトラブルの例をもとに、事態がどんな経緯をたどっていくのかを見ていくことにしましょう。
この記事の監修者

〈代表司法書士〉
福岡県久留米市にて、地域の方々を支える遺言・相続、民事信託、成年後見制度の利用支援など幅広く手掛ける。「わかりにくい法律手続きをわかりやすく」をモットーに、迅速・丁寧な法律家として活躍中。
▶ 森部修道司法書士事務所
この記事の監修者

2020年に海老名にしのだ法律事務所を開設。11年間にわたる相続分野の知識と経験を活かし、遺産相続のあらゆる問題解決に尽力。書籍執筆・セミナー講師実績なども多数。


目次
無効となる遺言書のパターン
- 遺言者本人が書いていない遺言書
- 自筆で書かれてない遺言書(相続財産目録は自筆でなくても良いが、その場合でも全ページに署名押印が必要)
- 作成年月日が書かれていない遺言書
- 署名と押印がない遺言書
- 遺言能力がない人が書いた遺言書
これらは自分で遺言を書く場合(自筆証書遺言)に無効になってしまうケースがほとんどです。
なお、遺留分(相続人に最低限保障された取り分)を考慮せず書かれた遺言書は、無効にはなりませんが争いに発展してしまうリスクをはらんでいます。
弟に父の財産を独占された一郎さんのケース
田中一郎さん(仮名・50歳)は、大学進学をきっかけに地元を離れて上京し、都内近郊に家を建てて家族とともに幸せに暮らしていました。
そんなある日、一郎さんは、地元にいる弟の次郎さん(47歳)から「肺炎で入院していた親父の容態が急変して亡くなった」との連絡を受けます。父・善太郎さん(80歳)は妻の死後、一人暮らしをしていましたが、1年前から認知症に。それ以来、次郎さんが実家の近くの住まいに父を呼びよせ、同居して介護を引き受けていました。それだけに、一郎さんは「すまないなぁ」という負い目を弟に持っていました。
ところが、そんな気持ちが一気に吹き飛んだのは、父の書斎から遺言書が見つかったときのこと。その遺言書には「所有している土地と建物、預貯金などの全財産を次男・次郎に相続させる」と書かれていたのです。
すぐに不服を申し入れると、次郎さんは怒り出し、すごい剣幕でまくし立てました。「親父と同居して、介護もしていた自分には、全財産を引き継ぐ権利がある。地元を見捨てたアニキが偉そうなことを言うな」と。
納得のいかない一郎さんは、勤めている会社の顧問弁護士の紹介で、相続トラブル解決に弁護士事務所を訪ね、相談することにしたのですが……。
▶介護をすると相続で有利になる?|親族間で揉めないための6つの生前対策
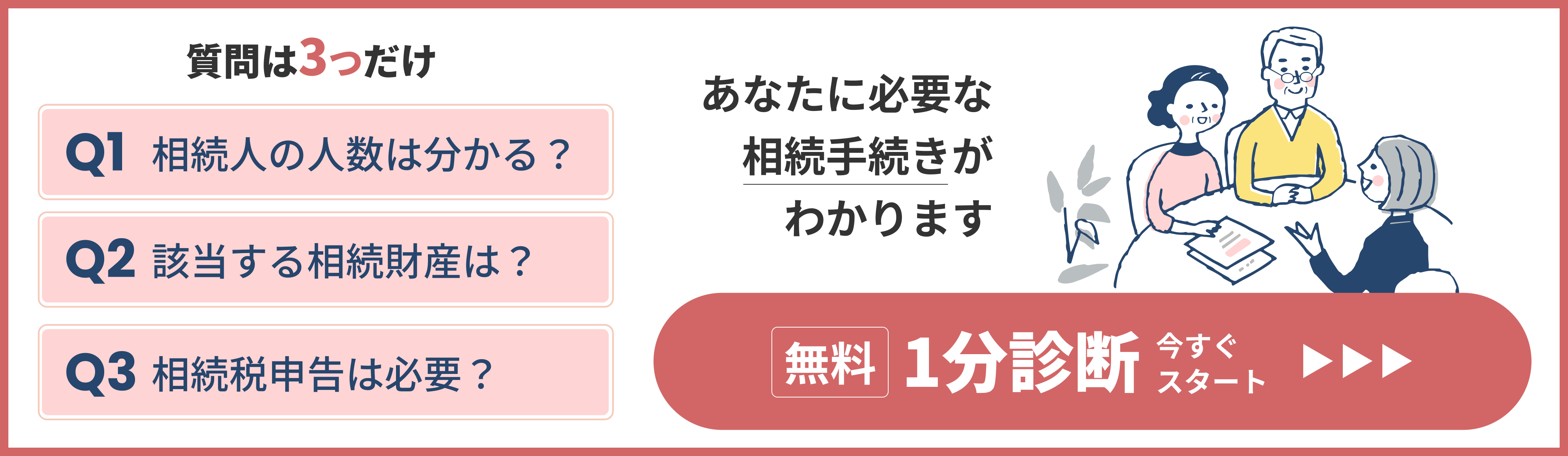
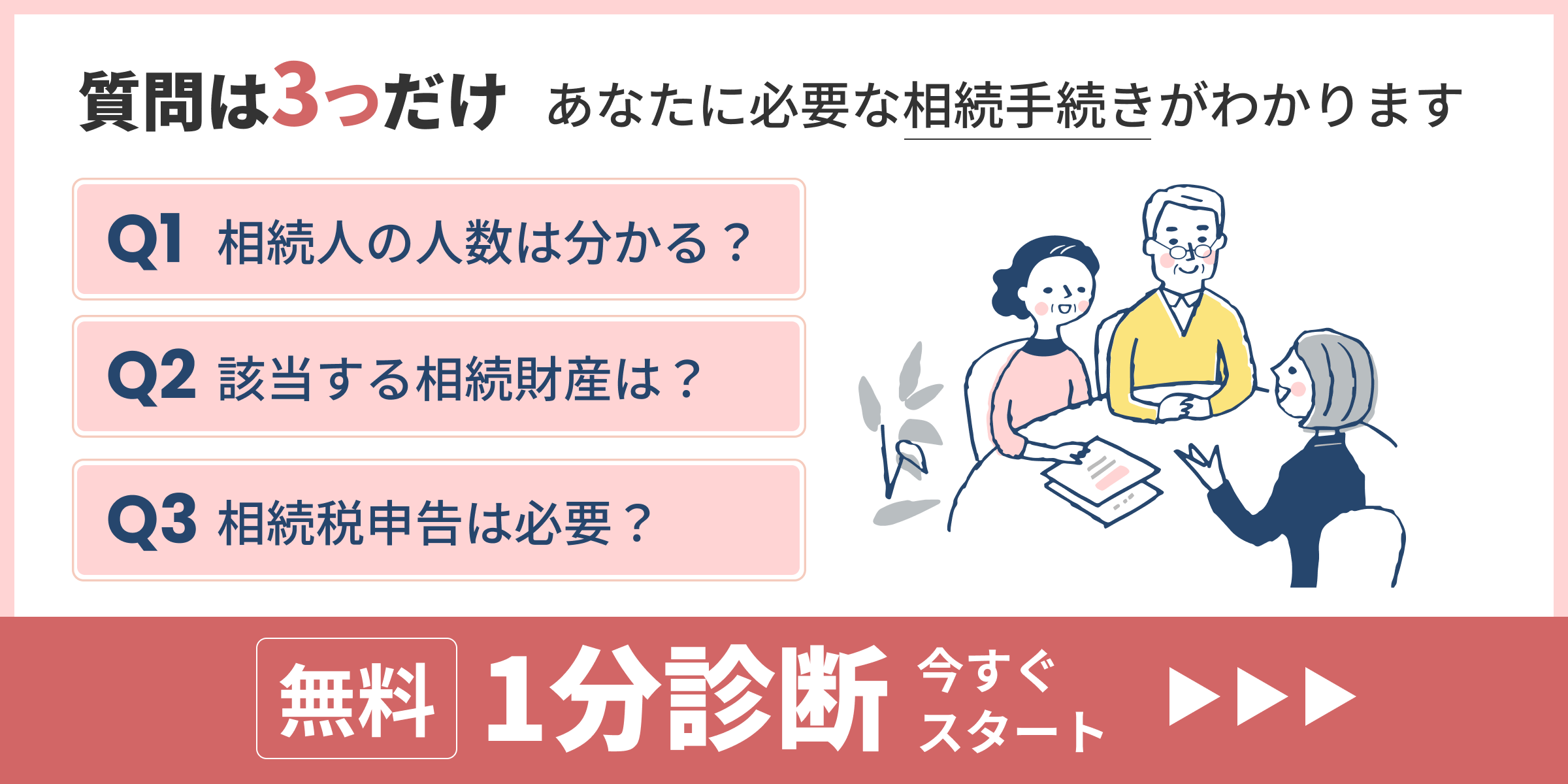
もらえる財産は2分の1?それとも4分の1?
不公平な内容の遺言がなされ、これに不服がある相続人が取りうる手段としては、遺留分の侵害額を請求をする、あるいは遺言書そのものが無効であると主張するということが挙げられます。
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった人)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のこと。遺留分権利者とは、配偶者、子・孫及び父母・祖父母等で、兄弟姉妹は含まれません。被相続人の子である一郎さんは遺留分権利者です。
遺留分権利者は、法定相続分を超えて財産を受け取った相続人または遺贈を受けた者(受遺者)に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に当たる金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)といいます。
遺留分の割合は、相続人が誰かということと、その組み合わせによって異なります。一郎さんのケースのように相続人が子2人の場合、その1人である一郎さんの本来の法定相続分は2分の1で、さらにその2分の1が遺留分となります。つまり、遺言の内容にかかわらず、一郎さんには善太郎さんの遺産の4分の1を受けとる権利があるということです。
その一方、遺言書が無効であると認められた場合、各相続人の取り分は法定相続分となります。子同士の相続権はつねに平等ですから(結婚などで異なる姓を名乗っている子も同様です)、一郎さんの法定相続分は2分の1となります。
遺言無効確認事件は、まず「調停」によって始まる
一郎さんが法定相続分の財産を受けとるには、遺言書が無効であることを調停、あるいは訴訟の場で争うことになります。
遺言無効確認事件は、家事調停の対象となる事件ですが、最初から訴訟を申し立てるのではなく、まずは家庭裁判所に対して遺言無効確認調停、または遺産分割調停を申し立てるのが普通です(これを「調停前置主義」といいます)。
家事調停では、非公開の場で裁判官と民間から選ばれた調停委員が当事者の間に入り、中立的な立場でそれぞれの言い分を聞きながら、話し合いによって解決を図ります。


「調停」が不成立の場合、「訴訟」に持ち込む
家事調停の過程で、相手方が遺言の有効性を強く主張して譲歩せず、話し合いによる解決ができなかった場合、遺言無効確認の訴えを提起することになります。
遺言書が有効か無効かを判断するのは、家庭裁判所ではなく地方裁判所です。
遺言無効確認の訴えは、遺言の無効を主張する相続人(本ケースの場合は一郎さん)が単独で原告となって、訴えを提起することができます。
一方、遺言が有効であると主張する相続人(次郎さん)が被告となりますが、遺言執行者(遺言の内容を実現するために遺産の管理や処分権限が与えられた人)の指定がある場合は、遺言執行者を被告とすることができます。
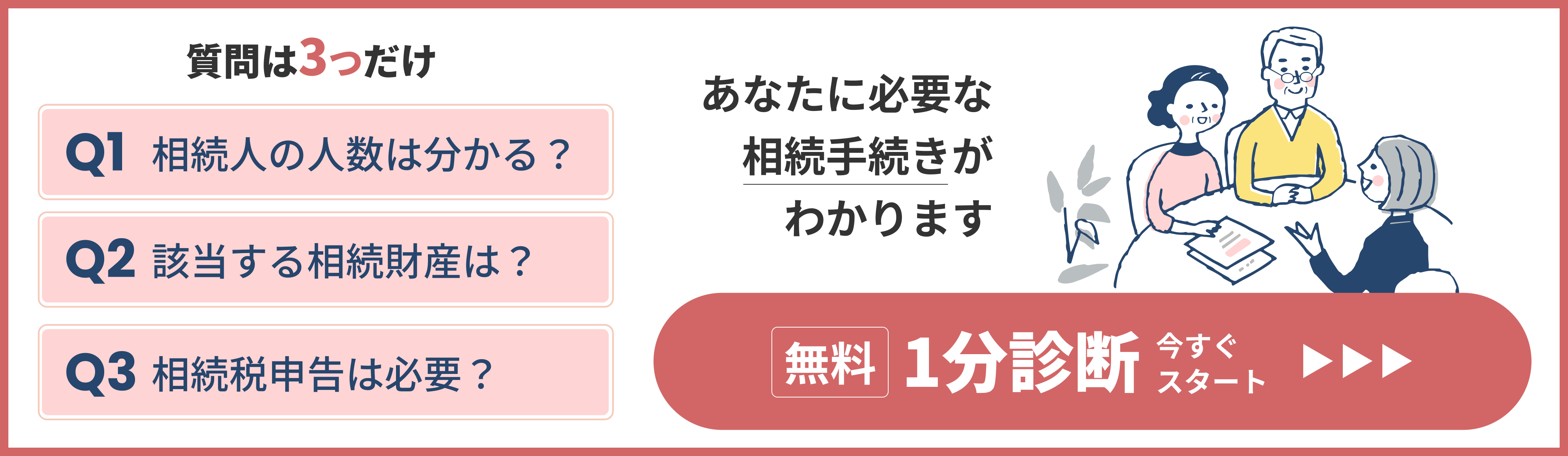
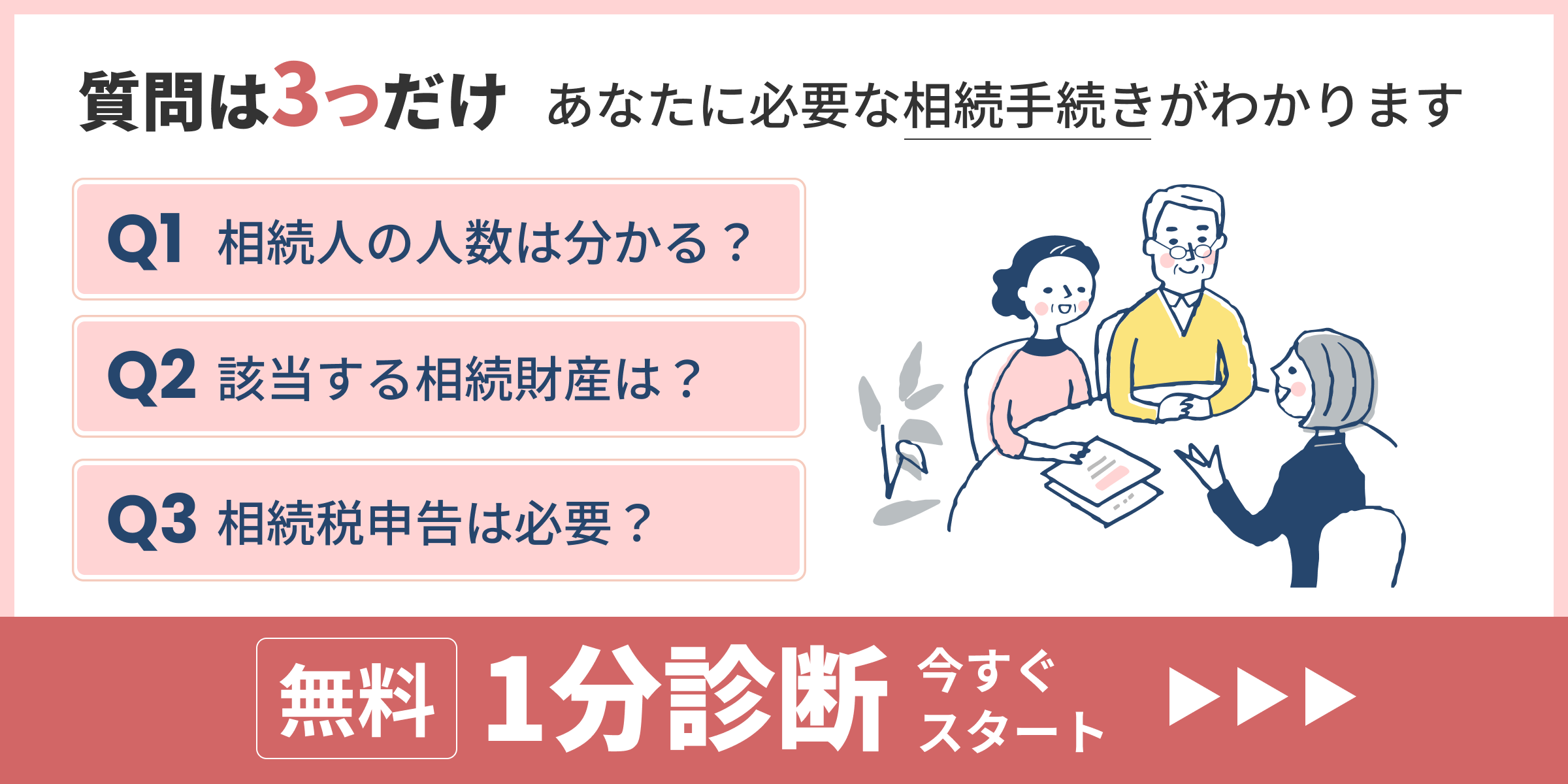
遺言の無効原因である「方式違反」とは?
遺言の無効原因として、まず第一に考えられるのは「方式違反」です。
遺言は、効力が発生するときには遺言者が死亡していることから、民法では遺言の方式を厳格に定め、遺言が遺言者の真意に基づいて作成されたものであることを担保しています。
例えば、自筆証書遺言には次のような方式が決められています。
自筆証書遺言に求められる方式
- 遺言者本人が全文を自筆で書く
- 作成年月日を入れる
- 署名と押印をする
- 書き加え、削除などの加除訂正を行う場合は所定の方法を守る(通常の二重線+印鑑での訂正後、余白部分に変更箇所を明記し、その都度署名)*ただし、全文を書き直す方がおすすめです。
次郎さんが有効だと主張する、善太郎さんの遺言が自筆証書遺言だった場合、以上の方式通りに書かれているかを確認すべきでしょう。
もし、その筆跡に不自然なところがあった場合、善太郎さんが生前に自筆で書いた手紙や書類と、遺言書の筆跡を見比べ、場合によっては筆跡鑑定によって、本人の筆跡かどうかが審理されます。遺言書の筆跡が本人のものでないと判断されれば、遺言書は無効になります。
すべての用紙に作成年月日があるか、加除訂正の方式に誤りがないかを確認し、どれかひとつだけでも欠けていれば、その遺言書は無効になります。なお、用紙が複数枚にわたる場合は、合綴した遺言書の1枚に署名・押印があれば、全体として有効です。
また、遺言書に書かれた不動産の情報が、登記事項証明書と違ったものだったり、預貯金の金額が実際の金額と違っていたりしていた場合、正しい方式で加除訂正されていなければ、その部分について遺言書は無効となる可能性があります。
なお、平成31年(2019年)1月13日以降に作成された自筆証書については、相続財産の全部または一部の目録(財産目録)を添付する際には、その目録については自書しなくても良いとされています。土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することも可能です。
無効と判断されるケースの多い「遺言能力の欠如」
次に考えられる遺言の無効原因は「遺言能力の欠如」です。
遺言能力とは、遺言の内容と、「その遺言を書くことによってどのような効果が発生するのかがわかる能力」のこと。高齢者の自筆証書遺言については、この遺言能力が争われることが多くなっています。
「認知症」も遺言書を無効にする大きな要因
善太郎さんは1年前に認知症になっており、それをきっかけに次郎さんの家で同居を始めたようですが、当時の病院のカルテは「遺言能力の欠如」を証明する有力な資料になりそうです。
認知症患者の遺言能力の有無を判断する指標として、「長谷川式スケール」の点数が使われることがあります。これは20点以上を「異常なし」、16~19点を「認知症の疑いあり」、11~15点を「中程度の認知症」、5~10点を「やや高度の認知症」、4点以下を「高度の認知症」と簡易に診断するためのもの。
しかし、裁判例では4点でも遺言が有効となったものもあれば、15点で無効となったものもあり、一概には言えません。
無効になったとき、有効になったときの具体的な手続き
以上のような経緯を経て、地方裁判所が「遺言書は無効である」と判断した場合は、法定相続分通りに分割をするか、遺産分割協議がまとまればその内容で分割することになります。
その反対に遺言書が「有効である」と判断された場合は、前述した遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)の問題になります。
遺留分侵害額請求権は,相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年(または相続開始の時から10年を経過したとき)に時効によって消滅します。従って、実務においては遺言書の無効を主張する訴訟の中で、「遺言書が有効だった場合は、予備的に遺留分を請求する」という主張をしておくことも考えられます。
ちなみに、遺留分侵害額請求は、遺言によって侵害された遺留分(一郎さんの場合は相続財産の4分の1)に当たる金銭の支払を請求することを指しますが、この制度が開始したのは令和元年(2019年)7月ですから、被相続人がそれ以前に亡くなった場合、これを請求することはできません。
その場合は、旧法下で定められている「遺留分減殺請求」で財産の「分割」を求めることになります。その結果、相続した不動産の権利が共有名義になることもあり、もめ事の解決に至らなくなってしまうという欠点があります。
まとめ
以上、田中一郎さんのトラブル事例から、「遺言無効確認事件」がどのような経緯で進んでいくのかを見ていくとともに、「遺留分侵害額の請求」についても見てきました。
遺言書によって火がついた相続トラブルは、燃え広がるのが早く、関係者の人間関係をあっという間に解消不能な状態にしてしまいます。
そのようなことにならないよう、遺言者は相続について基本的な知識を身につけ、遺言書からもめ事のタネを極力取り除いておくべきです。


▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きや遺言書の作成を依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。