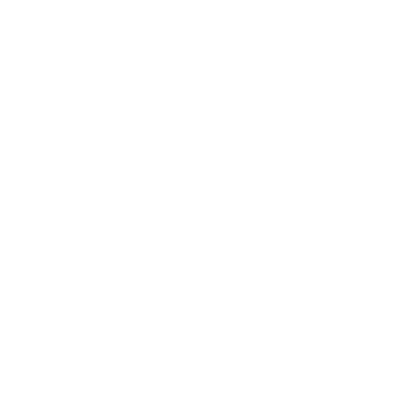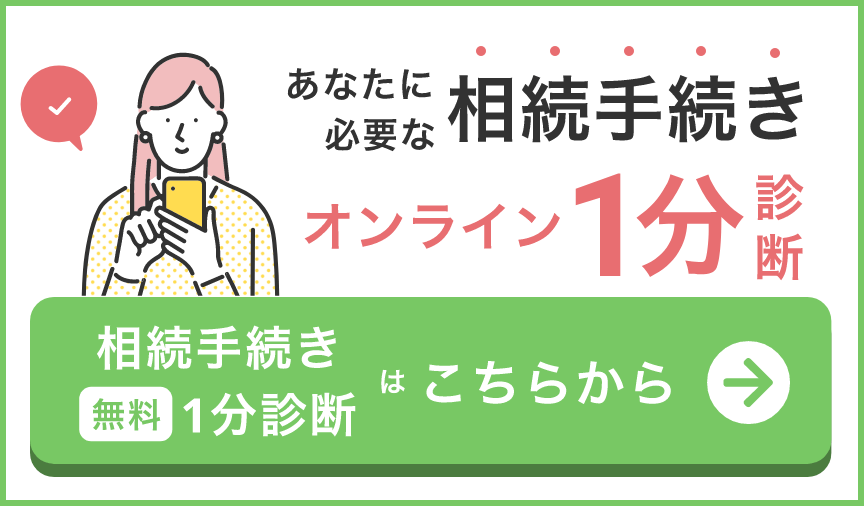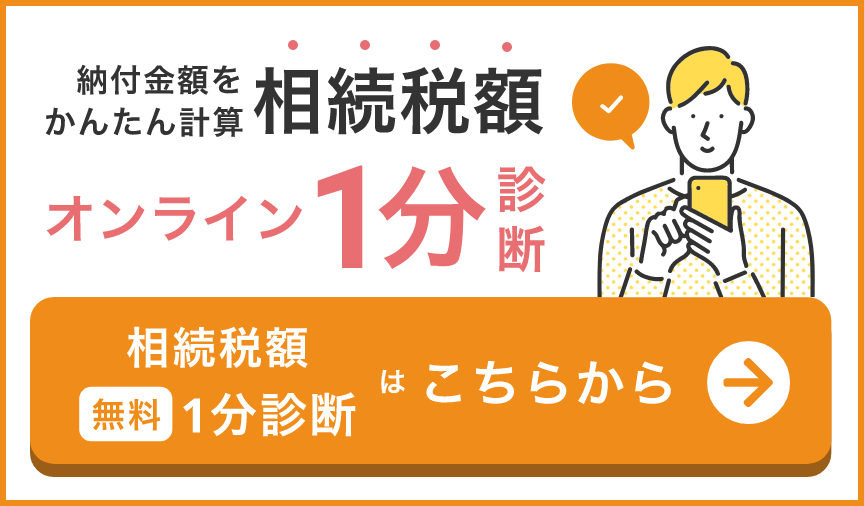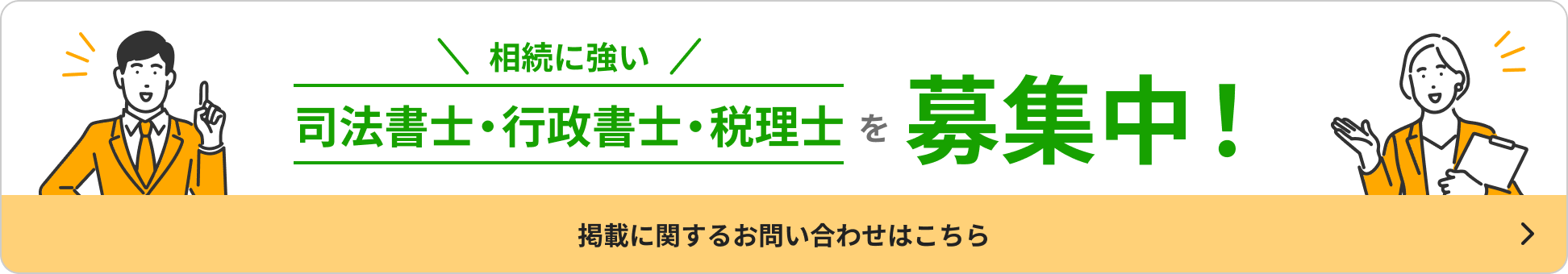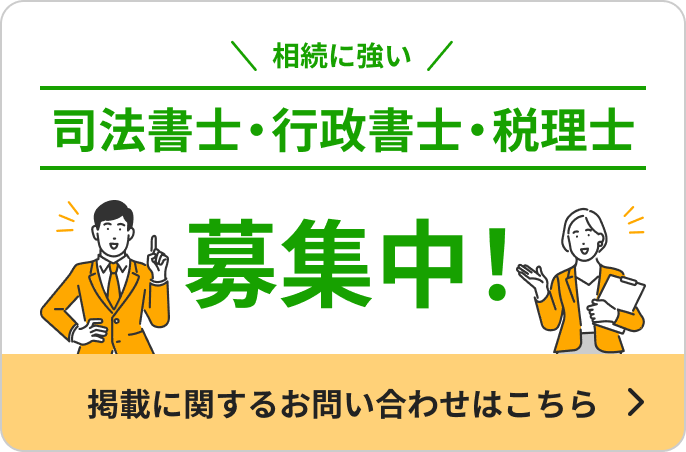相続税の基礎知識|申告・納税期限、基礎控除、相続税のかからない財産、みなし相続財産など

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
こちらの記事では相続税に関する概略をご案内させていただきます。


目次
相続税の申告と納税
相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月目の日までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。
基礎控除とは
相続財産の基礎控除とは、相続税がかからず申告の必要のない一定の金額になります。基礎控除額は法定相続人の人数によって異なってきます。平成27年1月1日以後に発生した相続に対して、基礎控除額は下記のとおりになります。
「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
配偶者と子供1人の計2人が法定相続人の場合、3,000万円+(600万円×2人)となり、4,200万円がこの場合の基礎控除額となります。


相続財産とは
国税庁では、「財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全て」と案内されております。有形無形とわず金銭的価値があるものは財産となります。また日本国内に存在するものだけでなく、日本国外に所在するものも含まれます。
そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか)
上記以外のものとして、次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。
(1) 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
(2) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
(3) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税又は結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
(4) 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます)
(5) 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受け取得した贈与財産
(6) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
(7) 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
相続税の課税対象になる死亡退職金について
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
なお、相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。


相続税の課税対象になる死亡保険金について
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
相続時精算課税適用財産について
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の申告の際に相続時精算課税制度を適用していた場合、上記のようにその財産は相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価格が相続税の課税価格に加算されます。
被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産について
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人がなくなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価格が相続税の課税価格に加算されます。
財産はプラスのものだけではありません
亡くなられた方の債務や負債も財産となります。借入金や未払い金の具体例としては住宅ローン、自動車ローン、カードローンや、未払いの医療費、税金などがあげられます。
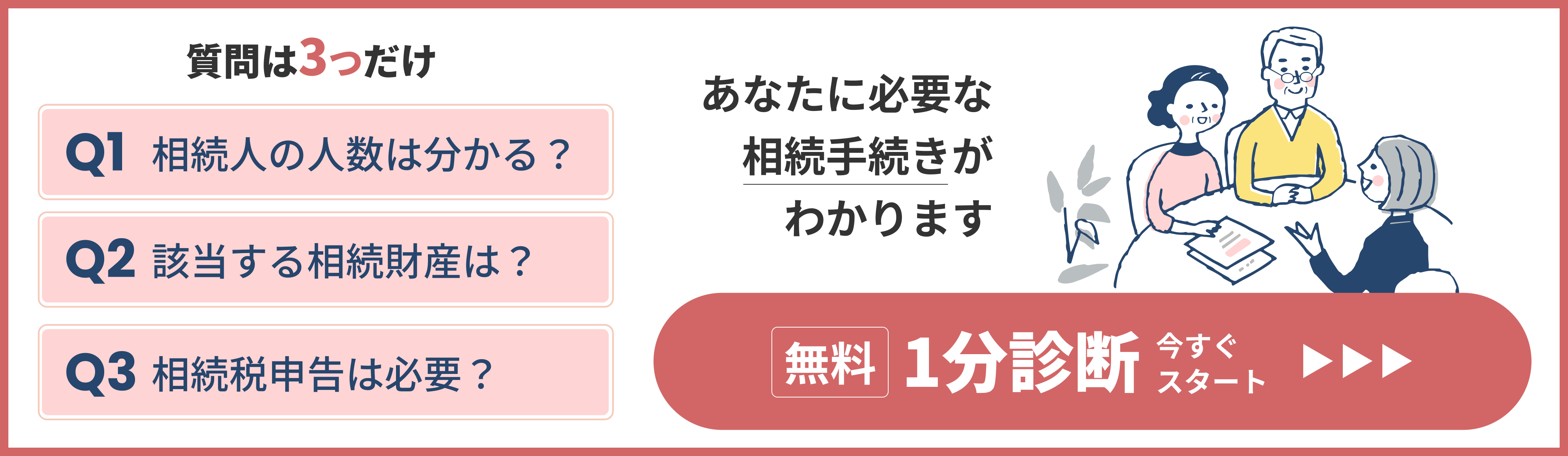
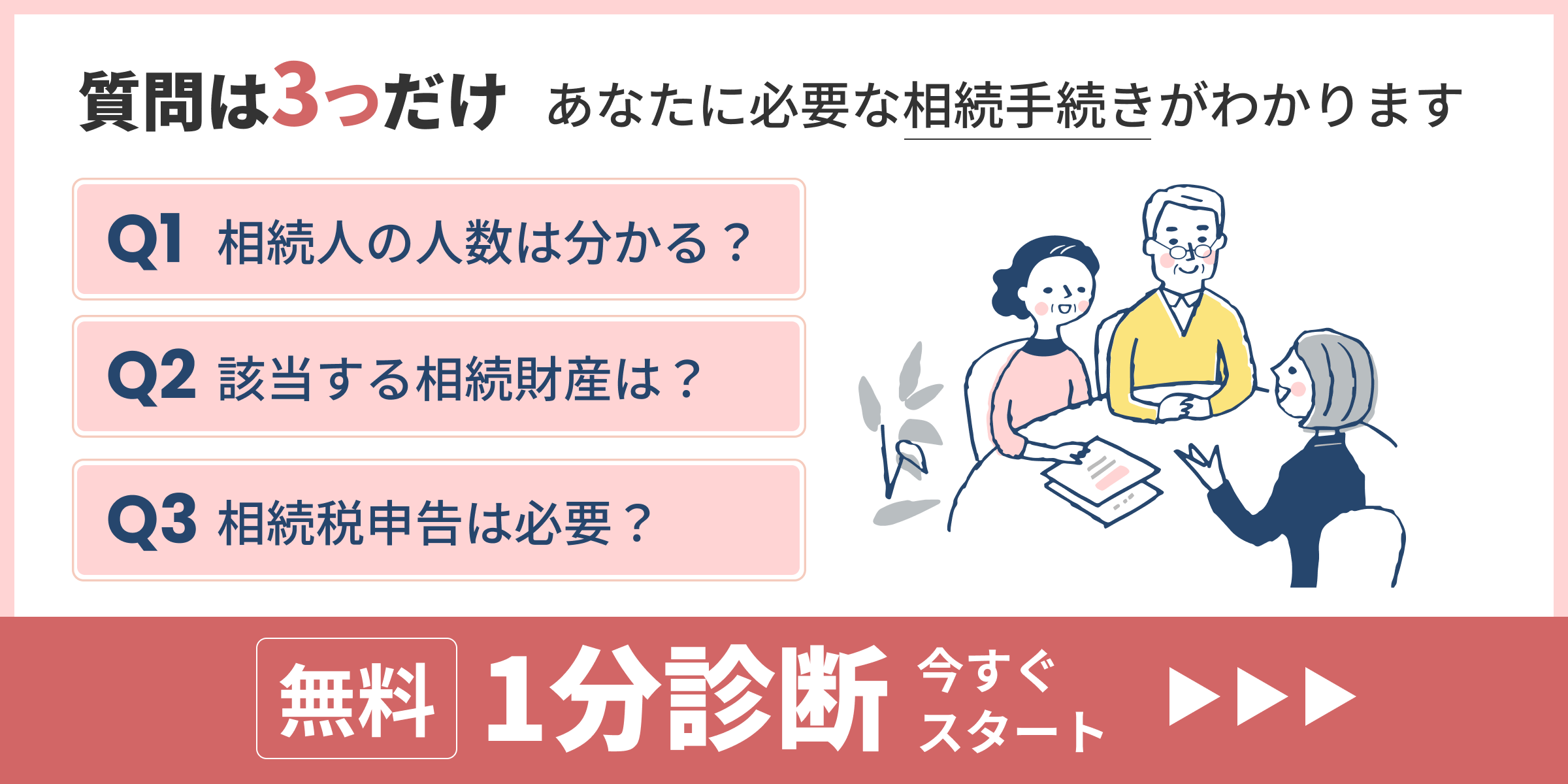
葬儀の費用について
被相続人の葬式で相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引けます。葬式費用としては、お寺などへの支払、葬儀社などへの支払、お通夜に要した費用などがあげられます。また事故等で亡くなってしまった際の捜索や運搬にかかった費用も含むことができます。なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や初七日等の法要に要した費用は、葬式費用に含まれないのでご注意ください。
相続税がかからない財産もあります
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。
- 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利。
- 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
- 相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
- 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
- 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。
主な相続財産の評価方法は?
代表的な財産として、宅地、建物、上場株式、預貯金があげられます。各財産の原則的な評価方法は下記のようになります。
①宅地 路線価方式と倍率方式
路線価方式とは路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方目―問える当たりの価額のことで「路線価図」で確認できます。宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した後、その宅地の面積をかけて計算します。
倍率方式とは路線価が定められていない地域での評価方法です。宅地の価額は原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。倍率は評価倍率表で確認できます。
路線価図や評価倍率表は、国税庁ホームページ(財産評価基準 路線価図・倍率表)にて確認することができます。
②建物 原則として、固定資産税評価額により評価します。固定資産税評価額については都税事務所や市役所、区役所、町村役場にて確認することになります。
③上場株式 原則として、下記の4つの評価額のうち、最も低い価格により評価します。
- 相続の開始があった日の終値
- 相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
- 相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
- 相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額
④預貯金 原則として、相続開始の日の現在の預入残高と相続開始の日の現在において解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額との合計額により評価します。ただし定期預金、定期郵便貯金及び定期郵便貯金以外の預貯金については、相続開始の日現在の既経過利子の額が少額なものに限り、相続開始の日現在の預入残高で評価することとなっております。
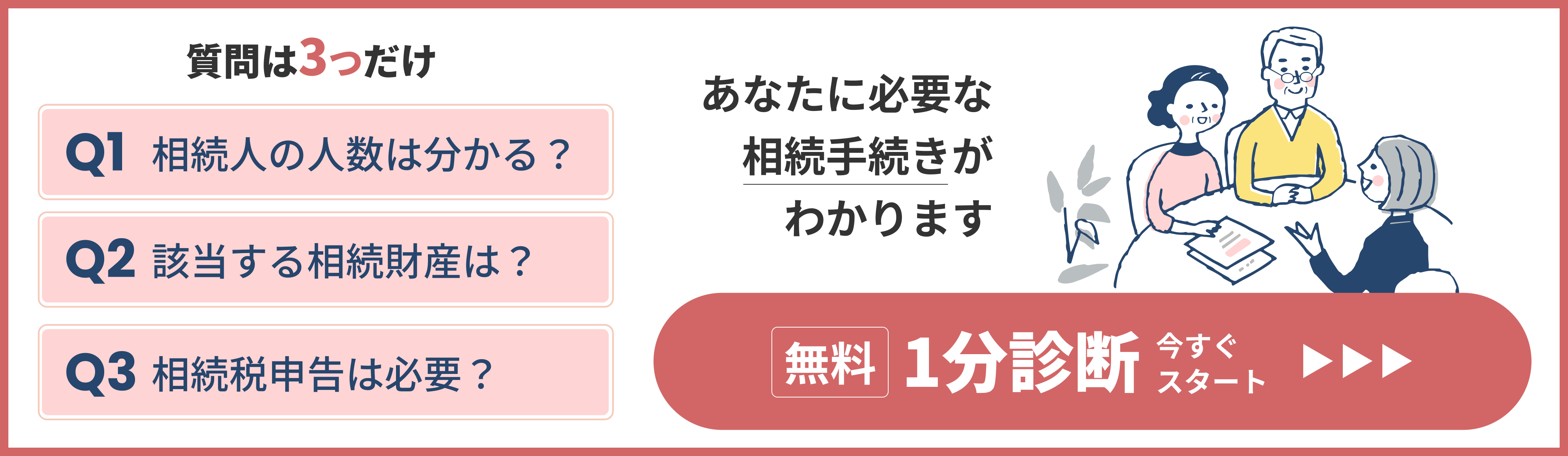
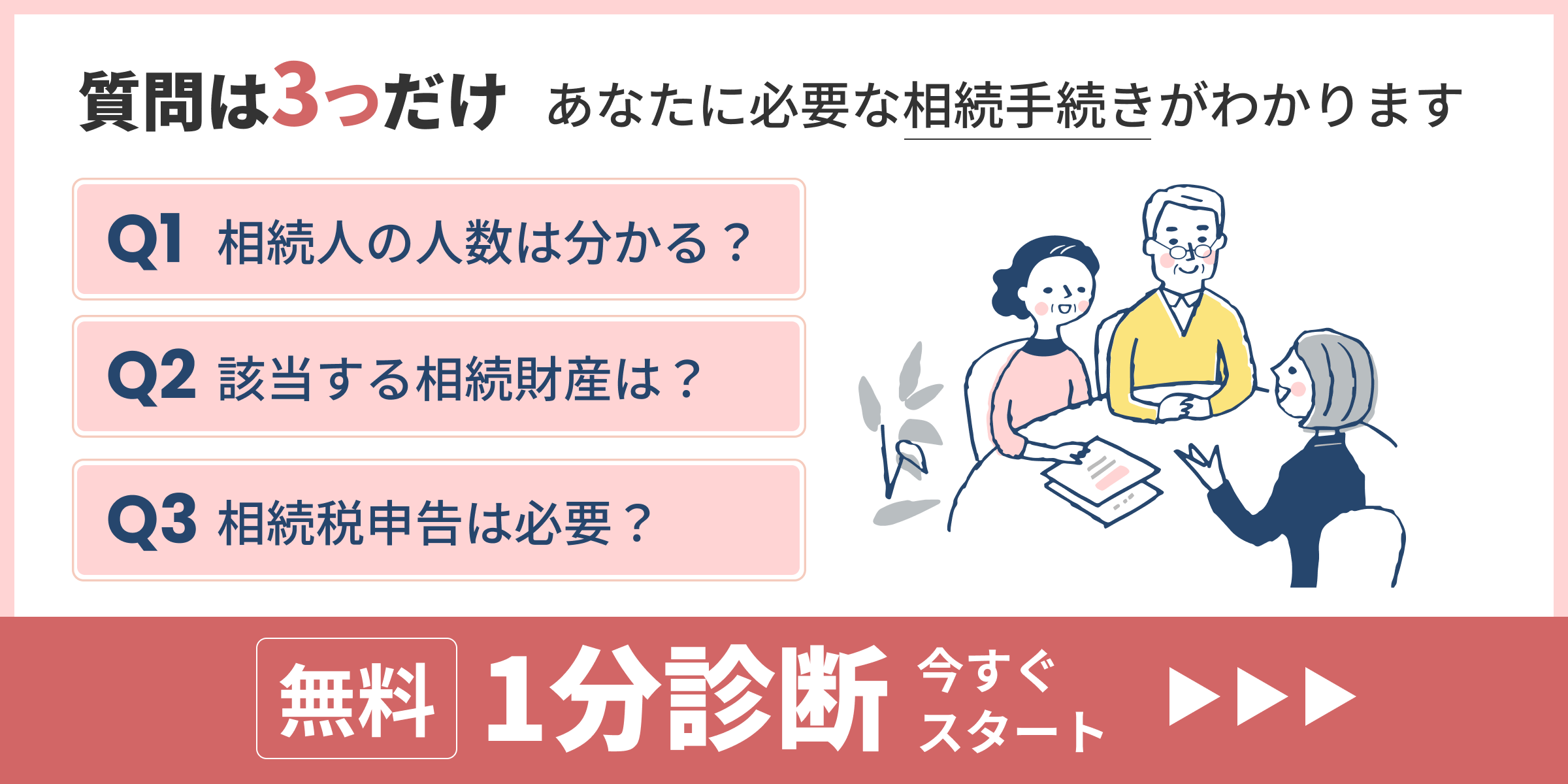
相続税の主な特例
相続税の申告を行うことによって、うけることができる特例がいくつかあります。代表的なものとして小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減、事業承継税制があげられます
①小規模宅地の特例
被相続人又は被相続人と生計を一つにしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
②配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者の課税価格が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
③事業承継税制
円滑化法に基づく認定の下、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、相続税の納税が猶予されます。
相続税の申告書にはマイナンバーの記載が必要
平成28年1月1日以降の相続などにより財産を取得した人が、相続税の申告書を提出する場合には、申告書にマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。被相続人のマイナンバーの記載は不要です。またマイナンバーを記載した申告書を提出する際は、税務署で本人確認(番号確認と身元確認)を行うために、申告書に記載された各相続人の本人確認の写しを添付する必要があります。e-Taxにより申告手続きを行う場合には、本人確認書類の掲示又は写しの添付は不要とされております。
「相続税申告」の際のマイナンバーの取り扱いの注意点
マイナンバーはマイナンバー法にて、収集、利用、保管、提供が制限されております。相続人等が複数人の場合、同じ書類の上に複数人の方のマイナンバーを記入することがあります。その場合の取り扱いの説明として、一人目の相続人がマイナンバーを記載した相続税の申告の書類を二人目以降の相続人に渡す行為について、国税局は下記のように記しております
相続税の申告書の作成に当たり、複数の相続人等がそれぞれのマイナンバー(個人番号)を記載するために、一の相続人等が相続税の申告書にマイナンバー(個人番号)を記載してその他の相続人等に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。
また相続税の申告書の控えの保管にあたっての注意点として
マイナンバー(個人番号)は、番号法で規定する場合を除き、他人のマイナンバー(個人番号)を収集又は保管することができないことから、他の相続人等のマイナンバー(個人番号)が記載された状態で相続税の申告書の控えを保管することはできません。したがって、相続税の申告書の控えを保管する場合は、その控えにはマイナンバー(個人番号)を記載しない(複写により控えを作成する場合は、マイナンバー(個人番号)部分が複写されないようにマスキングするなどの措置を講じる)など、マイナンバー(個人番号)の取扱いには十分ご注意ください。
と案内されております。他の相続人のマイナンバーが記載された状態での書類を保管されることのないようにご注意ください。
まとめ
こちらの記事では、相続税や関連する基本的な用語について取り上げさせていただきました。相続が発生した際に納税が必要かどうかはとても気になる点になると思います。ご自身のみで判断するのは難しいと思いますので、早めに専門家に相談し、相続税の申告が必要であれば必ず税理士にお願いされるのがよいでしょう。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。