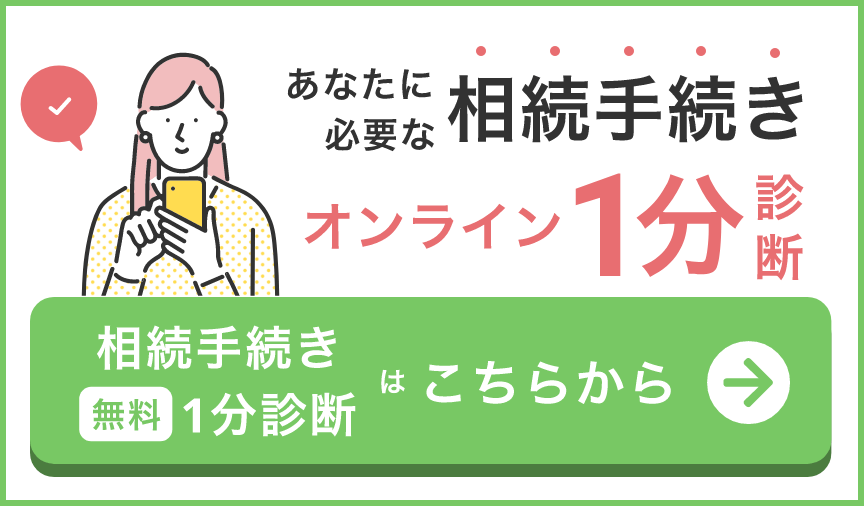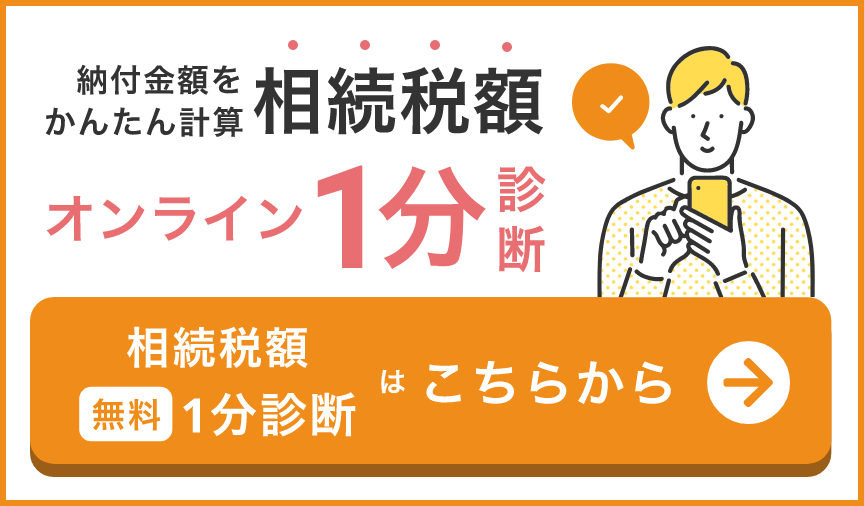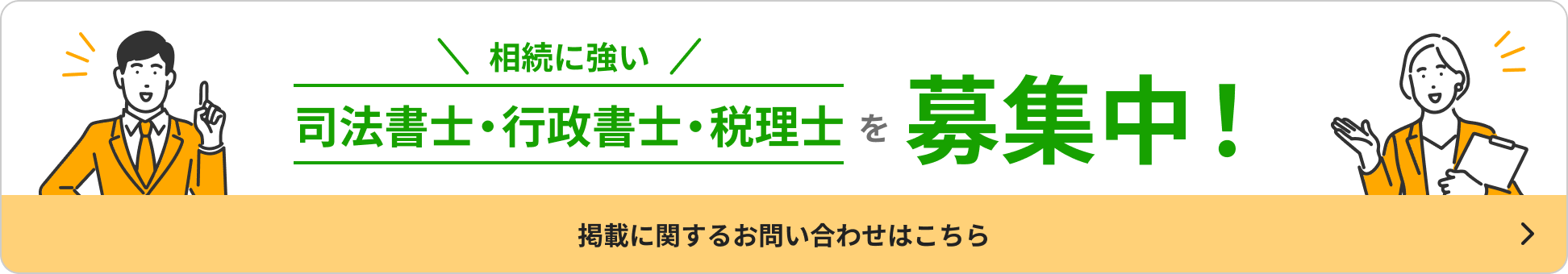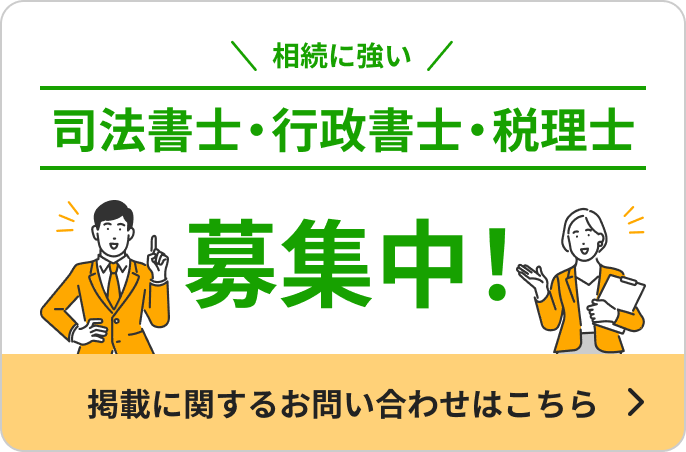相続した不動産の名義変更をしないと思わぬトラブルに!|相続登記に必要な書類や手続きの方法

相続した財産の中に不動産が含まれているときには、不動産の名義変更(相続登記)をする必要があります。相続登記には以前は期限がなかったため、手続きをしないまま放置しているようなケースもありますが、デメリットが少なくありません。
この記事では、相続登記をしなかったときのデメリット、相続登記に必要な書類、相続登記の仕方に加え、相続した不動産を売却したいときの注意点についてもご紹介します。


目次
相続財産に不動産が含まれているときのトラブル

被相続人(亡くなった人)から相続する財産に、不動産が含まれているときには、「相続登記」の手続きをします。相続登記とは、相続人の名前に不動産の名義変更をすることです。実はこの相続登記には、期限がありませんでした。そのため、相続登記をしないままの放置されているケースが存在しました。2024年4月に相続登記が義務化されましたが、相続登記をしないでいるとさまざまなトラブルが起こる恐れがあります。以下に解説していきます。
なお、相続登記の義務化の詳細は「【令和6年4月1日から施行】相続登記の義務化で違反の場合は罰則!必須知識をまとめて解説」を参照してください。
第三者に自分の所有権を証明できない
第三者に所有権を証明できないということは、売却をしたり、不動産を担保にしてお金を借りたりすることができないということです。今現在その予定がなくとも、今後何があるかはわかりませんので、必要になったときに困らないようにしましょう。
相続人が亡くなると、さらに手続きが面倒になる
相続登記をせずに、相続人A、B、Cの3名が共同相続人の状態になっていたとします。この状態でAが亡くなり、Aに配偶者と子2人の3人の相続人がいたとすると、Aに代わってこの3人に相続する権利が発生します。
相続する人数が増えるということは、揉めごとも増える可能性があります。また、その段階で登記をすることに決めても、手続きが複雑になってしまいます。
口頭での合意は、反故にされる可能性がある
兄弟が相続人であるときに、親と同居していた子が家を相続するケースは少なくありません。
相続が発生した段階で、ほかの相続人も同意しているからと相続登記をしないでいると数年後にお金に困ったり、独身だった兄弟が結婚したことで配偶者ができたりといったタイミングで、後から所有権を主張される可能性もあります。
さらに、金銭的に困っているだけでなく、財産を差し押さえられてしまうような状況になると、相続登記をしていない不動産の一部はその兄弟の財産ということになるため、差し押さえの可能性もあります。
実際に相続している人以外に固定資産税の納付書が送られてくる可能性がある
「固定資産税」が課税されるのは、1月1日の時点で「固定資産税課税台帳」に名前がある人です。相続登記をせずに共同名義になっているときには、全員に支払い義務があります。さらに全員に納付書が送られてくるわけではありません。市区町村にもよりますが、実際に相続したかどうかに関係なく、固定資産税課税台帳の先頭に名前がある人に送付されることがあります。固定資産税の納付でトラブルにならないためにも早めに相続登記をしましょう。
罰金の対象になる場合がある
令和6年4月1日より相続登記は義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に行わなければなりません。正当な理由なく怠ったときは、過料の対象になる場合があります。
相続した不動産の名義変更に必要な書類や手続きの方法
先述のようなトラブルにならないよう不動産を相続した場合の名義変更である相続登記を忘れずにおこないましょう。
ここからは、相続登記の具体的な手順について紹介していきます。
1:登記事項証明書(登記簿謄本)の取得

相続財産に不動産が含まれていることがわかったら、その不動産の正確な情報を知るために登記事項証明書を請求します。
登記事項証明書は、以前は登記簿謄本と呼ばれていました。これは、登記簿の謄本(コピー)という意味です。しかし、現在、登記簿はコンピューター化されており、コピーではなくデータを出力したものが交付されるため、登記事項証明書と呼ばれています。
不動産の登記事項証明書に記載されているのは、土地の持ち主や抵当権などの情報です。登記簿証明書には「地番」という住所が記載されています。
地番は普段使用している住所と異なるケースがありますが、これは都市部などで同じ地番に複数の建物があるなど地番だけでは管理しきれなくなったため「住居表示に関する法律」によって「住居表示(一般的に住所とよんでいるもの)」を割り当てた結果です。
登記事項証明書は、法務局で取得できます。
取得の方法は、
- 窓口で交付請求
- 郵送で交付請求
- オンラインで交付請求
の3つです。
請求の際は交付請求書に、土地の場合は「所在と地番」、建物の場合は「所在地番と家屋番号」を記入して提出します。これらは、権利証や固定資産税の納付通知書で確認可能です。
手数料は請求の仕方によって次のようになります。
- 窓口 600円
- オンラインで請求して郵送で受け取る 500円
- オンライン請求して窓口で受け取る 480円
手数料の支払い方法は窓口、または郵送のときには「登記印紙」、オンラインではインターネットバンキングやPay-easyに対応したATMなどです。
登記印紙は、法務局以外にも一部の郵便局で購入できます。
権利証があれば、登記事項証明書は必要ないと思う人もいるかもしれませんが、
- 前回の相続で相続登記されていなかった
- 被相続人の不動産だと思っていたのに、別の人の名義で登記されていた
といったトラブルもあるので、必ず確認しましょう。
前回の相続で相続登記がされていなかったとき
登記事項証明書を取得した結果、前の相続で相続登記がされていなかったときには、数次相続としての手続きの必要があります。
数次相続とは
亡くなった人の手続きがなされる前に、相続人が死亡してしまうというように相続が相次ぐことを数次相続といいます。なお、最初の相続を1次相続、次の相続を2次相続といいます。他の相続人が亡くなれば、3次相続、4次相続と続くことになります。
中間の相続人がひとりのケース
中間の相続人がひとりとは、例えば、祖父から子、子から孫というように相続されているケースです。
このようなケースで、祖父から子の相続で相続登記がされていなかったのであれば、子から孫への相続が発生したときの相続登記は祖父から孫への名義変更になりますが、名義変更は1度で済みます。
中間の相続人が複数のケース
中間の相続人が複数のケースとは、例えば、祖父から子AとBに相続された土地の登記がされていない状態で、子AからAの子、子BからBの子と、さらにそれぞれの子に相続するケースです。
このようなときには、
- 祖父から子A、Bへの相続登記
- 子Aからその子への持分全部移転登記
- 子Bからその子への持分全部移転登記
といように3回の登記が必要になります。3回登記をするので、当然費用も3回分かかります。
今回の例では非常に簡単にしていますが、実際には相続人の数はさらに多くなることもあります。また、必要な書類も増え、集めるのも難しくなります。
数次相続をしなければならないときには、専門家への依頼も検討することをおすすめします。
2:遺産分割協議
遺言書がなく、相続人が複数いるときには、必ず「遺産分割協議」をおこないます。遺産分割協議では、不動産に限らずすべての財産について「誰が何を相続するのか」について話し合い、さらにその結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書については「遺産分割協議書とは?作成の目的から書き方、必要書類までを全解説【行政書士監修】」で詳しく解説しています。
3:必要な書類を集める

相続登記で準備する書類は主に以下のようなものです。
- 固定資産評価証明書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 相続人の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
固定資産評価証明書がなぜ必要なの?と疑問に思う方もいるでしょう。
この証明書には土地の所有者や面積などのほか、固定資産税額と課税評価額などが記載されています。相続登記をする際には相続する不動産の評価額を元に登録免許税が課されるため、その計算をするために必要になるのです。
取得できるのは、23区内の不動産は都税事務所、それ以外は主に市町村の役場です。手数料は市区町村によって異なりますが、同じ区内であれば証明書1枚につき400円、2件以上申請する場合の2枚目以100円になります。(評価証明書は土地評価証明書と家屋評価証明書と分かれています。そのため土地と家屋の評価証明書が必要な場合、手数料は2枚分となります。)
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
戸籍は、結婚や本籍地の移動をすると新しく作成されます。「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」とは、これらをすべて揃えるということです。被相続人の最後の本籍地からさかのぼって請求します。さかのぼって取得する理由は、養子に出した子や認知した子が過去にいるとその子にも相続権があるので、すでにわかっている相続人以外にはいないことを確認するためです。
詳しい取得の方法は、相続の戸籍謄本に関する記事を参照してください。
被相続人の住民票の除票/相続人の住民票
住民票の除票とは、亡くなった人や転出された人の住民票のことです。住民票と同じ方法で取得できます。市区町村の窓口や郵送のほか、コンビニでも交付可能です。
相続人の戸籍謄本
戸籍謄本は相続人の本籍地の役場で取得できます。窓口だけでなく、郵送でも請求可能です。戸籍は現在、ほとんどの市区町村がコンピューター化されているため、戸籍謄本は「全部事項証明書」と呼ばれています。
相続人の印鑑証明書
印鑑証明書とは、お住いの市区町村に登録している印鑑(実印)を証明するものです。そのため、印鑑登録をしていないと交付できないので、していない人は、印鑑登録を先におこないます。
詳しくは印鑑証明書に関する記事を参照してください。
遺産分割協議で相続登記するケース
遺産分割協議によって相続する人が決まったケースでは遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果をまとめた書面です。遺産分割協議書に実印が押印されているため、効力を発揮するために、相続人全員の印鑑証明書の添付が必要になります。遺言で相続するケース
遺言書で法定相続人(民法で定められた相続権のある人)に相続させるケースでは、遺言書が必要です。自筆証書遺言であれば検認も必要です。
遺言書で相続するときには、ほかに相続人がいるかどうかは関係ありませんので、被相続人の戸籍は亡くなったときのものだけを提出します。
法定相続分の割合で複数人で相続するケース
法定相続人全員の名義で法定相続分の割合で相続するケースでは、以下の書類が必要です。
- 固定資産評価証明書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
不動産を含む相続では法定相続分の割合通りに財産を分けるのが難しくなります。ですから、以下のような方法で共有または分割することになります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
不動産の分け方については「【不動産の相続手続き】遺産分割方法、名義変更の相続登記や費用、相続税をわかりやすく解説」で解説しています。
4:登記申請書の作成
相続登記は、法務局での手続きとしては「所有権移転登記」です。
所有権移転登記のための登記申請書は、法務局の窓口だけでなく、法務局のホームページからダウンロードができます。相続の仕方によって書式や注意点が異なるので注意が必要です。
6:登録免許税
相続登記には登録免許税の納付が必要です。登録免許税とは不動産登記のために支払う税金で、登記する不動産の課税価格によって決まります。
計算式は次の通りです。
税率は法定相続人が所有権を移転するときの数値になります。第三者が遺言によって贈られるときや贈与では2%です。ただし、法定相続人が遺言によって相続するときには相続と同じ0.4%になります。
登録免許税の支払いは、原則として銀行など金融機関からの振り込みです。その納付に係る領収証書を当該登記の申請書に貼り付けて法務局に提出することになります。3万円以下のときは収入印紙でも支払うことができます。
7:法務局で手続き
登記申請書と添付書類が揃ったら、登記をする不動産の住所地を管轄する法務局で手続きをします。相続人の住所地や任意の法務局では手続きできませんので、注意してください。
法務局の窓口は、平日の17時00分まで申請を受け付けています。土・日・祝日・年末年始はやっていないため、平日に仕事をしている方や自分自身で出向くのが難しい場合などは、専門家に依頼することができます。
8:登記情報識別通知書を受け取る
登記名義人となった申請人に登記情報識別通知書が届けば、登記は完了です。紛失しても再発行はしてもらえませんのでご注意ください。
登記完了後、所有権の証明が必要なときには、法務局で登記事項証明書を交付してもらいます。
不動産を相続したときの税金の注意点
不動産を含め遺産を相続するときに課税されるのは相続税です。
相続税の計算方法については「相続税の基礎知識|相続税の対象になる財産と計算方法、控除額、申告と納税の仕方【税理士監修】」を参照してください。
不動産を購入などで取得したときに課税される税金として知られているのは不動産取得税ですが、相続による取得では不動産取得税は課税されません。しかし、遺贈や死因贈与では課税されることがあります。
遺贈と死因贈与の違い
遺贈とは遺言者が遺言書の中で特定の人に財産を渡すと記したもので、いわば一方的なものです。しかし、死因贈与は、贈与者(財産を渡す人)と受贈者(財産を受け取る人)の間で贈与者の生前に「死亡した時点で財産を渡す」という契約をおこない、贈与者が亡くなったことで契約書に記載された財産が贈与されるため双方の合意があります。この点が遺贈と死因贈与の違いです。
相続した不動産を売却したいときの注意点

遠方にある家屋や利用しない農地などを相続したときには、相続した不動産を売却したいケースも多いのではないでしょうか。そのようなときには、売却するタイミングによっては損をしてしまうことがあります。
そこで、取得費加算の特例が活用できるか確認をしてみましょう。取得費加算の特例は、相続で取得した不動産を売却するときの特例です。不動産を売却したときには譲渡所得税が課税されますが、不動産の取得費を課税される金額から差し引くことができます。
取得費加算の特例は相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却したときには、取得費に一定額の相続税を含めることができるというものです。
しかし、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例との併用はできないなど注意点があるので、不動産を売却したいと考えている方は事前に入念に検討しましょう。
専門家に相談した方がいいケース
相続登記は、相続人自身がおこなうこともできますが、司法書士に依頼する人も多いようです。
以下のようなケースでは専門家への依頼を検討してください。
- 時間がない
- 不動産の住所地が遠方である
- 遺産分割協議がまとまらない
- 売却までまとめて依頼したい
相続登記を司法書士に依頼したときの相場は約8~15万円です。
不動産の評価額が高額であったり、遺産分割協議書の作成や不動産の調査も含めて依頼をしたりすると料金はこれよりも高くなります。依頼料に加えて、窓口へ出向いたときなどには、交通費の実費や日当が別途発生することもありますので、料金の比較をするときには、これらも含めて考えましょう。
▼あなたに必要な相続手続き1分で診断できます。▼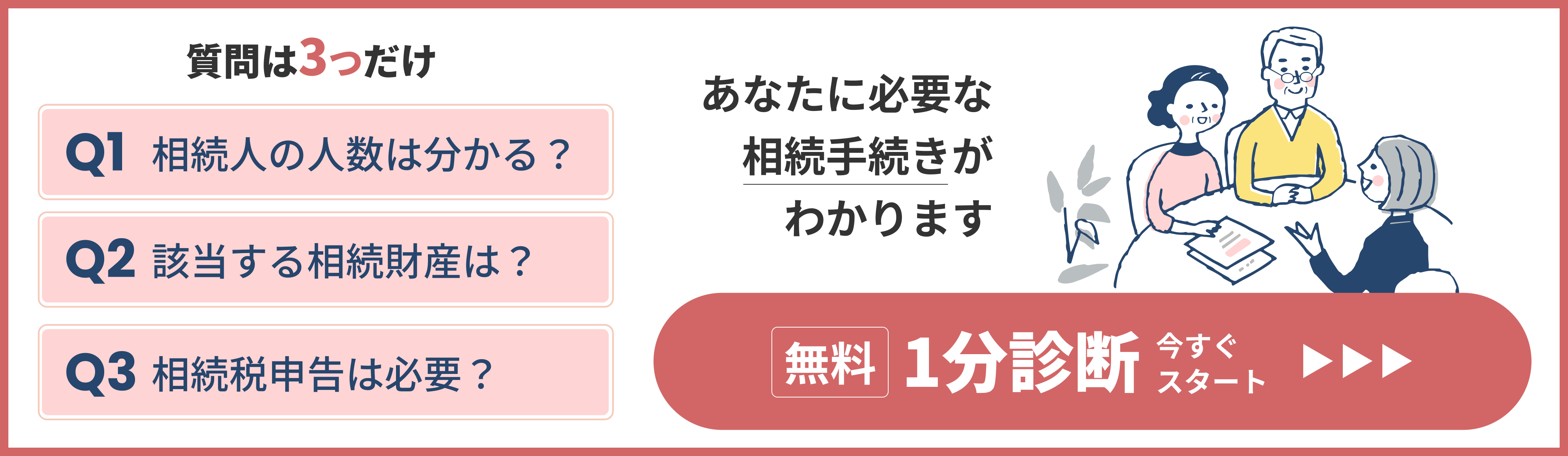
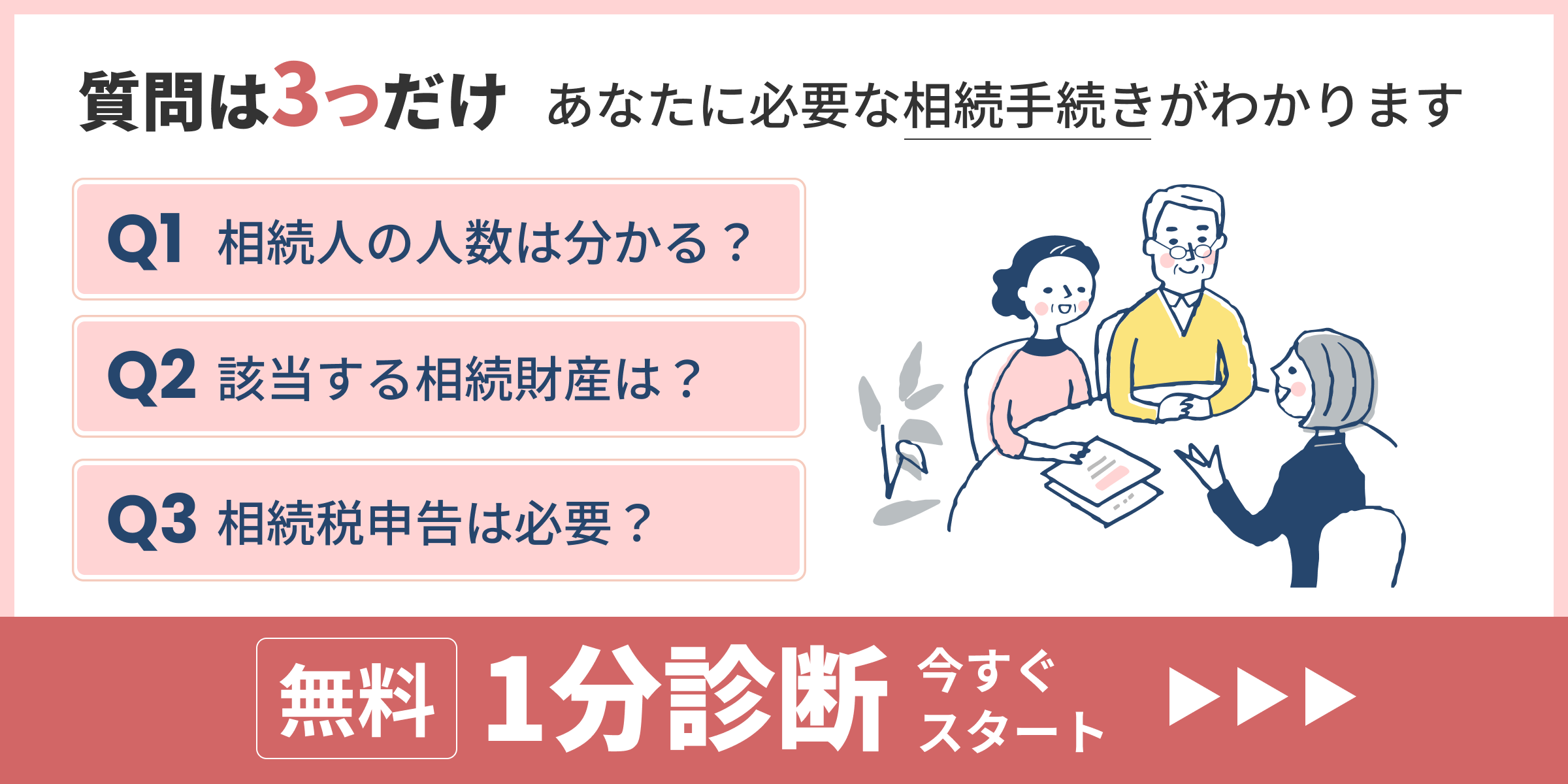
相続登記に関するよくある疑問
相続登記に関するよくある疑問とその答えをご紹介します。
Q:相続登記はいつまでにすればいいのですか?
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に行わなければなりません。正当な理由なく怠ったときは、過料の対象になる場合があります。
Q:登記事項証明書は不動産の住所を管轄する法務局に行くのですか?
登記事項証明書はコンピュータ化されているので、最寄りの法務局やオンラインでも請求できます。
Q:土地を相続しました。ほかに兄弟もおらず、私の子もひとりです。相続人同士でもめることもないので、所有権の移転の登記をしなくてもいいのではありませんか?
将来、お子さんに複数の子ができて相続登記が必要になったときは、必要な書類が増えるため集めるのが大変です。また、所有権移転登記をしていないと売却のほか、何かあったときに、担保にして融資をうけるなどの行為もできません。また、相続登記は令和6年4月1日に義務化されたので、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に行わなければなりません。正当な理由なく怠ったときは、過料の対象になる場合があります。
Q:相続した土地の所在地が遠方なので、最寄りの法務局で登記をしてもらえますか?
登記は相続する不動産の住所地を管轄する法務局以外では、受け付けてくれません。遠方で行くのが難しいときには司法書士への依頼も検討してください
Q:父が遺言で私に不動産を残してくれました。遺贈に該当して不動産取得税もかかりますか?
遺贈で不動産取得税がかかるのは第三者のときです。法定相続人の場合は相続税がかかります(ただし計算の結果、相続税がかからない場合もありますので詳しくは相続税の計算方法を参照してください。)
まとめ
不動産を相続したときには不動産の登記(名義変更)が必要です。相続登記をしないでいると
- 第三者に自分の所有権を証明できない
- 登記しないまま相続人が亡くなると、次の相続での手続きが複雑になる
- 口頭での合意は、反故にされる可能性がある
- 固定資産税のトラブルにつながる可能性がある
- 罰金がかかる可能性がある
といったデメリットがあります。
相続登記は、必要書類を揃えて、法務局に提出をすれば相続人自身でも可能ですが、集める書類が多くて大変なときや管轄の法務局へ出向くのが難しいときには専門家への依頼も検討しましょう。
不動産は、預貯金などの財産に比べ手続きの点では複雑な財産です。相続で家族が争うのを避けるためには、生前によく話し合っておいたり、不動産を所有している方が遺言書を残しておくのも一つの方法です。いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、相続手続きでお困りことがある方はお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。


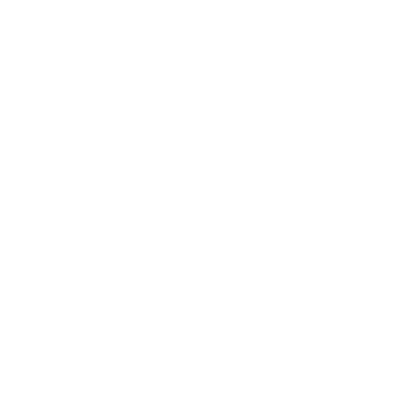
 Webで無料相談はこちら
Webで無料相談はこちら