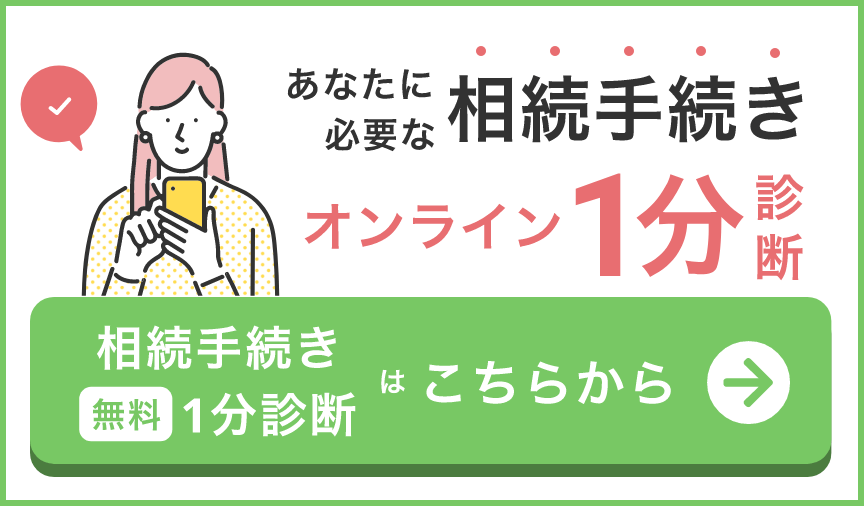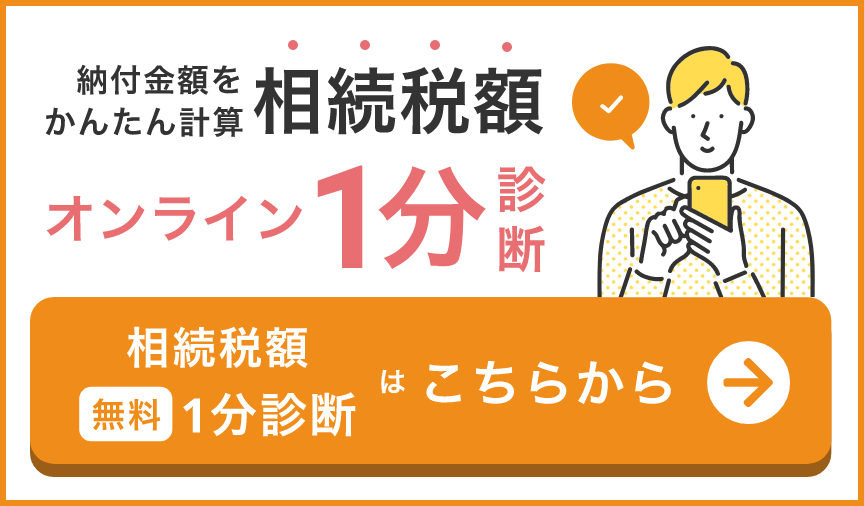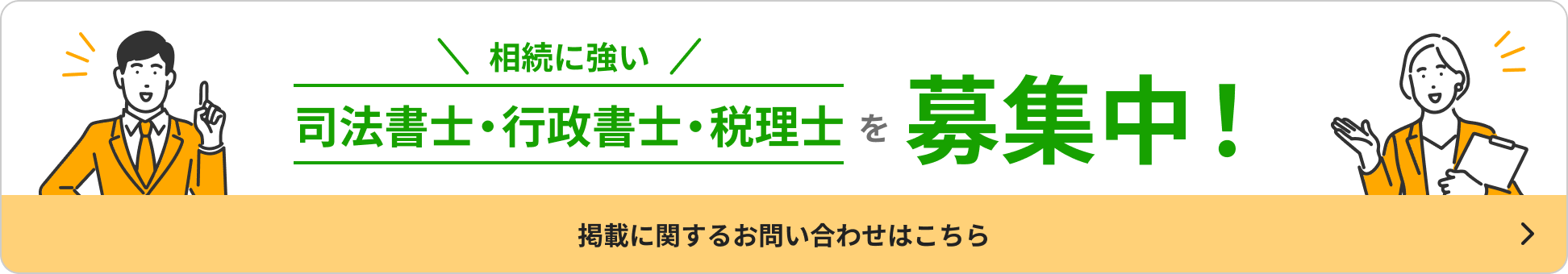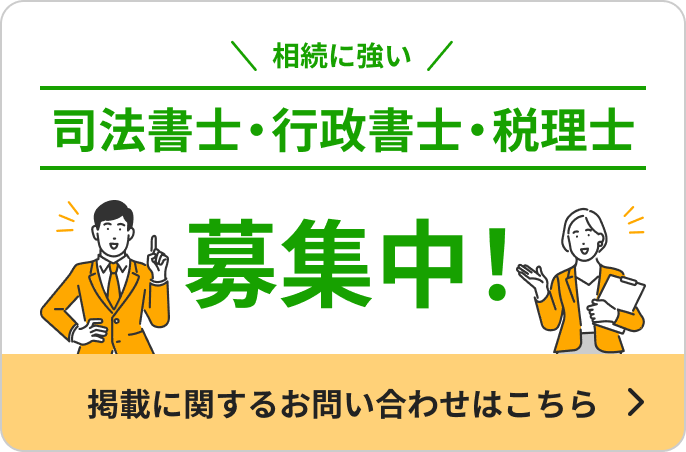相続税の非課税枠|相続税の基礎控除額と非課税財産

相続税には税負担を軽減するために非課税枠というものが設けられており、それぞれに適用するための条件が設けられています。相続財産と法定相続人の人数によって変わる基礎控除額のほか、さまざまな非課税枠があります。
この記事では、相続税の非課税枠を利用してできるだけ相続税の負担が減らせるよう、相続税の申告要否の判断のしかたや、非課税枠が設定されている財産の種類と適用条件、相続税が非課税となる財産の種類などをご紹介します。


非課税枠・非課税財産を理解して相続税を抑えよう

2015年(平成27年)の民法改正により相続税の課税対象となる人が増えていますが、相続税の計算は煩雑であるため、自分で相続税の申告を行おうとすると税負担が軽くなる非課税枠を見落としてしまう可能性があります。
相続税の負担をできるだけ軽くするには、どのような財産に非課税枠が設定されているか、どのような人が利用できるのかなどを正しく理解することが大切です。
相続税の非課税枠について知ることで、相続税をかしこく計算しましょう。
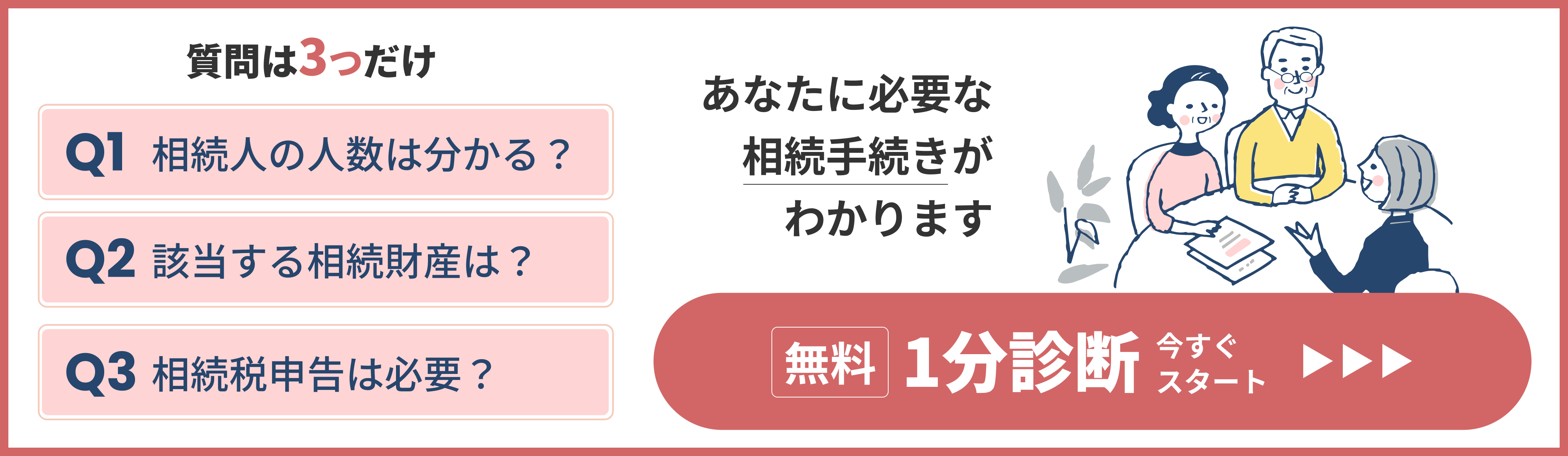
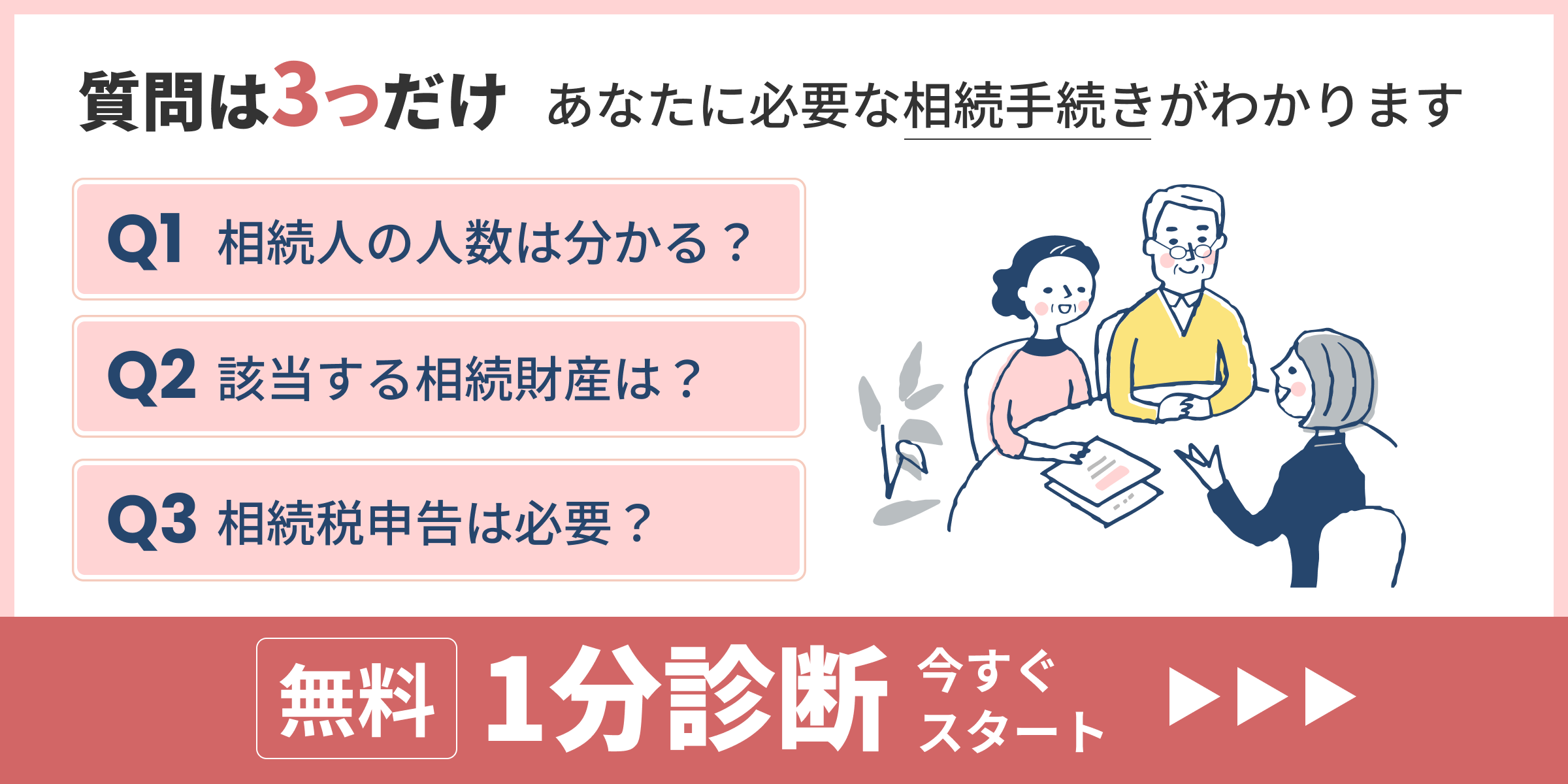
相続税の申告はいくらから必要になる?
相続税の申告要否はまず「基礎控除額」を超えるかを確認
まずはどういった場合に相続税が発生するのを確認しておきましょう。
相続税は相続する財産の総額によって申告が必要かどうかが変わり、ポイントは財産の総額が「基礎控除額」を超えるかという点です。
基礎控除とはどの相続においても一律に差し引かれる控除で、基礎控除と相続財産の関係は次のようになります。
- 相続する財産の総額>基礎控除額:相続税が課税される
- 相続する財産の総額<基礎控除額:相続税が非課税となる
相続する額が3,600万円以下なら申告不要
相続税計算における基礎控除額は以下の計算式で算出されます。
相続が発生する場合、相続人が最低1名以上いることになるため、基礎控除額の最低金額は3,600万円となります。
したがって法定相続人の人数にかかわらず、相続財産の総額が3,600万円以下の場合は相続税は発生せず、税務署への相続税の申告も必要ありません。
3,600万円を超える場合は法定相続人の人数によって変動
相続財産が3,600万円を超える場合には、法定相続人の数に基づいて基礎控除額を算出し、相続税申告の要否を確認しましょう。
基礎控除額を「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の式で算出し、基礎控除額が相続財産の総額より大きければ相続税は申告不要ですが、基礎控除額が相続財産の総額より小さければ相続税の申告が必要となります。
たとえば法定相続人が5人、相続財産の総額が5,000万円の場合、相続税の申告要否は以下のように判断します。
- 基礎控除額:3,000万円 + 5人 × 600万円 = 6,000万円
- 基礎控除額:6,000万円>相続財産の総額:5,000万円 ⇒ 基礎控除額の方が大きいため、相続税の申告は不要
相続税が発生するかは基礎控除額によって変わってきますが、基礎控除額は増やすことができるのでしょうか。
基礎控除額は法定相続人の数が増えるにつれ増えるため、法定相続人を増やすことができれば基礎控除額も増やすことができます。
相続税対策として知られている孫を養子にする(孫養子)という方法は、法定相続人を増やすことも目的のひとつなのです。
法定相続人に算入できる養子の数には制限があり、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと定められています。
ただし、養子縁組が節税目的で行われたと判断された場合は、その養子は法定相続人とは認められません。
また、孫養子については相続税の負担の調整を図る目的で相続税の2割加算の対象となります。(孫養子が代襲相続人にも該当する場合は2割加算の対象外)
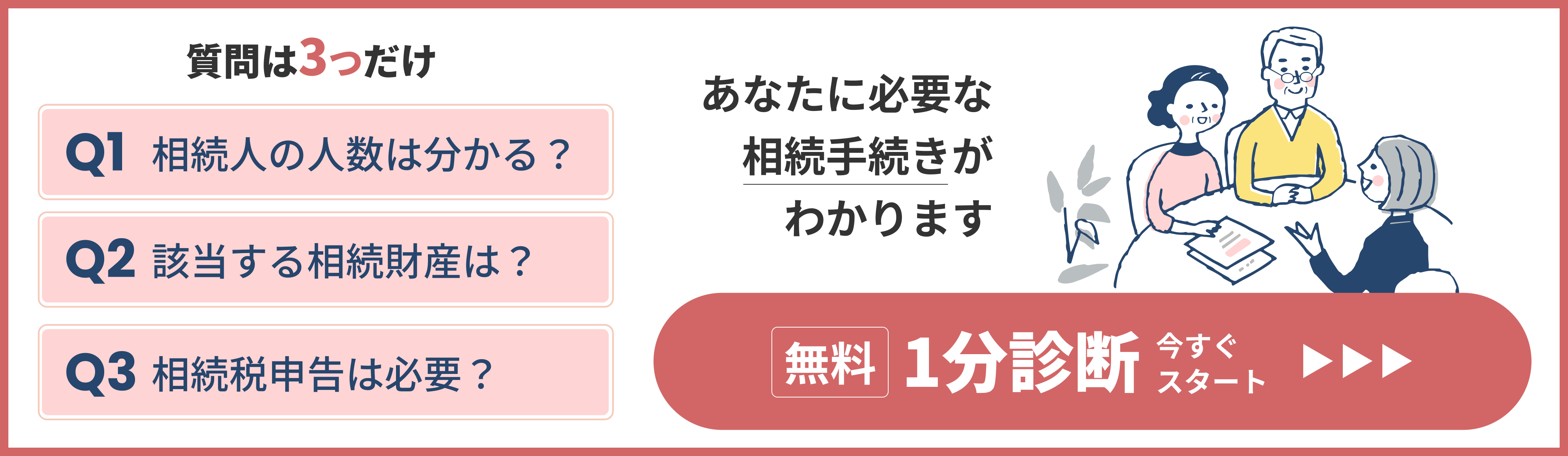
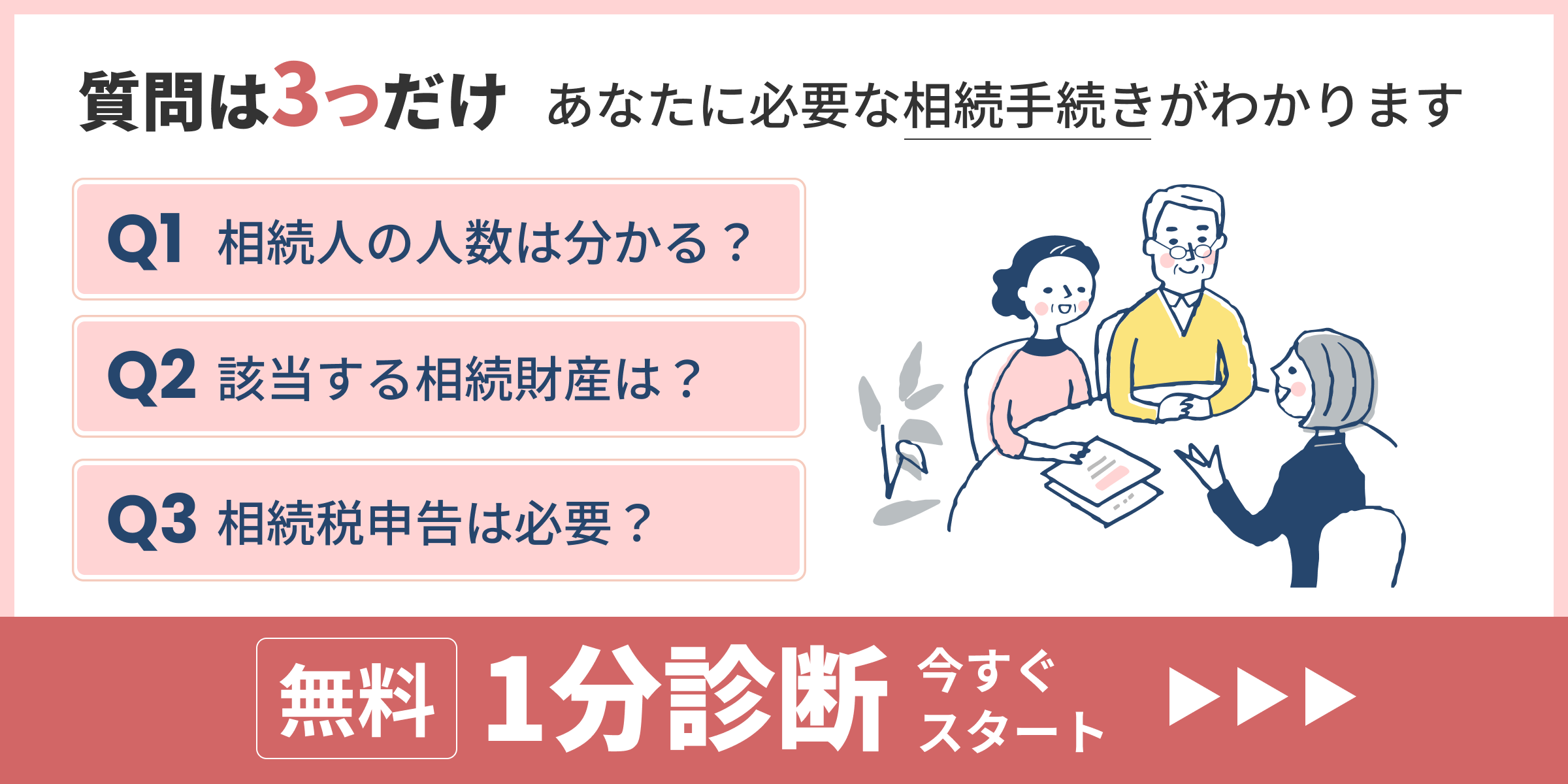
非課税枠が用意されている財産・制度とは?

1. 生命保険金
被相続人が亡くなったことにより相続人が取得した生命保険金(損害保険金も同様)については非課税枠が設けられています。
非課税となるのは500万円×法定相続人の数で、非課税枠を超えた保険金のみ課税対象となります。たとえば法定相続人が3人の場合は500万円×3人で1,500万円が非課税枠となります。
生命保険金は相続税の非課税枠が用意されているほかにも、原則として遺留分の対象とならないなどのメリットがあるため、生前の相続対策としても有効といえます。
ただし、名義保険(契約者と保険料負担者が異なる保険契約)の場合は生命保険金であっても非課税枠の対象にならないこともあるので注意が必要です。
相続税対策として生命保険を利用したい場合、名義保険と判断されてしまうと非課税枠が利用できない場合があります。
名義保険とは契約者と保険料負担者が異なる保険契約のことで、被保険者が誰なのかによって非課税枠が利用できるかどうか決まります。
非課税枠が利用できるケース
- 契約者が相続人で、保険料負担者が被相続人
- 被保険者が被相続人
非課税枠が利用できないケース
- 契約者が相続人で、保険料負担者が被相続人
- 被保険者が相続人
2. 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
被相続人の配偶者には控除に関して特例が設けられており、控除金額が他の控除よりも大きいのが特徴です。
被相続人の配偶者の控除額は以下の通りです。
1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きいほう
配偶者控除が適用されるためには条件が2つあります。
- 相続税の申告
配偶者控除を利用し被相続人の配偶者の相続税額が0になった場合でも、相続税の申告書を作成のうえ税務署へ提出する必要があります。 - 申告期限までに申告を済ませる
相続税の申告期限は「被相続人が死亡したこと知った日の翌日から10ヵ月」とされており、配偶者控除を利用する場合にはこの10ヵ月の期限内に相続税の申告を終わらせる必要があります。
なお、申告期限内に遺産分割協議がまとまらず相続税の申告が難しそうな場合は、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込み書」を添付のうえ提出すれば、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまった場合に限り配偶者控除の適用が受けられます。
配偶者控除は控除金額が大きいため、配偶者の相続割合を大きくすることで相続税額を抑えることはできますが、配偶者が亡くなった際に二次相続で支払う相続税が高額になることもあるため、二次相続を含め事前にシミュレーションなどを行った方がよいでしょう。
3. 死亡退職金
死亡退職金とは、被相続人が会社に在職中であった場合、被相続人が退職に際して受け取るはずだった退職金が遺族に対して支払われるというもので、死亡退職金についても相続税の非課税枠が設けられています。
死亡退職金における相続税の非課税枠は500万円×法定相続人の数となり、非課税枠を超えた死亡退職金額のみ課税対象となります。
死亡退職金が支払われるかは被相続人の勤務先の規定により異なるため、支払われないこともあります。
また、会社によっては従業員が亡くなった場合に弔慰金が支払われることがあります。
弔慰金は原則相続税の課税対象とならないものですが、金額が大きいと課税対象となる場合があり、業務上の死亡であれば普通給与の3年分、業務外の死亡では普通給与の半年分を超える部分について相続税が課税されます。
4. 小規模宅地等の特例
被相続人が所有していた土地についても、土地の用途によっては相続税の負担を軽減する特例が利用できることがあり、これを「小規模宅地等の特例」といいます。
相続税を算出する際、土地については評価額に基づいて計算しますが、小規模宅地等の特例が適用されるとその土地の評価額が最大で80%減額されます。
小規模宅地等の特例についても配偶者控除と同様、利用したい場合は相続税の発生如何を問わず相続税の申告が必須です。
特例が適用される土地の種類は自宅の土地(特定住居用)・貸付用を除く事業に使用していた土地(特定事業用)・他人に賃貸していた土地(貸付事業用)に限られ、面積の上限が設けられています。
小規模宅地等の特例の対象となる土地
| 区分 | 上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用(自宅の敷地) | 330㎡まで | ▲80% |
| 特定事業用(商売用の土地) | 400㎡まで | ▲80% |
| 貸付事業用(賃貸事業の土地) | 200㎡まで | ▲50% |
小規模宅地等の特例については減額割合が大きく、相続税の計算にも大きな影響を与えるため、適用要件が厳しく設定されています。
そのため、小規模宅地等の特例が適用できるかどうかについては専門家に相談のうえ判断を仰ぐべきでしょう。
また、土地の相続においては評価額の算出が必須となりますが、評価額の算出は専門家でも人によって評価結果に違いが出るとも言われているほど難しいものであるため、土地の相続に関しては専門家を頼るほうが安心でしょう。
5. 未成年者控除
相続人が未成年の場合は未成年者控除が利用できます。
未成年者控除は、未成年の相続人が満18歳になるまでの年数1年あたり10万円で計算した額を相続税額から差し引く制度で、1年未満の期間については切り上げて1年とみなして計算します。
たとえば相続人が満15歳であった場合は、10万円 × 5年 = 50万円が控除できる金額となります。
また、未成年者の相続税額より差し引かれる金額の方が上回った場合、扶養義務者の相続税からも差し引くことが可能です。
未成年者控除を利用して相続税額が0となることがわかった場合は、相続税の申告は不要となります。
6. 障害者控除
障害者控除は相続人が障害者の場合に適用される控除です。
相続人が満85歳になるまでの年数1年あたり10万円(特別障害場合は年20万円)で計算した額を相続税額から差し引くことができ、1年未満の期間があるときは切り上げて1年とみなします。
障害者控除についても未成年者控除と同じように、障害者の相続税額よりも控除金額の方が大きい場合は扶養義務者の相続税からも控除されるのが特徴で、障害者控除を適用して相続税額が0円になった場合の相続税の申告は不要です。
7. 贈与税額控除
被相続人から生前贈与を受けて贈与税を納めている場合、贈与税額控除が適用されることがあります。
相続税は相続開始時の財産額に基づいて計算されますが、相続開始3年前までに被相続人から贈与された財産についても相続財産に含める必要があり、贈与税を支払っていた場合は二重課税となってしまいます。
相続時精算課税制度の適用を受けていた場合についても、制度適用時以降に贈与された財産がすべて相続財産に含まれてしまうため、こちらも税金が二重に課税されてしまうこととなります。
贈与税額控除はこうした同一財産への贈与税・相続税の二重課税を防ぐために設けられており、控除されるのは相続財産に加える必要のある贈与財産に対してかかった贈与税の金額です。
贈与税額控除により相続税額が0円になった場合、相続税の申告は不要です。
なお、被相続人から贈与された財産については、贈与税が発生しない範囲での贈与であっても下の条件を満たす場合は相続財産に必ず含める必要があるため、相続税を計算する際には注意が必要です。
- 暦年贈与の場合:相続開始3年前までに贈与された財産すべて
- 相続時精算課税制度が適用されている場合:制度適用後に贈られた財産すべて
8. 相次相続控除
被相続人が亡くなる10年前までに、被相続人が別の相続(1次相続)で相続税を支払っていた場合は相次相続控除が適用されます。
1次相続(被相続人が相続税を支払った相続)における相続税額のうち、相続から経過1年につき10%の割合で減らした金額が控除金額となります。
相次相続控除が適用される要件は以下の通りです。
- 法定相続人であること
遺贈により法定相続人以外の人が財産を相続した場合、その人は控除を受けられません。
相続放棄をしたり、排除により法定相続人でなくなった場合も控除の対象外です。 - 被相続人が前回の相続で相続税を支払っていること
前回の相続で相続税額が0円であった場合は対象外です。
相続が相次ぐことで大きくなる税負担を減らすことを目的とした制度のため、そもそも相続税を支払っていない場合は控除もされません。 - 前回の相続が10年以内であること
1次相続と2次相続(今回の相続)が10年以上開いている場合は控除が受けられません。
なお、期間をカウントする際に1年未満の端数は切り捨てることができます。
9. 外国税額控除
外国税額控除とは、外国に納めた相続税額のうち、一定の要件を満たすものについて、日本で課せられる税額から控除する制度です。
外国税額控除については一般の人が適用可否を判断するのは難しいでしょうから、遺産が外国にもある場合は税理士に相談することをお勧めします。
10. 医療法人持分税額控除
相続人等が、被相続人から相続又は遺贈により医療法人の持分を取得した場合において、その医療法人が相続開始の時において認定医療法人(相続税の申告期限又は令和8年12月31日のいずれか早い日までに厚生労働大臣の認定を受けた医療法人を含みます)であり、かつ、相続人等が相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄したとき、その他一定のときは、その相続人等の相続税額から、放棄相当相続税額を控除します。
11. 農地等についての相続税の免除
農業を営んでいた被相続人(亡くなった人)等から相続や遺贈(遺言によって財産を取得させること)によって農地を取得し、その人も農業を営む場合等に、相続税の一部又は全部の納税が猶予され、さらに一定の要件を満たすと猶予中の相続税の納税が免除されるというものです。
12. 非上場株式等についての相続税の免除
事業承継税制は、事業承継にかかる相続税や贈与税の支払いを猶予する制度です。2018年には制度が改正され、要件が大幅に緩和されました。詳細については、以下の記事を参考にしてください。
13. 山林についての相続税の免除
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(立木又は土地をいいます。)を有していた一定の被相続人から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした一定の相続人(「林業経営相続人」といいます。)が、自ら山林の経営(施業又はその施業と一体として行う保護をいいます。)を行う場合には、その林業経営相続人が納付すべき相続税のうち、特例山林に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます(猶予される相続税額を「山林納税猶予税額」といいます。)。
この山林納税猶予税額は、林業経営相続人が死亡した場合にはその納税が免除されます。
詳しくは、国税庁ウェブサイト「No.4149 山林を相続した場合の納税猶予の特例」をご参照ください。
14. 医療法人の持分についての相続税の免除
相続人等が、医療法人の持分を被相続人から相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人であるときは、納付すべき相続税のうち、この特例の適用を受ける持分の価額に対応する相続税については、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「医療法人持分納税猶予税額」といいます。)。
この医療法人持分納税猶予税額は、一定の要件を満たしたときには、その全部又は一部が免除されます。
詳しくは、国税庁ウェブサイト「No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例」をご参照ください。
15. 特定の美術品についての相続税の免除
寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づきその特定美術品をその寄託先美術館の設置者に寄託していた人から相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人(「寄託相続人」といいます。)が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税の額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます(猶予される相続税の額を「美術品納税猶予額」といいます。)。
この美術品納税猶予税額は、一定の要件を満たすこととなった場合には免除されます。
詳しくは、国税庁ウェブサイト「No.4154 特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除」をご参照ください。
16. 個人の事業用資産についての相続税の免除
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を都道府県知事から受ける後継者(平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。)である相続人又は受遺者(「特例事業相続人等」といいます。)が、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた被相続人から、その事業に係る特定事業用資産の全てを平成31年1月1日から令和10年12月31日までの相続又は遺贈により取得をした場合には、その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件の下、特例事業相続人等が納付すべき相続税のうち、特例事業用資産に係る課税価格に対応する相続税の納税が猶予され、特例事業相続人等が死亡した場合等には、その全部又は一部が免除されます。
詳しくは、国税庁作成のパンフレット「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし」をご参照ください。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼相続税が非課税となる代表的な財産

相続する財産の中には相続税の課税の対象外となる財産がいくつかあります。
ここでは相続税が課税されない代表的な財産を見ていきましょう。
1. 日常礼拝をしているもの
仏壇や神棚、墓石などの日常礼拝をしているものについては相続税の課税対象外となっています。
これらの財産については、国民感情に照らし合わせて相続税を課税するのは馴染まないというのが理由です。
日常礼拝をしているものには以下のようなものが該当します。
- 墓地
- 墓石
- 仏壇
- 仏具
- 神棚
- 神体
- 神具
- 位牌
- 庭内神し など
ただし、日常礼拝をする対象となりえるものでも、場合によっては相続税の課税対象となります。
たとえば仏像について、礼拝目的ではなく投資を目的としている場合や、仏像自体が極端に高価である場合に課税対象となることがあります。
2. 寄付をした財産
相続後に寄付をした財産についても非課税となることがあります。
非課税となる条件には以下のようなものがあります。
- 相続税の申告期限までに寄付した財産であること
相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月)までに寄付をし、さらに相続税の申告まで済ませる必要があります。 - 遺言による寄付ではないこと
被相続人の遺言によっておこなわれた寄付は対象外です。相続人の意思による寄付であることが必要です。 - 寄付先が国や地方公共団体、特定の公益法人であること
寄付先はどこでもいいわけではありません。要件を満たすには寄付先が国や地方公共団体のほか、独立行政法人や社会福祉法人などの特定の公益法人である必要があります。
なお、この他にも細かい条件があるため、寄付を考えている場合は専門家に相談するのがベターです。
要件をすべて満たした場合、寄付した財産については相続税が非課税となるほか、所得税や住民税が減額されることもメリットといえるでしょう。
3. 公益事業に使われる財産
学校教育など公益目的の事業に使われることが確実な財産については非課税となります。
公益事業として認められているものの例には以下のようなものがあります。
- 学校教育や学校教育に類する教育を行う事業
- 育英事業
- 科学技術に関する知識の普及や学術の研究に関する事業
- 宗教の普及やその他教化育成に寄与する事業
その他、公益事業として認められる事業については国税庁のホームページをご確認ください。
相続して2年経過しても公益目的事業に使用されていない場合、利用実態がないとみなされて相続税の課税対象となり、さかのぼって相続税を納める必要があります。
4. 香典
香典も相続税の課税対象外となっています。
香典については遺族が葬儀の参列者からいただくものでるため、故人の財産ではありません。
故人の財産ではないということは相続財産に当たらないということであるため、相続税の課税対象にはならないのです。
所得税や贈与税についても、社会通念上相当と認められる範囲であれば香典は非課税とされています。
5. その他非課税となる財産
ここまでご紹介してきたほかにも、課税対象とならない財産には以下のようなものがあります。
通り抜け私道
不特定多数の者の通行の用に供されている私道については、その私道の価格は評価しない、つまり相続税が課税されないこととなっています。
道路の幅員の大小は関係なく、公共性があるかどうかであるかが判断基準となります。
歩道状空地
歩道状空地とは、集合住宅の建築にあたって敷地の道路沿いの一部を私道として整備したものを指します。
この歩道状空地が居住者等以外の第三者も自由に通行できるようになっている場合、通り抜け私道とみなされ相続税は課税されません。
借家権
借家権は建物の借主がもつ賃借権のことで、借家権も相続財産に含まれます。
借家権の評価が必要になるかどうかはケースによって異なります。
- 借家権が権利金等の名称で取引される慣行のある地域:評価が必要
- 借家権が権利金等の名称で取引される慣行のない地域:評価は不要
日本国内で賃借権が取引される慣行がある地域はかなり少ないため、ほとんどの場合借家権には相続税が課税されません。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権とは、被相続人の配偶者が住んでいた自宅の遺産分割が終わるまでの間、その自宅に住んでいられる権利のことで、この権利は相続税の評価対象外です。
ただし、2020年4月から開始した配偶者居住権については相続税の評価対象となります。
未支給年金
被相続人が年金受給者であった場合、死亡後に振り込まれる年金を未支給年金と呼びます。
未支給は相続税の課税対象ではなく、相続人の一時所得扱いとなり所得税の対象となります。
相続税の非課税枠に関するQ&A
Q:相続税の申告はいくらから必要?
相続する財産の総額が「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の金額に収まっていれば、相続税は発生しません。これを基礎控除額といいます。この基礎控除額を超えると相続税が課税されます。
Q:相続税の非課税枠が設定されている財産は?
相続税の非課税枠が設定されている財産には、次のようなものがあります。
- 生命保険金:500万円×法定相続人の数の金額まで控除
- 配偶者の税額軽減(配偶者控除):1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きいほうまで控除
- 死亡退職金:500万円×法定相続人の数の金額まで控除
- 小規模宅地等の特例:特定住居用・特定事業用・貸付事業用のいずれかに使用している土地の評価額を最大80%減額(面積に上限あり)
- 未成年者控除:未成年の相続人が満20歳になるまでの年数1年あたり10万円控除
- 障害者控除:障害を持つ相続人が満85歳になるまでの年数1年あたり10万円(特別障害場合は年20万円)控除
- 贈与税額控除:暦年贈与の場合は相続開始3年前までに贈与された財産にかかった贈与税分が控除され、相続時精算課税制度が適用されている場合は制度適用後に贈与された財産すべてにかかった贈与税分が控除される
- 相次相続控除:被相続人が亡くなる前10年の間に財産を相続し相続税を納税している場合、被相続人が支払った相続税額から経過1年につき10%の割合で減らした金額を控除
Q:相続税が非課税となる財産は?
相続税が非課税となる財産には、次のようなものがあります。
- 日常礼拝をしているもの
- 寄付をした財産
- 公益事業に使われる財産
- 香典
- その他(通り抜け私道、歩道状空地、借家権、未支給年金、配偶者短期居住権など)
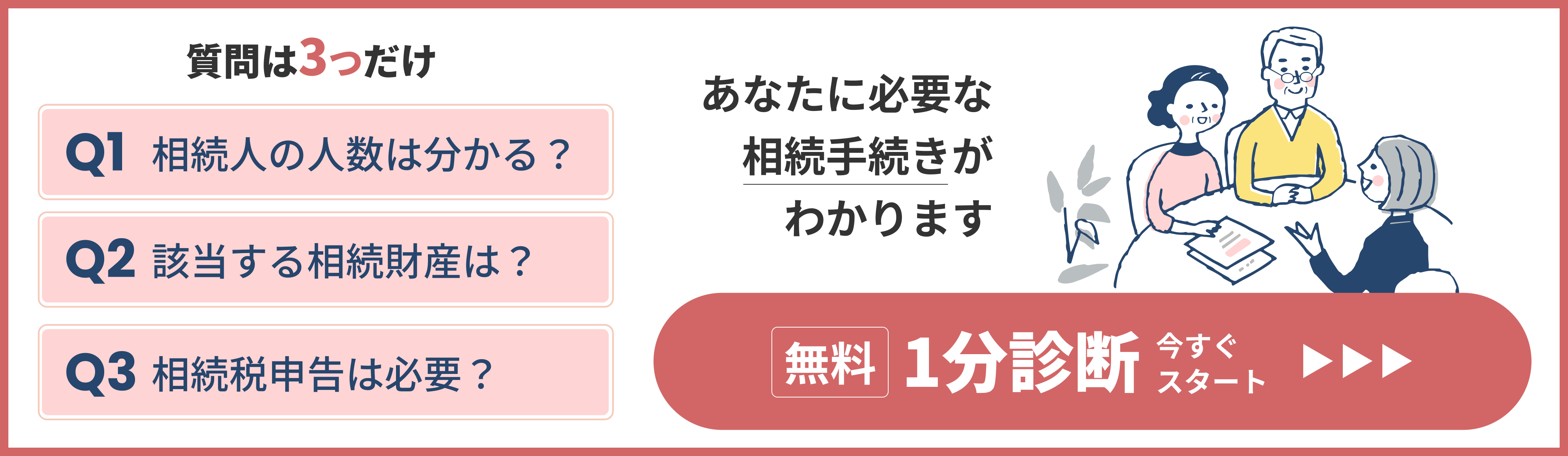
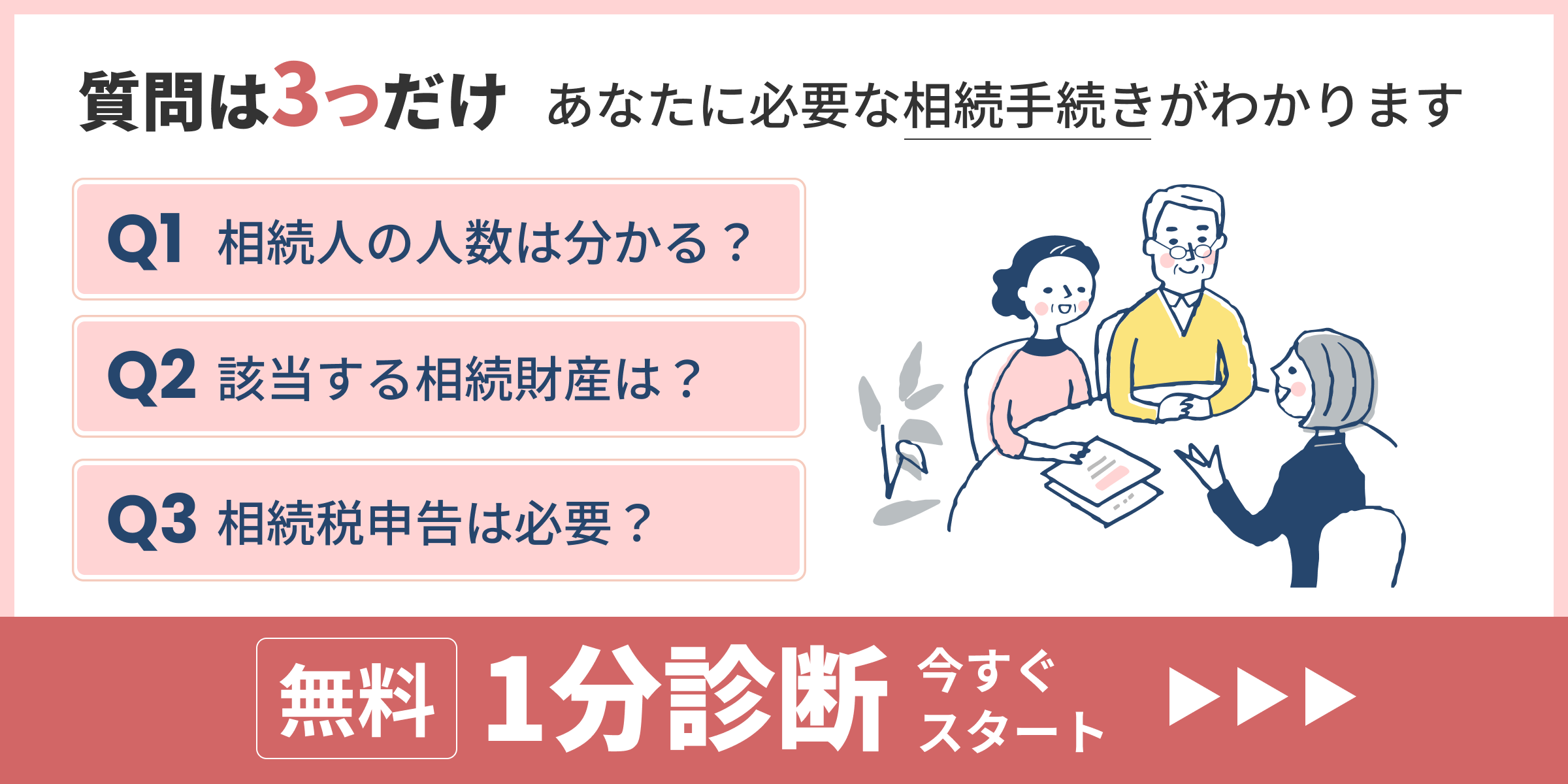
まとめ
相続税の非課税枠についてご紹介してきました。
- 非課税枠がある相続財産の種類には生命保険金、死亡退職金などがある
- 税負担を軽減する配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用することもできる
- 相続財産のうち課税対象とならないものには日常礼拝をしているもの、寄付をした財産、公共事業に使われる財産などがある
これらの制度をうまく利用することで相続税額を抑えることができるため、利用できる制度はもれなく利用したいものです。
「自分が利用できる制度が知りたい」という場合や、「専門家に相続税の計算を依頼したい」という場合には一度専門家へ相談するのがおすすめです。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、相続税の非課税枠について疑問がある方はお気軽にご相談ください。


▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。


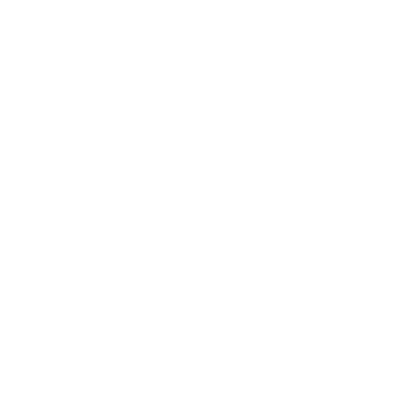
 Webで無料相談はこちら
Webで無料相談はこちら