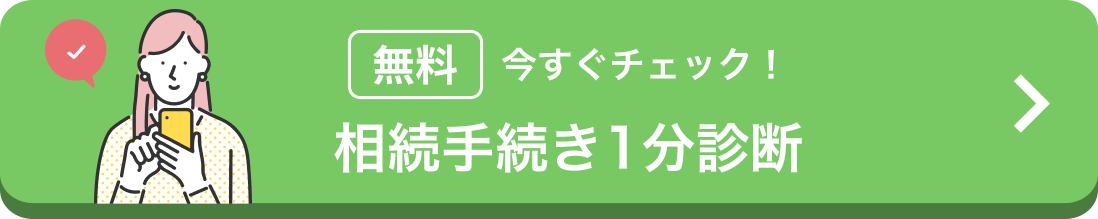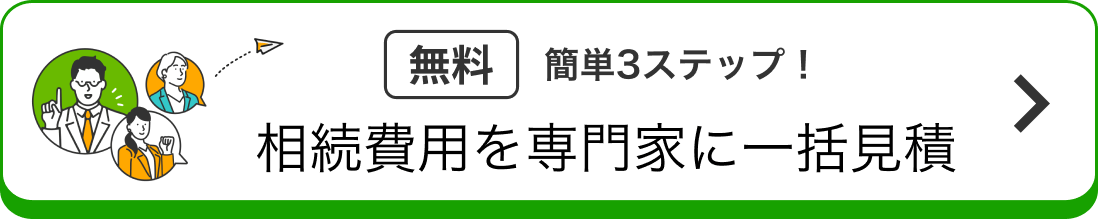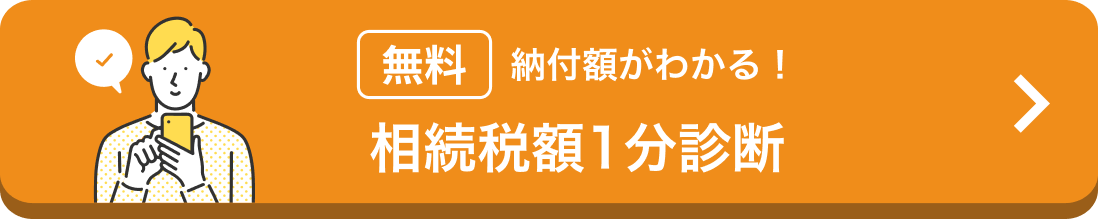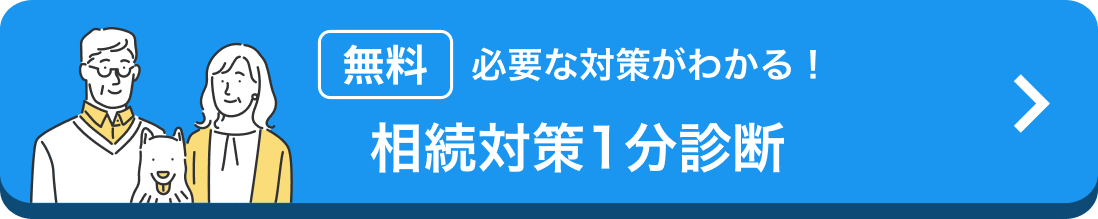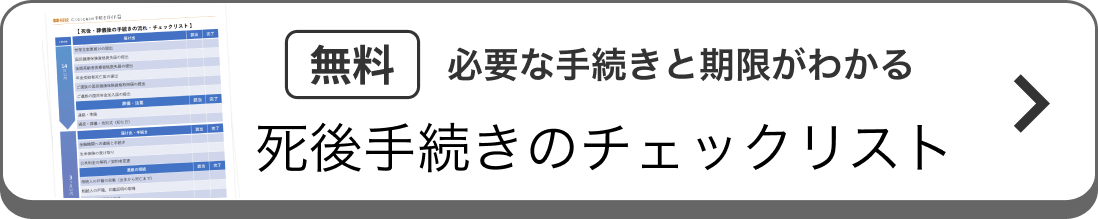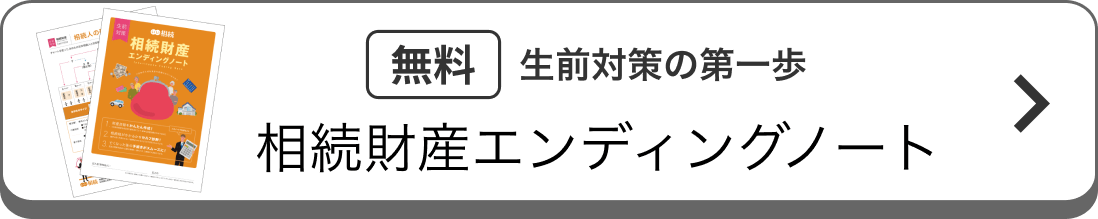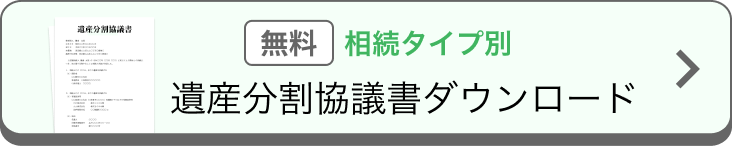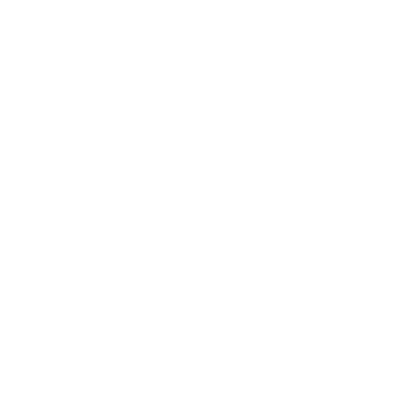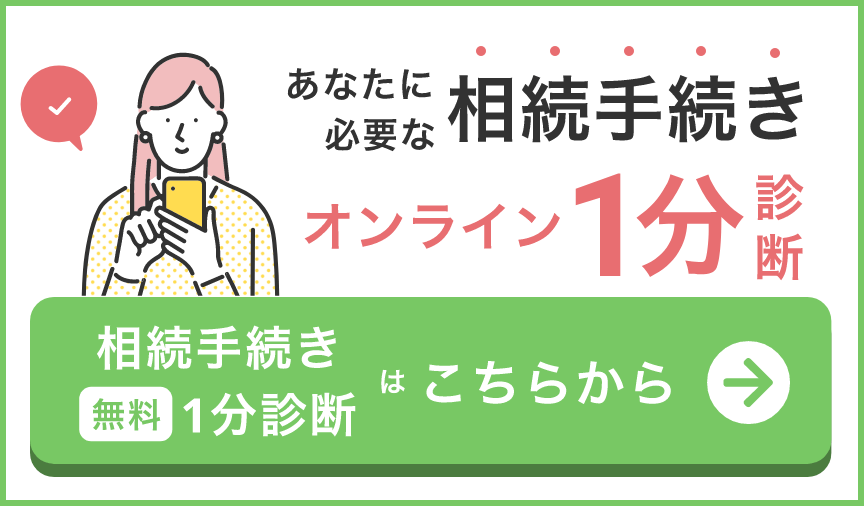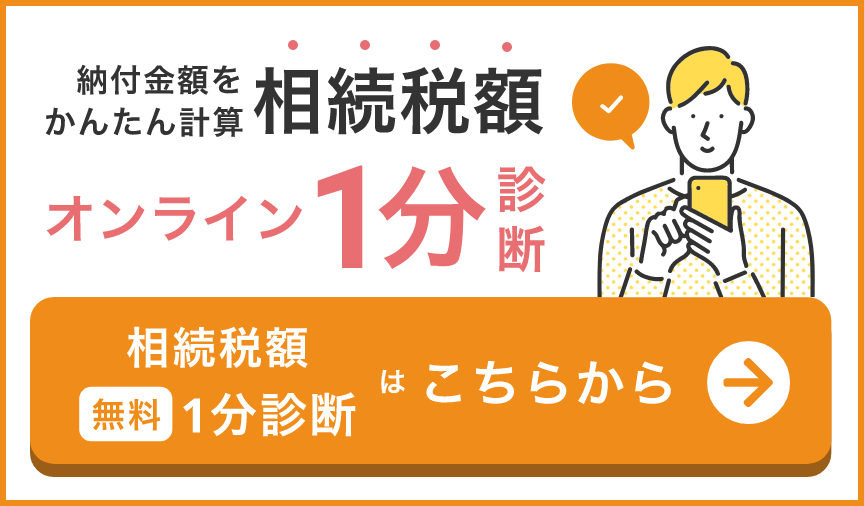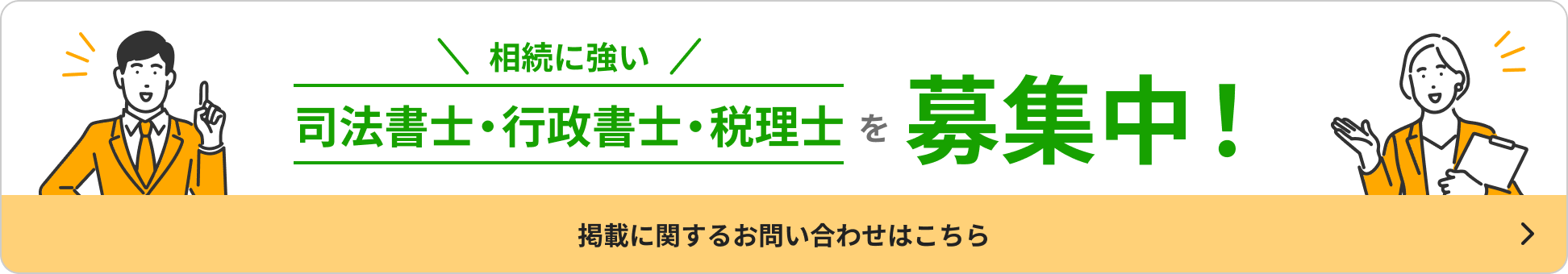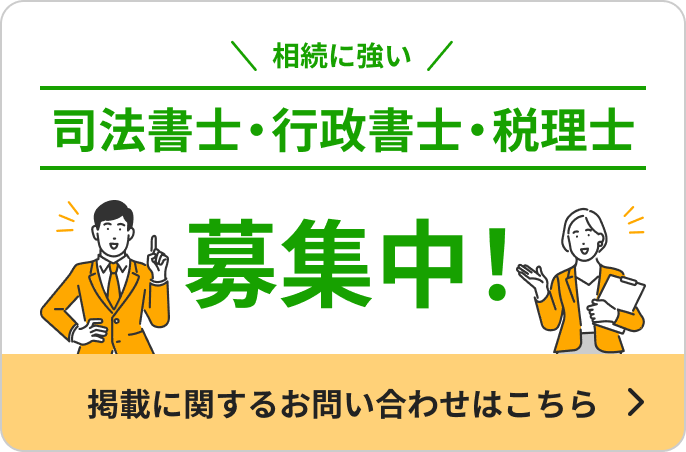遺贈にかかる税金は相続税だけではない!基礎控除や計算方法を説明
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2019年6月28日に公開された記事を再編集したものです。

遺贈を受けた人や、遺贈によって財産を譲与しようと考えている人にとって、「遺贈すると、どのような税金が、いくらかかるのか」ということが気になるのではないでしょうか?
そこで、この記事では、遺贈にかかる税金についてわかりやすく説明します。


この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。


遺贈とは?
遺贈とは、遺言者が死後に財産を人に無償で譲与することです。
遺贈は、相続人に対してだけでなく、誰に対してでもすることができます。法人に遺贈することもできます(なお、遺贈を受ける人を「受遺者」といいます)。
遺贈する場合は、遺贈する旨を遺言します。
相続人に遺言で財産を譲与したい場合は、遺贈のほか、相続させる旨の遺言をする方法があります。
遺贈よりも相続させる旨の遺言の方が相続開始後の手続面において有利なので、相続人に対して遺言で財産を譲与する場合は、遺贈ではなく相続させる旨の遺言の方をお勧めします。
一方、相続人以外の人に対して遺言によって財産を譲与する場合、相続させる旨の遺言をすることはできず、遺贈のみが選択肢となります。
また、遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、財産の全部又は一部を包括的に遺贈するもので、財産に対する一定の割合を示してする遺贈をいいます。
特定遺贈とは、特定の物や権利、あるいは一定額の金銭を与えるというように、財産を特定してする遺贈(割合で示されていない遺贈)をいいます。
遺贈にかかる税金
遺贈を受けた財産には、次の税金がかかる場合があります。以下、それぞれについて説明します。
遺贈を受けた財産の相続税の計算方法
遺贈を受けた財産は、相続した財産と同じく、相続税の課税対象となります。
なお、ここでは特に遺贈と関連が深いポイントに絞って説明するので、相続税の詳しい計算方法については関連記事をご参照ください。
基礎控除
相続税には基礎控除があります。
受遺者や相続人の全員が遺贈や相続等によって取得した遺産の合計額が基礎控除額以下の場合は全額が控除されるので、結果として相続税はかからないことになります。
相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
つまり、法定相続人が1人増えるごとに、基礎控除額は600万円増えます。
この点、遺贈によって遺産を取得する人の数が増えても法定相続人の数は変らないので、遺贈は基礎控除額に影響しません。
2割加算
相続や遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)の一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人の場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
一親等の血族とは、父母と子(養子を含む)のことです。
配偶者の父母や連れ子は一親等の血族ではありませんが、連れ子でも養子にした場合は一親等の血族になります。
なお、養子でも、代襲相続人でない被相続人の孫は、例外的に2割加算の対象となります。
代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹が生きていれば法定相続人であったが相続開始以前に死亡していたというとき(相続欠格や廃除によって相続権を失ったときも含む)に、その人の子が代襲して相続人となることができる制度で、代襲して相続人となった人のことを、代襲相続人または代襲者と言います。
死亡保険金
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされ、いずれの場合でも相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
| 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 |
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
寄付
遺贈による寄付と税金の関係について説明します。
相続税は個人に課せられる税金なので、法人が遺贈を受けた場合、受遺者である法人には相続税はかかりません。
法人が遺贈によって得た経済的利益には、通常、法人税がかかります。
ただし、公益法人等には税制優遇があり法人税がかからないことがあります。
また、法人に遺贈した場合は、被相続人にみなし譲渡所得が生じ、準確定申告(納税者が亡くなった年の確定申告)によって所得税等を納付しなければならないことがありますが、この譲渡所得についても、公益法人等への遺贈の場合は、一定の要件を満たすことで非課税となる特例があります。
また、個人が相続や遺贈によって取得した財産であっても、「宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」については、相続税がかかりません。
他方、相続人や受遺者が、相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付した場合において一定のときは、相続税がかかりません。


遺贈を受けた不動産に不動産取得税がかかる場合とその計算方法
不動産取得税とは、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得者に対して課税される税金です。
有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。
ただし、相続、包括遺贈や、相続人に対してなされた特定遺贈の場合には、不動産取得税はかかりません。
つまり、遺贈に関して不動産取得税がかかる場合は、相続人以外の人に対してなされた特定遺贈の場合のみということになります。
不動産取得税の税額の基本的な計算方法は、「課税標準×4%」です。
しかし、2021年3月31日までに取得した土地と住宅については、税率が3%になります。
課税標準は、原則は、固定資産税評価額と同額ですが、2021年3月31日までに取得した宅地については、課税標準が「固定資産税評価額の2分の1」になります。
つまり、2021年3月31日までに取得した宅地の不動産取得税は、固定資産税評価額の1.5%になります。
固定資産税評価額は、市町村役場(東京23区は都税事務所)で管理している固定資産課税台帳に記載されています。
マンションの場合は、通常、敷地権が付いているので、区分建物(専有部分)にかかる税額と敷地権にかかる税額を合計します。
敷地権の固定資産税評価額は、敷地全体の固定資産税評価額に敷地権の割合(共有持分)を掛け算して計算します。
敷地権の割合も固定資産課税台帳に記載されています。
なお、マンションの敷地も、宅地なので、課税標準が固定資産税評価額の2分の1になります。
また、不動産取得税には、様々な税額軽減措置があります。
不動産取得税について詳しくは「不動産取得税は相続の場合は非課税で申告も不要!登録免許税はかかる」をご参照ください。
遺贈を受けた不動産を登記する際の登録免許税の計算方法
登録免許税は、不動産の登記等をする際にかかる税金です。
遺贈によって取得した不動産を登記する場合にも登録免許税がかかります。
受遺者が法定相続人かどうかによって税率が異なります。
法定相続人の場合は0.4%で、法定相続人でない場合は2%です。
登録免許税の税額は、「固定資産税評価額×税率」で計算します。
遺贈を受けた不動産を譲渡した場合の譲渡所得にかかる税金の計算方法
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます(ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはならず、事業所得などになります。)
ここでは、特に、土地や建物についての譲渡所得について説明します。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
「収入金額 − (取得費 + 譲渡費用) − 特別控除額 = 課税譲渡所得金額」
収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。
取得費には、売却した不動産を遺言者が取得した時の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
具体的には、次のようなものが取得費に含まれます。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
- 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税 ※業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。
- 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料
- 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
- 土地の取得に際して支払った土地の測量費
- 所有権などを確保するために要した訴訟費用 ※例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用のことをいいます。相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません。
- 建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
- 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
- 既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
また、遺贈により取得した財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を取得費に加算することができます(詳しくは「取得費加算の特例を受けて譲渡所得税を軽減させる方法」参照)。
これを「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいますが、この特例は、後述の「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」との併用ができません。
税額を試算して、より税額が低くなる方の適用を受けるようにしましょう。
取得費が分からない場合は、収入金額の5%相当額とします(この場合には、相続人などが支払った登記費用などを取得費に含めることはできません。)。
また、取得費が収入金額の5%未満の場合も、収入金額の5%とします。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
そして、特別控除には、様々なものがありますが、相続した不動産について特に関係するものに、「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例」があります。
「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例」とは、空き家となった被相続人(亡くなった人)の住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡し、一定の要件に当てはまる場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除するというものです。
詳しくは「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例の適用を受けるための知識」をご参照ください。
不動産に対する譲渡所得税の税率は、長期譲渡所得と短期譲渡所得とで異なります。
長期譲渡所得の場合は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)、短期譲渡所得の場合は39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)です。
不動産を売った年の1月1日現在で、その不動産の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得に、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
遺贈によって取得した不動産については、遺言者の所有期間と相続人の所有期間を通算して判定されます。
例えば、30年前に遺言者が1000万円で取得した不動産を相続し3000万円で譲渡しその譲渡費用が100万円だった場合は、長期譲渡所得なので税率は20.315%となり、譲渡所得税額は、「3000万円−(1000万円+100万円)×20.315%=385万9850円」となります(取得費加算と特別控除がない場合)。


遺贈と死因贈与、それぞれにかかる税金の違い
遺贈と似たようなものに死因贈与があります。
死因贈与とは、自分の死後に財産を譲ることを、財産を譲り受ける者との間で生前に約束しておくことをいいます。
遺贈と死因贈与には、それぞれにかかる税金に違いあり、遺贈の方が有利になるケースがあります。
まとめ
以上、遺贈にかかる税金について説明しました。
遺贈にかかる税金について不明な点は、相続に精通した税理士に相談することをお勧めします。


▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。


ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。