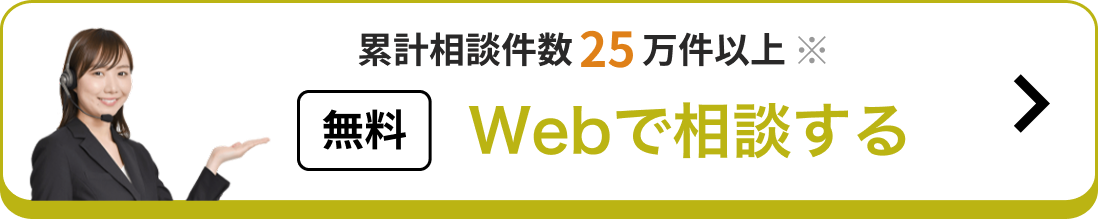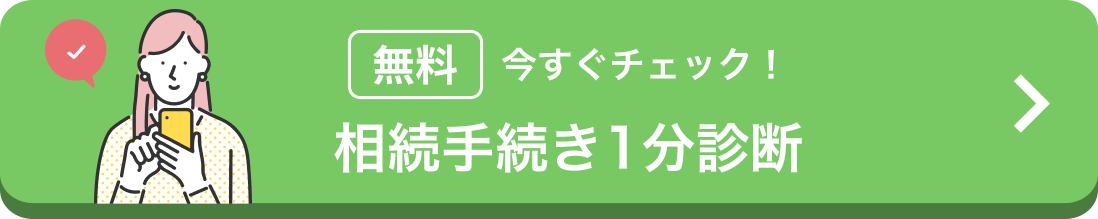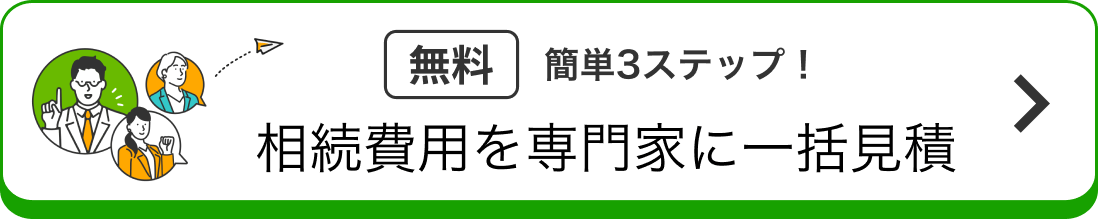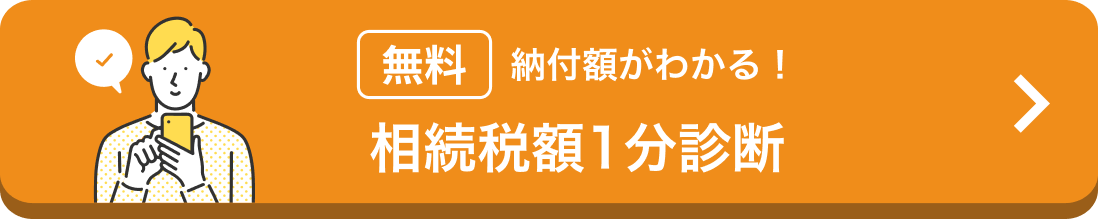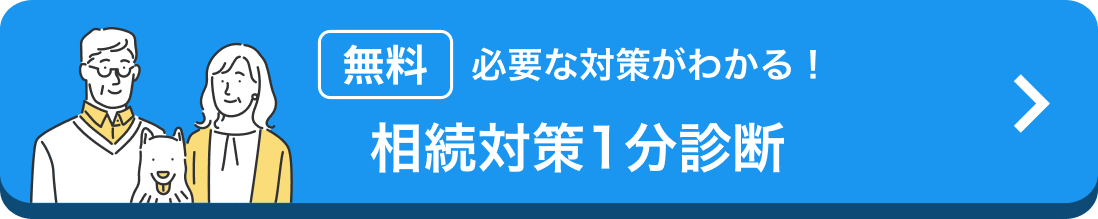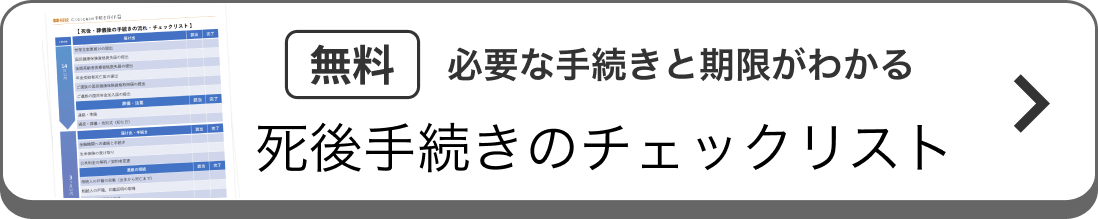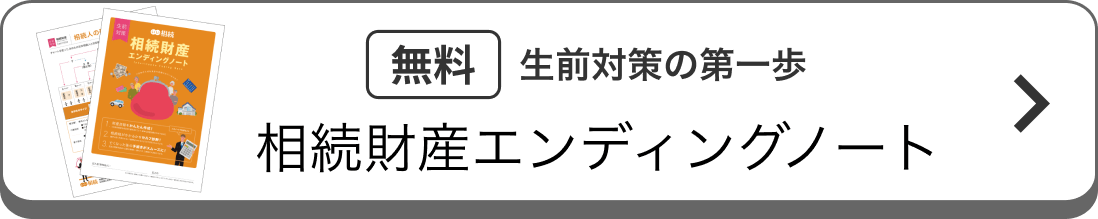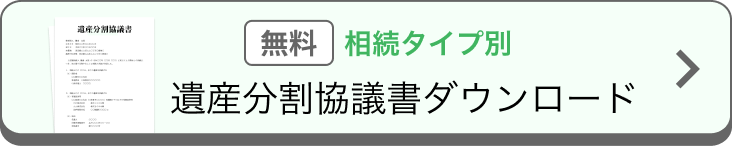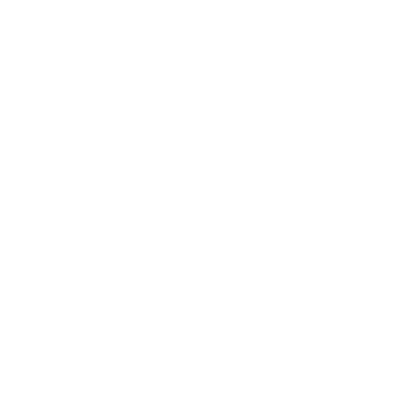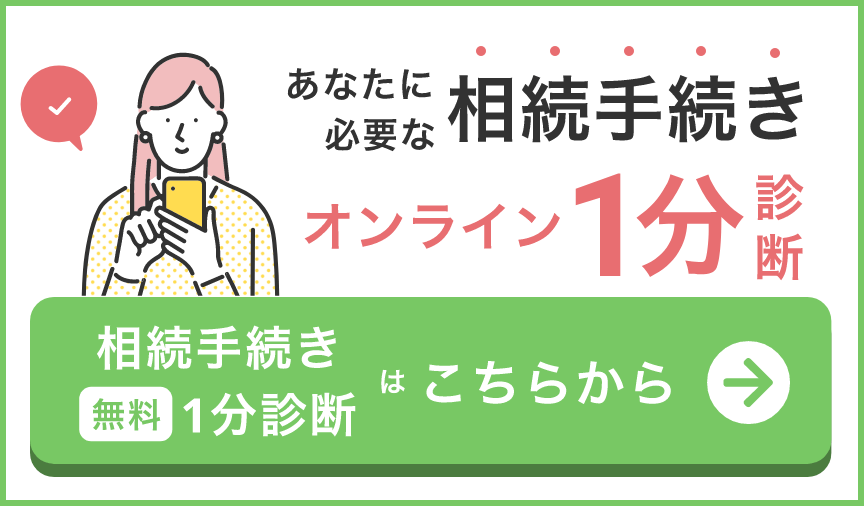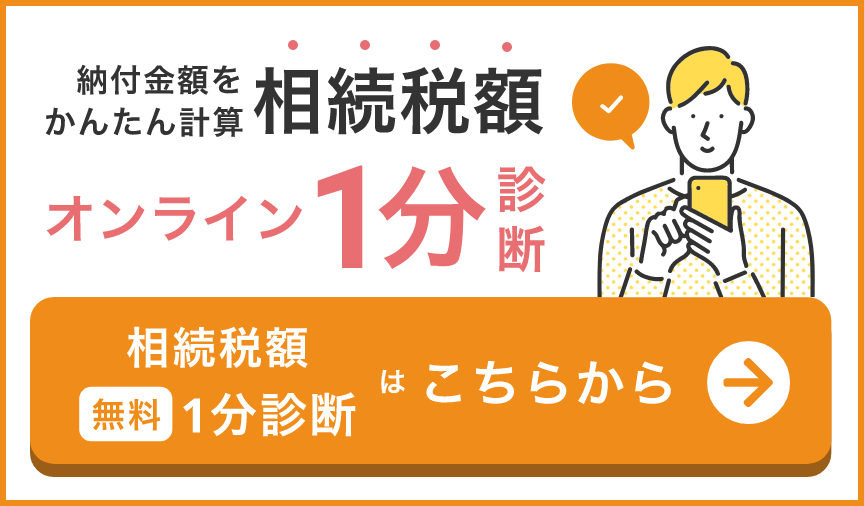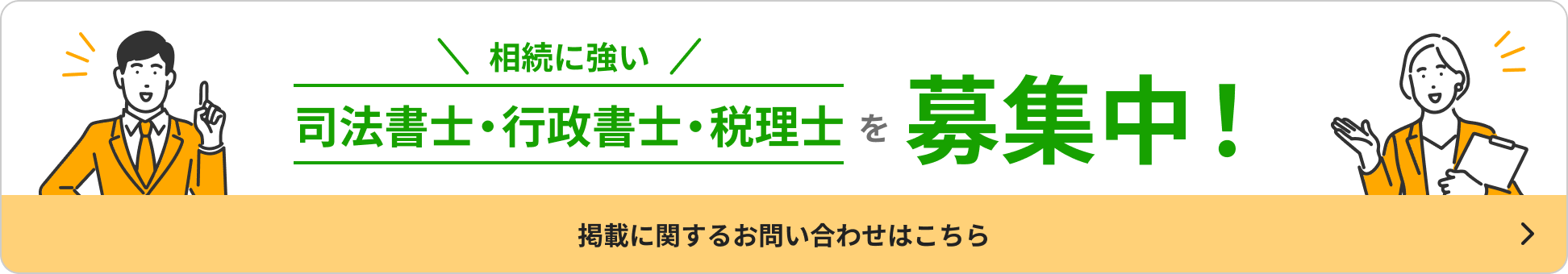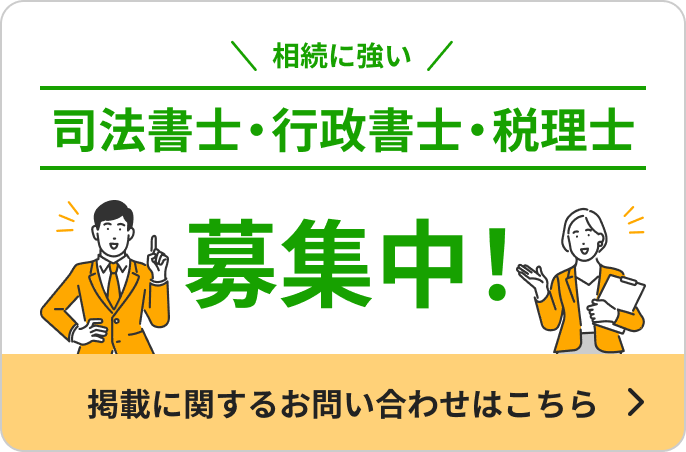生前にお墓や仏壇を買っておくと節税になるって本当ですか?

相続税対策として事前にできる相続税対策の一つが「非課税財産を取得すること」です。 ただ、この対策をする際には気をつけなければならない点がいくつかあります。
非課税になる相続財産とは
相続税の課税対象となる財産から除外される「非課税枠」を使った節税対策はいくつかありますが、生命保険金の非課税枠として設けられている「法定相続人×500万円」を活用する、祭祀財産等の購入をするなどの方法がしばしば見受けられます。
祭祀財産とは、墓地や仏壇、神具、仏像等を指します。通常、これらの祭祀財産は換金目的で所有するものではなく、先祖を崇拝するための儀式的な慣習色が強いため、国民感情に照らし合わせても相続税の課税対象とすることは適切ではないとして非課税財産とされているのです。

祭祀財産は生前に購入しておく必要がある
相続税の課税時期は、相続発生時となります。そのため相続税の対象となるか否かの判断も相続発生時点の財産の現況により判断されます。 相続発生後に祭祀財産を購入しようと考えていたとしても、相続発生時点ではあくまで「現金」として判断されてしまい、相続税の課税対象に組み込まれてしまいます。
このように祭祀財産は被相続人の死後に購入しても節税の意味はありませんので、被相続人(亡くなった人)がまだ元気なうちから計画的に購入しておくことが必要です。
祭祀財産は現金で購入しておくことが重要
相続税の非課税となる祭祀財産の取得、維持又は管理のために生じた債務は、債務控除の対象外となると規定されています。つまり、ローンで購入した際の残債務や未払金については債務控除の対象外となるので、相続税の非課税枠を最大限に利用したいのであれば現金で祭祀財産を購入する必要があります。
すべての祭祀財産が適用になるわけではない
相続税の非課税となる祭祀財産は、日常礼拝をしている物に限られます。これは祭祀財産を非課税扱いにした理由が、上記のとおり「先祖を崇拝するための財産に課税するのは国民感情の観点からも適当ではない」との判断からであることから考えたら当然の扱いといえます。 そのため、購入した祭祀財産が商品や美術品・骨董品あるいは投資対象物と認定されてしまうと非課税扱いにはならず、相続税の課税対象となってしまいます。
その家族が住んでいる家やその他の家具・調度品などとのバランスから考えても明らかに分不相応に祭祀財産だけが豪華な場合は課税されてしまうことがありますので注意が必要です。

ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。