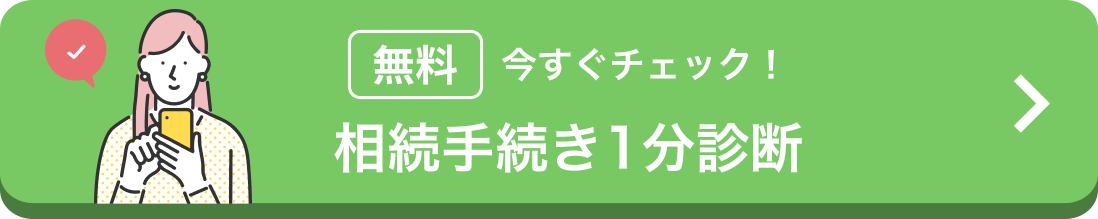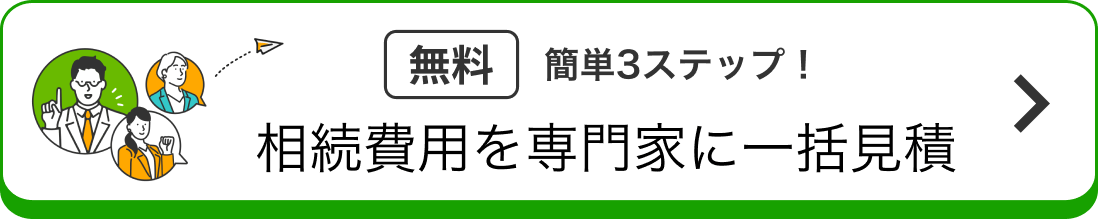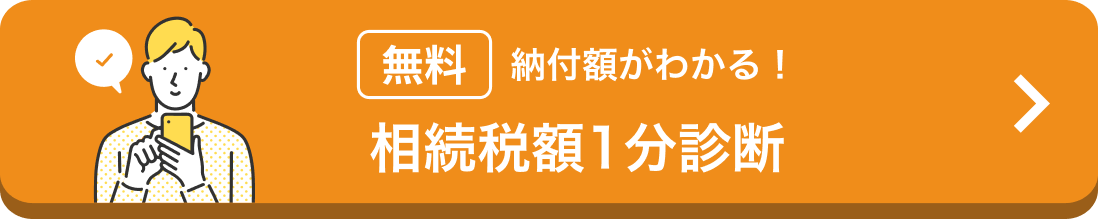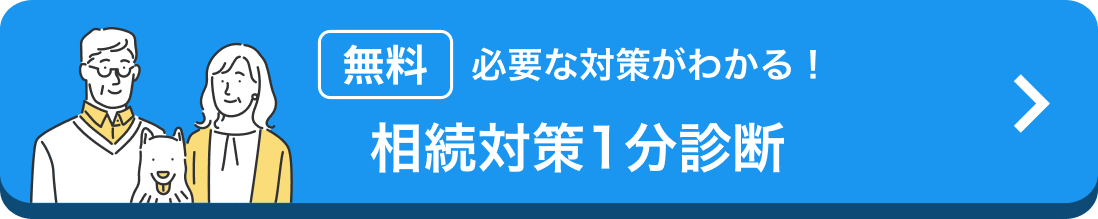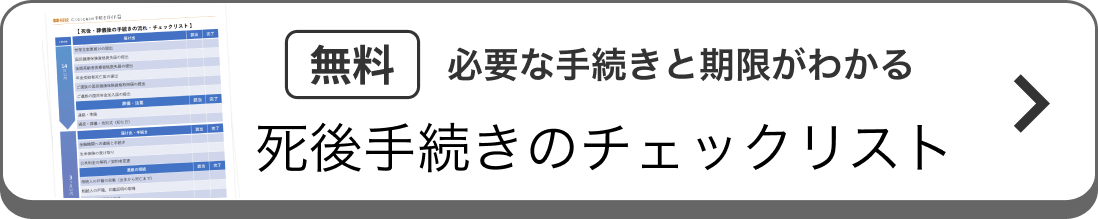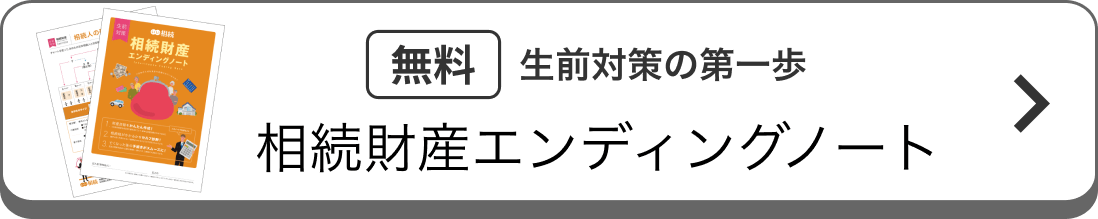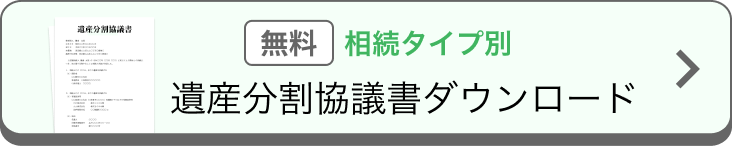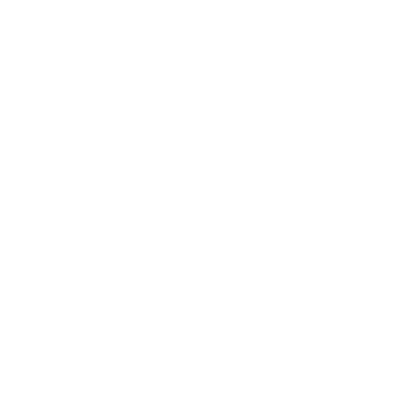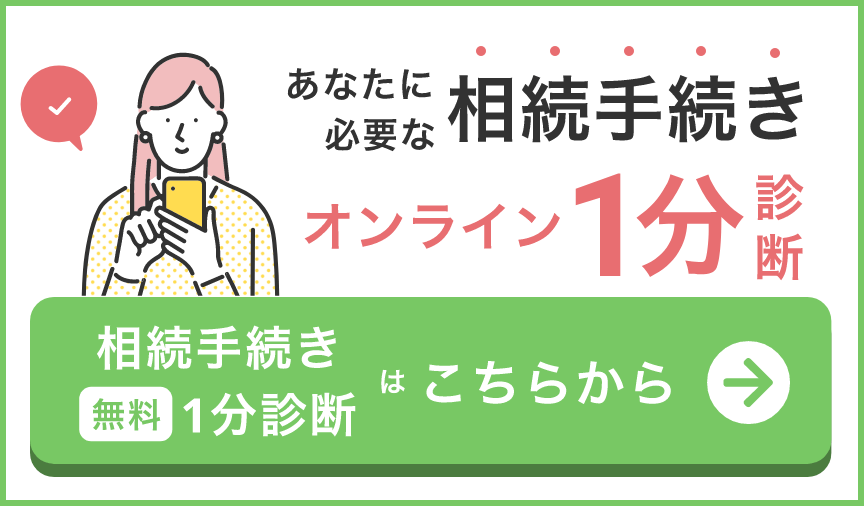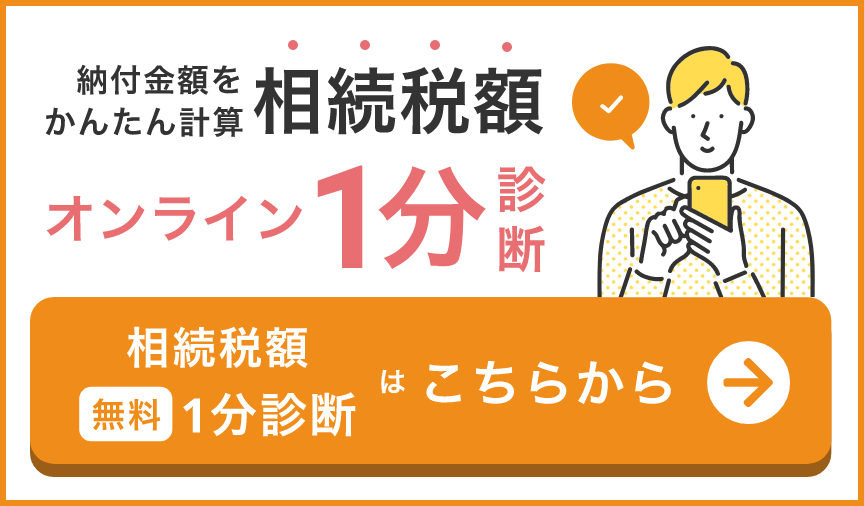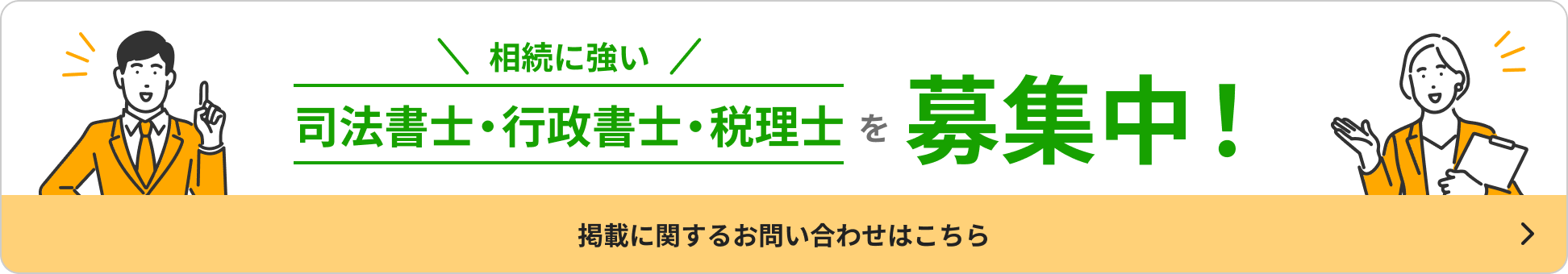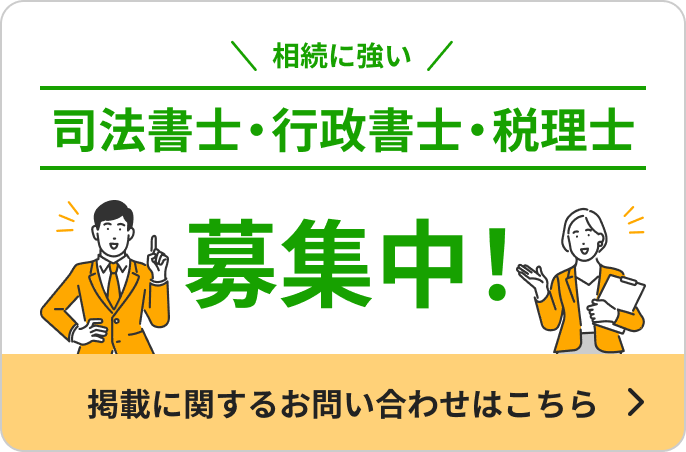エンディングノートの作り方は?書くべき内容や選び方、注意点についても解説

最近、終活への関心が世間で高まっているなかで、「エンディングノート」という言葉を聞くかと思います。エンディングノートとは、人生の終末期における考えや希望、遺志などを記しておくノートです。
エンディングノートを書いておくことによって、自分が亡くなった後、家族が困ることも少なくなるでしょう。今回はエンディングノートの作り方について解説します。


エンディングノートとは
エンディングノートとは、終活に関する自分の考えや希望などを残しておくためのノートです。「終活ノート」「生前整理ノート」と呼ばれることもあります。
エンディングノートに記載する内容は、例として以下のものがあげられます。
- 介護や葬儀、お墓の希望
- 家族や友人への感謝の気持ち
- 自分史や資産情報、パスワード
エンディングノートを作成しておくことによって、事故や病気によって判断力を失ったり、突然この世を去ったときでも、残された家族がスムーズに手続きをおこなうことができます。身辺整理や生前整理の一環としておこなう目的もあります。
エンディングノートと遺言書の違い
エンディングノートに関連する言葉で「遺言書」を聞いたことのある人もいるでしょう。エンディングノートと遺言書は違うものです。
エンディングノートと遺言書は、「法的拘束力の有無」が大きな違いです。相続で有効な遺言書は法律で決められた形式があり、それに則って作成されたものは法的な効力を持ちます。
遺言書はその形式の違いから「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などいくつかの方式に分かれています。遺言書を作成する際には、その要件や違いなとをきちんと把握してから作成すると良いでしょう。
一方、一般的なエンディングノートは遺言書としての形式が取られていないものがほとんどなので、相続に備えるための遺言書の代用にはなりません。
したがってエンディングノートに書かれた内容を必ず実行する必要はない、ということを認識しておきましょう。


エンディングノートの作り方
エンディングノートの形式は自由です。したがって自分の好きなノートを買ってきて書いたり、パソコンやスマホのアプリで作成してもかまいません。
また、エンディングノート専用のノートも発売されています。専用のノートにはあらかじめ書くべき項目などがノート内に印刷されています。専用ノートと言っても、気に入ったデザインや好みのものを選んでかまいません。


エンディングノートに書く内容
では、エンディングノートにはどのようなことを書けばよいのでしょうか。後で抜け漏れがないよう書き終わったら見直しをし、他に書いたほうがよい項目があれば追記していきましょう。
自分の個人情報
基本的な個人情報をエンディングノートに記載しておくと、自分が亡くなった後に家族が相続手続きをする際にスムーズに進めることができます。
またエンディングノートに自分史を記載しておくことによって、遺族に自分の人生を伝えられたり、自分がどのような思いを抱いていたかを伝えることができます。
- 氏名
- 生年月日
- 現住所
- 本籍地
- 家族構成
- 家系図
- 血液型
- 健康保険証番号
- 運転免許証番号
- マイナンバー
自分のプロフィール
- 自分史
- 思い出
- 経歴・資格
- 趣味・特技
- 性格・信念
- 親しい友人
- よく行くお店
- 好きな食べ物
財産の情報
財産の情報も、エンディングノートに書くべき重要な項目です。何の財産があるのか、ローンや借金は残っているのか、必要書類の保管場所や口座の暗証番号など、必要な情報を記載しましょう。
自分が亡くなったあと削除してほしいSNSや会員情報などがある場合、IDやパスワードなども記載しておきましょう。
- 預貯金
- 保険
- 年金
- 不動産
- 有価証券(株式・債券・手形・小切手)
- 負債(借入金)
- タンス貯金
- 貴金属
- 骨董品
- その他、価値のあるコレクション
医療・介護の希望
終末医療や延命治療に関しても、エンディングノートに書いたほうが良い項目です。自分の判断能力がなくなった場合に、家族が決断するのも大変なことです。エンディングノートに記載しておくことによって「本人の意思を尊重できた」と遺族に安心してもらえるでしょう。
他に、緊急入院する際となった場合に備えてかかりつけ医やよく行く病院なども記載し、加えてアレルギーや持病、常備薬などがあれば記入しておきましょう。
- 希望する介護スタイル
- 入居予定の介護施設
- 終末医療・延命治療の希望
- 臓器提供の有無
- かかりつけ医と病院
- アレルギーや持病、常備薬
葬儀・お墓の希望
一昔前まで本人が葬儀やお墓について決めるのは一般的ではありませんでした。しかし近年では、葬儀やお墓の選択肢が多様化し、本人が希望する葬儀の形式を選ぶケースが増えています。「縁起が悪い」といって話しにくい内容ではありますが、事前に家族で話し合いをしておくことが望ましいです。
自分の葬儀やお墓にこだわりがある人は、詳細をエンディングノートに記載しておいたほうが、遺族もやりやすいでしょう。
- 信仰している宗教
- 葬儀の形式
- 喪主
- 招待したい参列者
- 遺影の写真
- 葬儀社・斎場
- 納骨方法・場所
- お墓の有無・希望
相続・遺言
前述のとおりエンディングノートには法的拘束力がないため、エンディングノートとは別に遺言書を作成する必要があります。遺言書の保管場所を記載しておくと良いでしょう。
形見分けとは故人の親族や親交のあった人へ遺品を贈り、思い出を分かち合う日本の風習です。形見であっても金額が大きい品物は相続権に触れる可能性があります。高価な形見があるときは、形見わけについても遺言書に書いておくといいかもしれません。
- 遺言書の有無
- 遺言書の保管場所
- 遺言書の種類
- 形見わけ
- 連絡先
エンディングノートには、親しい友人・知人の連絡先を一覧でまとめておくと便利です。他にも、日頃連絡をとっている所属先などがあれば記載しましょう。
入院や訃報の連絡、葬儀の案内などを遺族が友人にしたい場合に役に立ちます。また友人宛のメッセージをエンディングノートに記載しておけば、遺族が伝えてくれるかもしれません。
家族や親族へのメッセージ
家族や親族へのメッセージを、ぜひエンディングノートに残すことをおすすめします。
自分が死ぬ直前は、家族や親族とゆっくり話をできないかもしれませんし、面と向かって感謝の気持ちを伝えるのは恥ずかしいと感じる人もいるでしょう。だからこそ、自分の素直な気持ちをエンディングノートに記載しておくと後悔がないでしょう。
文章で書くのが苦手という人はイラストや動画を撮ったり、思い出の写真を添えても良いでしょう。
ペットの情報と引き取り先
一人暮らしでペットを飼っているなら、引き取り先を決めておかなければなりません。家族や親族が受け入れてくれればよいですが、難しい場合は事前に希望者を探しましょう。
また引き取り先とあわせて、ペットの情報も書き記しておくと安心です。名前や年齢はもちろん、健康状態や性格、趣味嗜好を書いておくことで、次の飼い主がペットを受け入れやすくなります。
- ペットの名前
- 年齢
- 性別
- 健康状態
- 病歴
- かかりつけの病院
- 性格
- 好きなペットフード
- お気に入りのオモチャ
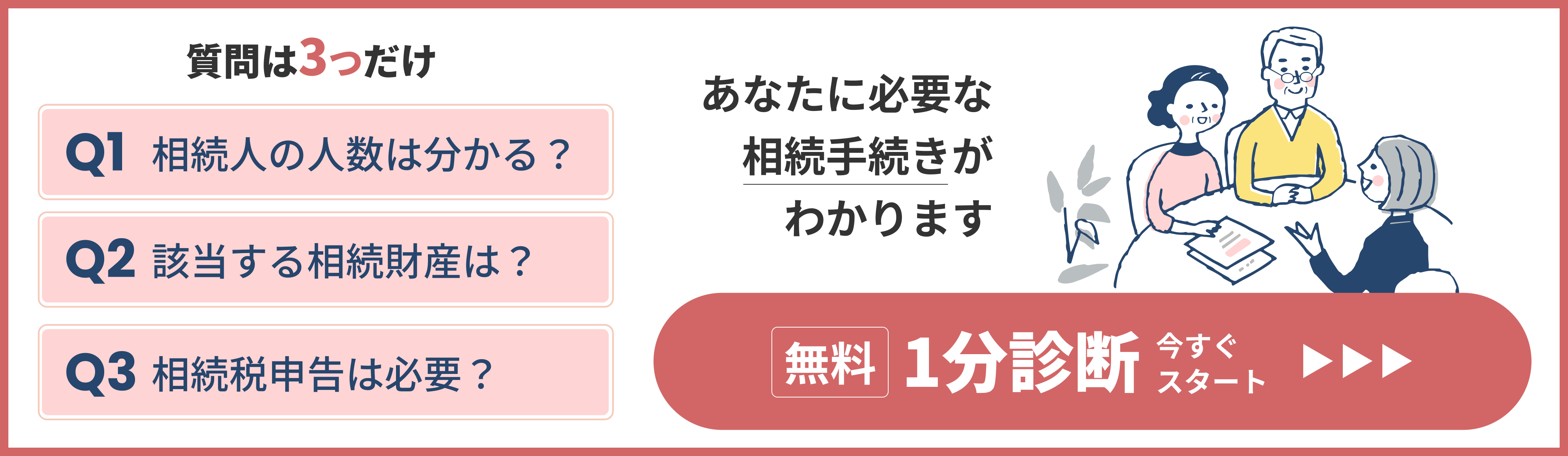
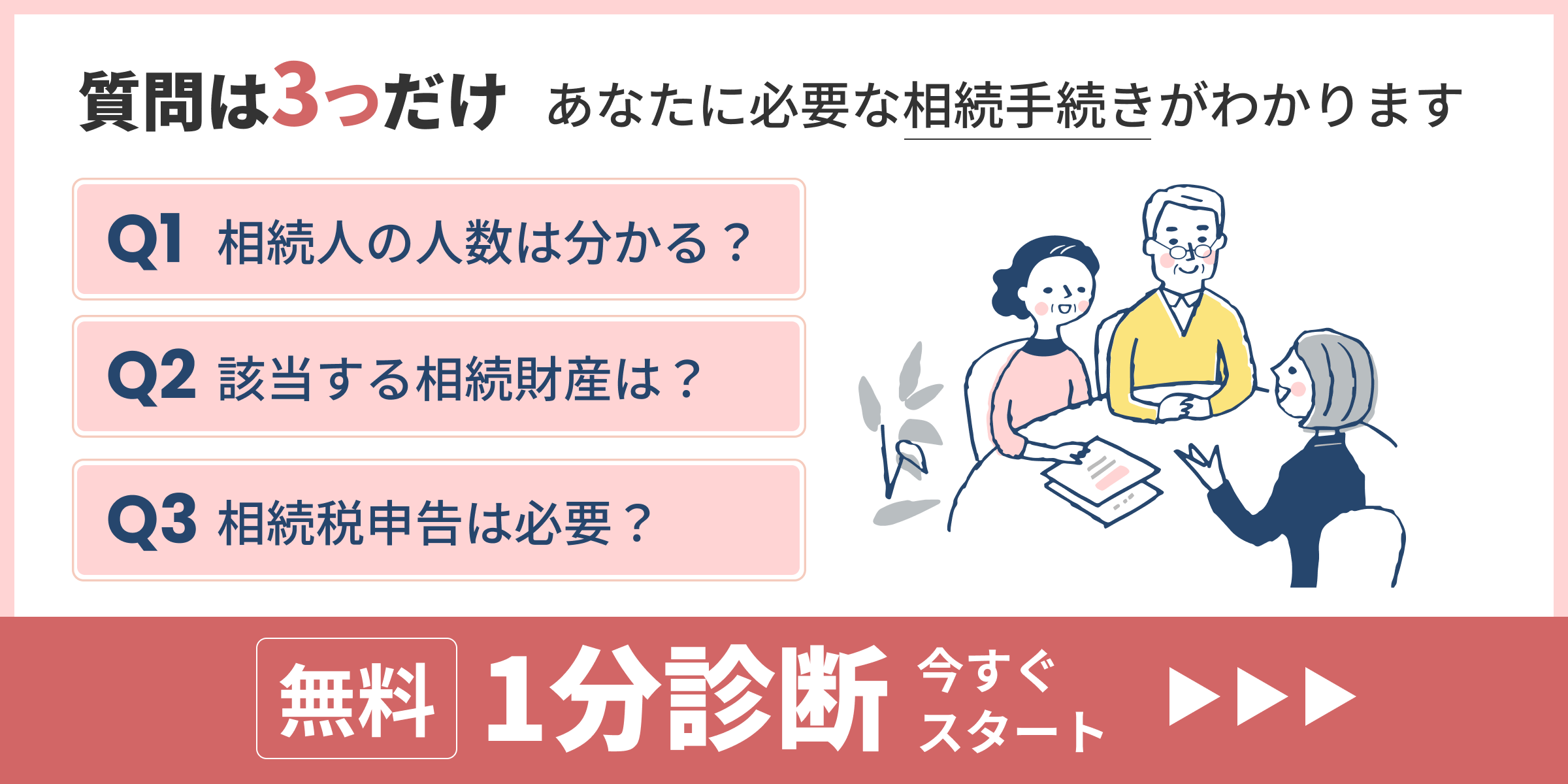
エンディングノートの選び方
いろいろな種類のエンディングノートが販売されています。購入する際には実際に中身を見て、目的に合ったものを選びましょう。
自分の人生を振り返りたい
自分の人生を振り返りながらエンディングノートをまとめたい人は、自分史の年表やプロフィールページが充実しているノートを選びましょう。項目を埋めていくだけで、これまでの思い出や経験を振り返ることができます。
残された家族の負担を減らしたい
家族の手続きの手間や負担を減らしたい場合は介護や葬儀、相続の項目が充実しているエンディングノートを選ぶと良いでしょう。ノートの項目ごとに書いていけば抜け漏れなく情報を整理して記載することができます。
特に介護や延命治療については、自分らしい最期を迎えるためにも、元気なうちから考えておくことをおすすめします。
備忘録として使いたい
自分が亡くなるまでの間に備忘録としてエンディングノートを使いたいなら口座情報や保険、クレジットカード番号などの項目があるノートがおすすめです。
自由に自分らしいノートを作りたい
イラストや写真で自分らしいノートを作りたい、自由に記述したいという人は無地のノートがおすすめ。エンディングノート用のノートでなくても、自分の好きなノートを選んで自由に書いてかまいません。


エンディングノートの注意点
エンディングノートを作成する際には、どのような点に注意すればよいのかを解説します。
個人情報を記載した場合厳重に保管する
エンディングノートに個人情報を記載した場合は、鍵付きの引き出しや金庫など、人目のつかない場所で厳重に保管するようにします。
口座情報やパスワードなど、エンディングノートには重要な個人情報がたくさん記載されます。万が一紛失したり、他人に見られたりした場合、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
ただし、銀行の貸金庫に保管するのは推奨しません。貸金庫を開けるまでに手続きが必要となるため、手間がかかってしまいます。
信頼できる相手に保管場所を伝える
エンディングノートは厳重に保管する必要はありますが、最低限家族や信頼できる相手には保管場所を伝えておきましょう。
エンディングノートが見つけられないと作成した意味がありません。故人の意思が反映されなくなったり、遺族が手続きに手間がかかってしまいます。
エンディングノートに法的拘束力はない
前述のとおり、エンディングノートに法的拘束力はありません。したがって、必ず希望どおりになるとは限らないので注意しましょう。
相続について法的に希望を残したい場合は、遺言書をあわせて作成しておくことをおすすめします。遺言書には要件があるため、作成にあたっては行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。エンディングノートの内容は定期的に見直す
エンディングノートは定期的に見直し、古い内容があれば書き直しましょう。記載した当時とは状況が変わったり、気持ちの変化もあるかもしれません。完成したら終わりではなく、何度か見直して修正することによって、自分の希望をより正確に残せるでしょう。
エンディングノートに書き方の決まりはないため、あとからページをつけ足したり追記してかまいません。
まとめ
今回はエンディングノートの作り方について解説しました。エンディングノートを作成しておくと、もし自分が亡くなった後も遺族がスムーズに手続きができるでしょう。また、家族への思いなどをエンディングノートに記載しておくのも良いですね
エンディングノートを作成する際は、あわせて遺言書も作成しておくことをおすすめします。遺言書の作成や生前対策をしたい場合は、ぜひ、いい相続までお問い合わせください。相続に強い専門家をご紹介します。


▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きや遺言書の作成を依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。